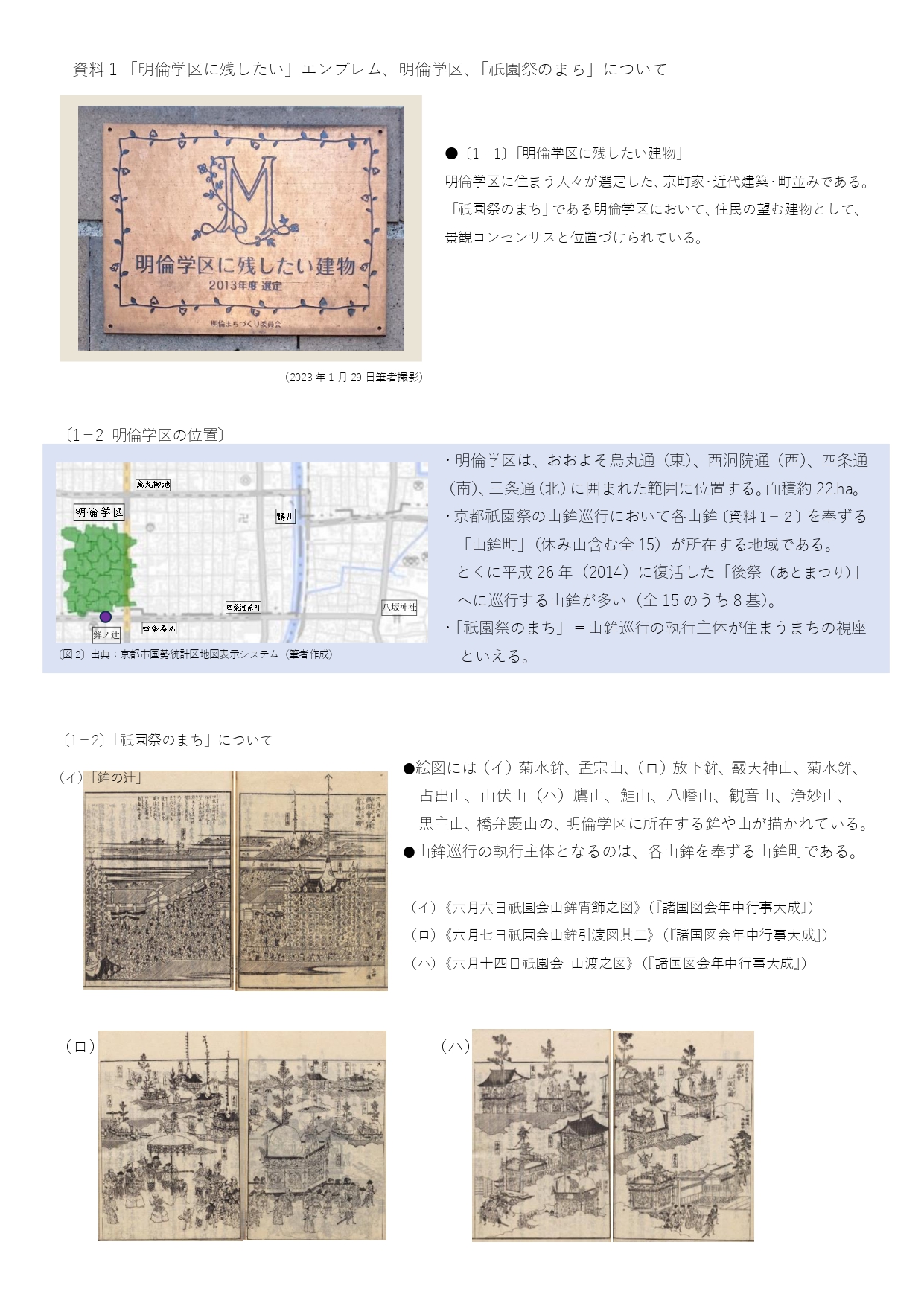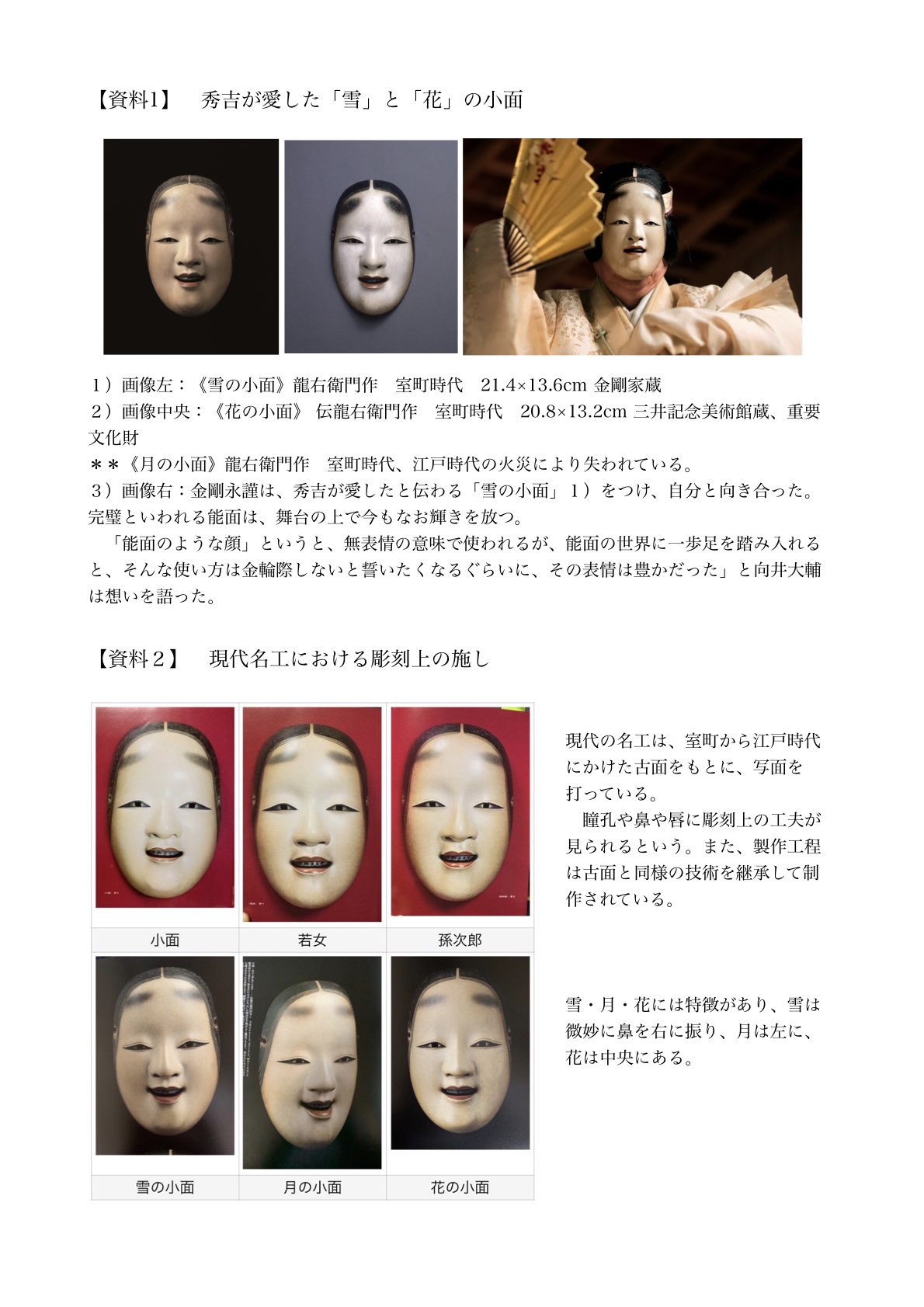伝統と現代が交差する日本の”美”京都「櫛まつり」
移り変わりの激しい現代社会で、伝統行事を継続させることは決して簡単なことではない。日本の”美”でもある、伝統と現代の結髪技術を実際に拝見できる、京都「櫛まつり」の取り組みを追ってみる。
1 基本データと歴史的背景
1-1.「櫛まつり」とは
京都市東山区にある安井金比羅宮にて、使い古した櫛やかんざしに感謝を込めて、お清めし供養するお祭りのことである。1961年(昭和36)から行われており、安井金比羅宮の境内に久志塚(櫛塚)が建立されたことがきっかけにより始まったとされる(図1)【資料5】。京都美容文化クラブ櫛まつり実行委員会により実行されており、例年9月の第4月曜日に行われている。昔は「櫛(くし)」から、9月4日に行われていたとされる。「櫛まつり」が行われる安井金比羅宮は、縁切り縁結び碑が置かれており、あらゆる悪い縁を切り良縁を結ぶとされる御利益で全国的にも有名な神社である(図1)【資料5】。「櫛まつり」では、髪の美しさを引き立てる櫛をお祀りする事で、美のご利益があるともされている。一般の方も使い古した櫛や折れた櫛があれば、供養できるとのこと。
1-2.行事当日
午後1時より塚の前で祭典が執り行われ(写真4,5)【資料2】、寄せられた櫛が塚内へ納められ(写真6)【資料2】、拝殿にて舞踊の「黒髪」が奉納される(写真7)【資料3】。2時頃より、伝統の髪型と風俗衣装の解説行われ(写真8)【資料3】、時代風俗行列が神社周辺祇園界隈を練り歩く(写真9,10)【資料4】。時代風俗行列の順路は、安井金比羅宮→東大路通→四条通西へ→花見小路北へ→新橋西入へ→白川筋→花見小路南へ→安井北門通り→安井金比羅宮 (図2)【資料5】雨天の場合、行列巡行は中止される。
2. 事例のどんな点について積極的に評価しているのか
「櫛まつり」は日本女性の美の伝統、アイデンティティを大切にしており、日本髪の美しさと高度な結髪技術を見ることができる点、各時代の髪型の解説を聞くことができる点を積極的に評価している。さらに、伝統の髪型と風俗衣装をまとった時代風俗行列が京都の風景、雰囲気のある祗園界隈を練り歩く姿は、まさに歴史絵巻であり魅力的である。グローバル化が進む現代において、古代から現代の日本髪を実際に見る機会というのは、非常に珍しく貴重である。これらの習熟した結髪の技術を要する髪型は「櫛まつり」を主催されている美容師の集まりで構成された、京都美容文化クラブの方々により伝統の髪型が現代に再現されているのである。実際に、結髪にはマーセルコテや櫛など昔の美容道具を使い(写真2,3)【資料1】、髪の毛を分ける際にも現代にある便利なヘアクリップではなく紙を使い縛り分け(写真1)【資料1】、モデルの方も毛染めをしていない地毛で、伝統の髪型は結われている。日本髪の技術は講習や勉強会にて伝えられ、それぞれの美容室や学校にて技術の向上に練習されている。また、担当する髪型を決める方法は事前にくじ引きで決定される。これらの活動は、美容業界において日本髪を専門に扱う美容室やスタイリストが増え、国内外問わず日本文化に興味を持つ人々に対するサービスが広がっていく可能性を秘めている。特に、日本髪の美しさ、高度な技術は海外でも高く評価されており、日本髪の技術が国際的なイベントやファッションショーにも取り入れられ、日本髪をテーマにしたアート作品やパフォーマンスなどが増えている。「櫛まつり」では、美容学生の方々がモデル参加や運営サポートにも貢献しており、美容を学ぶ学生の方々が実際に「櫛まつり」に参加をすることで、若い世代に対しての文化イベント体験にて、結髪技術の受け継ぎにも繋がっているといった点も高く評価できる。
3. 国内外の他の同様の事例と比較して何が特筆されるのか
同じ京都市で行われる伝統行事、京都三大祭りの一つの京都市左京区の平安神宮で行われる「時代祭」は、平安神宮の創建と平安遷都1100年を奉祝する行事として、1895年(明治28)より始まり、桓武天皇が794年(延暦13)に長岡京から平安京に都が移された日と関連して、例年10月22日に、明治維新から江戸、安土桃山、室町、吉野、鎌倉、藤原、延暦と8つの時代を20の列、牛や馬を含む行列が行われる。雨天の場合、行列巡行が順延される。「櫛まつり」は「時代祭」と比較すると行事の規模や知名度は低いが、「時代祭」での江戸時代の婦人列を除く、他の時代行列は地毛ではなく鬘である。一方で、「櫛まつり」においては、古墳時代から現代舞妓の各時代すべての髪型には、鬘が使われておらず、全て地毛で結いあげられた、日本髪が現代に再現されていることが特筆とされる。
4. 今後の展望について
4-1.インターネットの活用
今後「櫛まつり」はさらなる地域振興や観光資源としての発展が期待されている。特に、インターネットやSNSの活用により、若い世代へのアプローチが重要になると考える。若い世代へのアプローチを行うことで、若い技術者達に日本髪の伝統や技術に興味をもってもらうきっかけとなる。まずは、伝統技術を知らない世代に興味をもってもらう機会を増やしていくことが大切である。また、日本国内だけでなく海外にも、国際的な観光客を対象としたインターネットやSNSのプロモーション活動を強化することにより、世界のより多くの人々に「櫛まつり」という伝統行事の魅力を伝えることが可能である。インターネットを使って「櫛まつり」公式サイト作成、時代風俗行列の行列順路マップの記載、巡行されるおよその時間と通りの名前、観覧しやすい場所のポイントのアドバイス、事前告知などの活用にも期待される。
4-2.有料観覧席を設ける
特に、観覧客が多く集まる、塚の前での祭典(図1①)【資料5】や拝殿で舞踊「黒髪」の奉納(図1②)【資料5】、時代風俗行列の白川筋において(図2)【資料5】、観覧スペース確保の活動が行われることにより、より良い空間となるのではないかと考える。今後「時代祭」の様に有料観覧席を設けることにより〈註1〉、企業の協賛や運営資金を増やせることができ、行事の継続に寄与できる。さらに、混雑を避けることで、より良い観覧体験ができるため、観覧客の満足度を高めることもできる。特別な体験や価値が提供されることにより、観光資源としての魅了も高まる。有料観覧席を設けることは「櫛まつり」に新たな可能性をもたらす一方で、有料観覧席を設けることにより、伝統を重んじる地域の方々や行事の本来の趣旨や伝統が損なわれると感じる人が出てくると考える。従って、地域の方々の意見や伝統を尊重しながら、有料観覧席を設ける計画を立てていくことが大切であり、有料観覧席を設けると同時に、観覧者が実際に櫛を使って日本髪を作ってみるなどといった、新たな体験型プロブラムやワークショップを提供する機会が生み出されることも期待される。
5. まとめ
「櫛まつり」に限らず、現代において行われている伝統行事とは、人と人の繋がりにより伝統が新しい世代に伝わっている。それらは、伝統が受け継がれる環境づくりがされていること、さらに今ある情報や資料の再調査が行われ、新しい資料として残っていることなど、あらゆる先代の知識と努力で成り立っている。さらに、伝統行事が行われる地域の方々の力とは、伝統行事が継続させるにあたってとても大切な存在である。今後「櫛まつり」のような貴重で珍しい伝統行事を継続して行くには、やはり地域の方々のサポートと技術の後継者が不可欠であると考える。「櫛まつり」という伝統行事は、日本の古き良き美の歴史を実際に肌で感じ取ることができる。伝統と現代が交差する美の技術、文化の継承が反映される重要な行事と言えるだろう。
-
 櫛まつり (2016年09月26日、筆者撮影)
櫛まつり (2016年09月26日、筆者撮影) -
 (写真1)美容室キミにて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真1)美容室キミにて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真2)美容室キミにて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真3)美容室キミにて(2016年09月26日、筆者撮影) -
 (写真4)安井金比羅宮にて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真4)安井金比羅宮にて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真5)安井金比羅宮にて(2024年09月23日、筆者撮影)
(写真6)安井金比羅宮にて(2024年09月23日、筆者撮影) -
 (写真7)安井金比羅宮にて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真7)安井金比羅宮にて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真8)安井金比羅宮にて(2016年09月26日、筆者撮影) -
 (写真9)白川筋にて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真9)白川筋にて(2016年09月26日、筆者撮影)
(写真10)白川筋にて(2016年09月26日、筆者撮影) -
 (図1)安井金比羅宮の境内案内図(2025年01月15日、筆者作成)
(図1)安井金比羅宮の境内案内図(2025年01月15日、筆者作成)
(図2)時代風俗行列の行列順路(2025年01月15日、筆者作成)
参考文献
安井金比羅宮公式ウェブサイト
http://www.yasui-konpiragu.or.jp/ (最終アクセス日 2025年01月25日)
京都観光オフィシャルウェブサイト、京都観光Navi 「イベント情報 第64回 櫛まつり【安井金比羅宮】」
https://ja.kyoto.travel/event/single.php?event_id=4992 (最終アクセス日 2025年01月25日)
平安神宮公式ウェブサイト 「京都三大祭 時代祭について」
https://www.heianjingu.or.jp/festival/jidaisai.html (最終アクセス日 2025年01月25日)
京都観光オフィシャルウェブサイト、京都観光Navi 「時代祭 有料観覧席のご案内」〈註1〉
https://ja.kyoto.travel/event/major/jidai/seat.php (最終アクセス日 2025年01月25日)
取材先
有限会社美容室キミ (取材日2016年09月26日)
安井金比羅宮(取材日2016年09月26日、2024年09月23日)