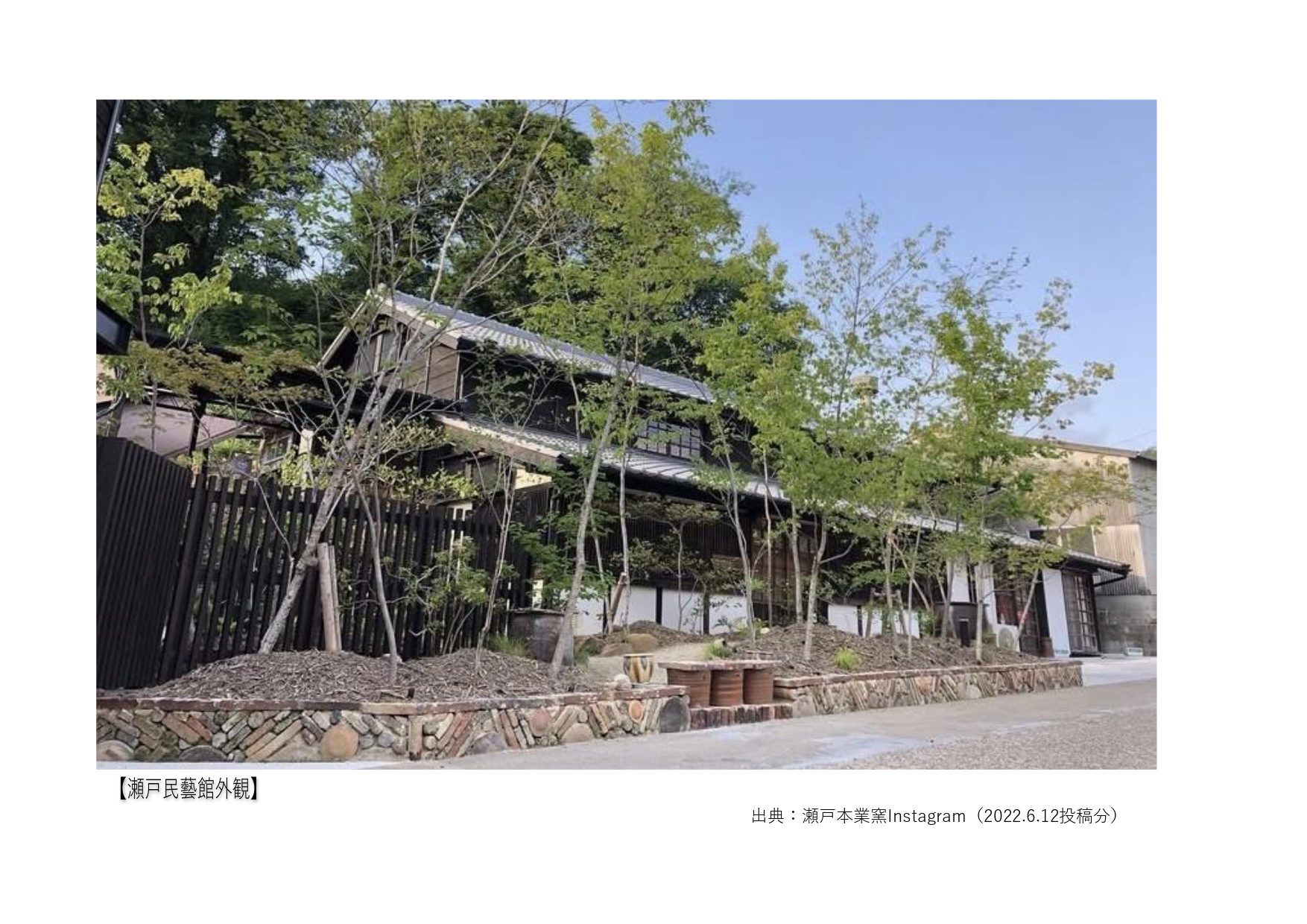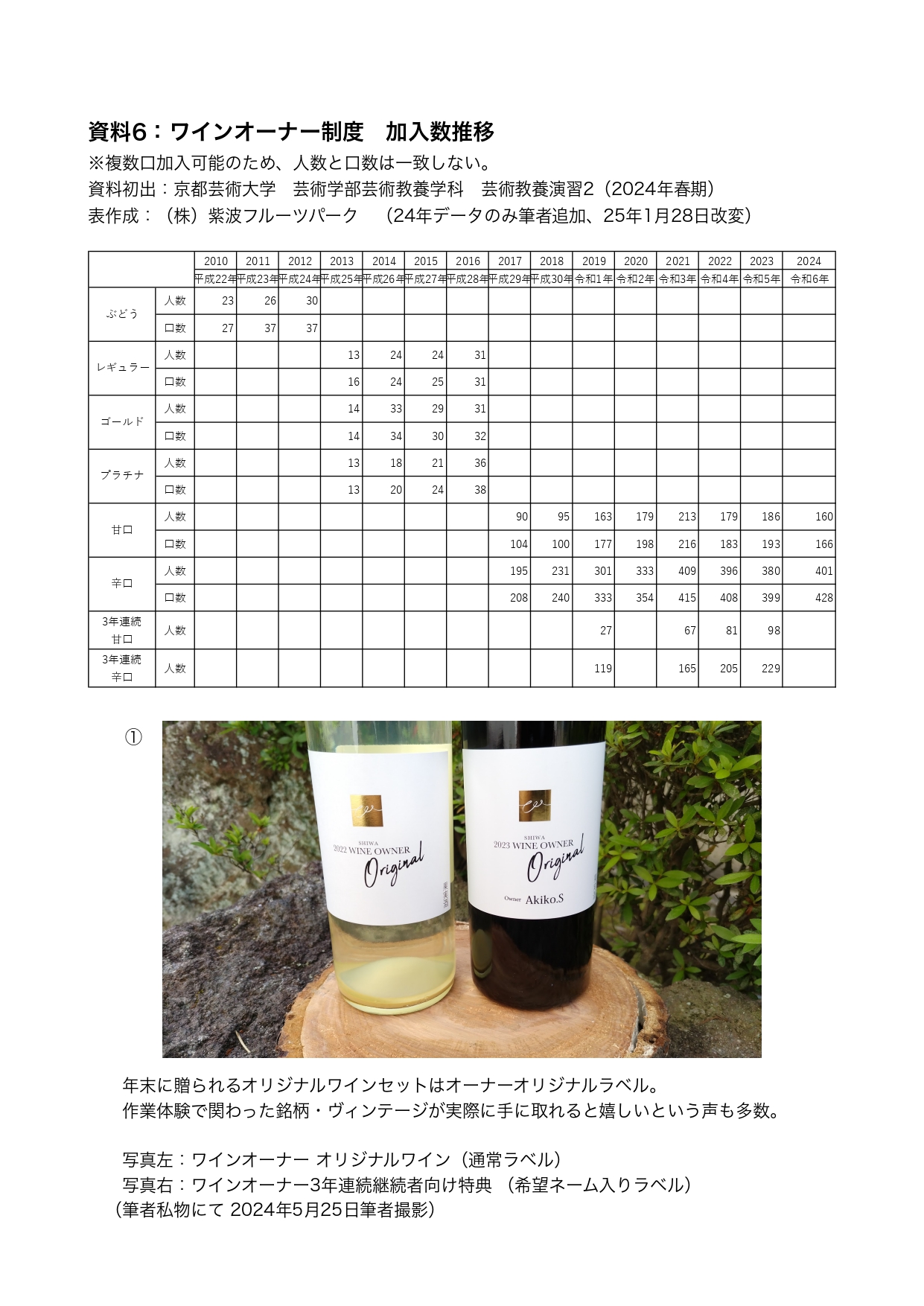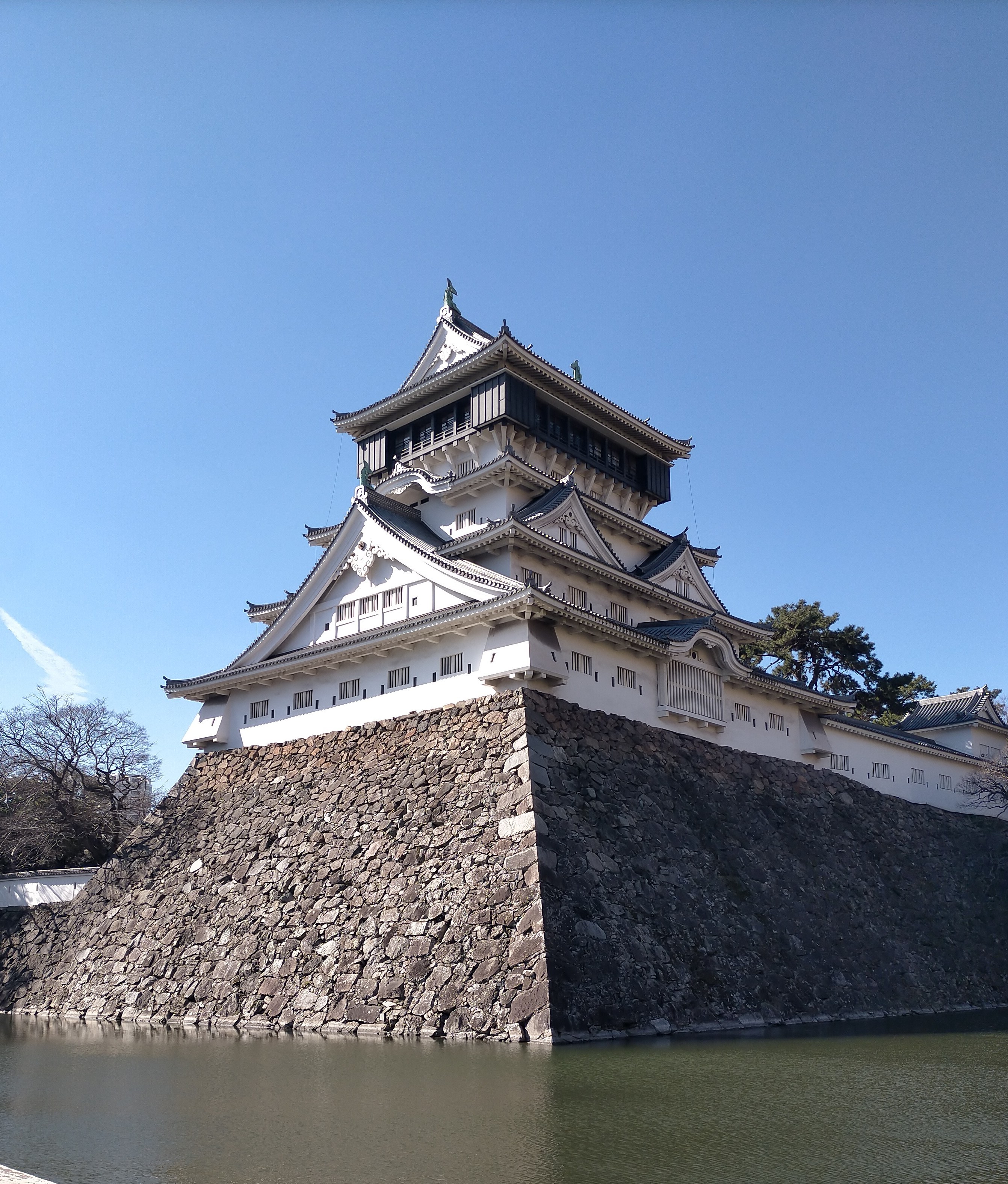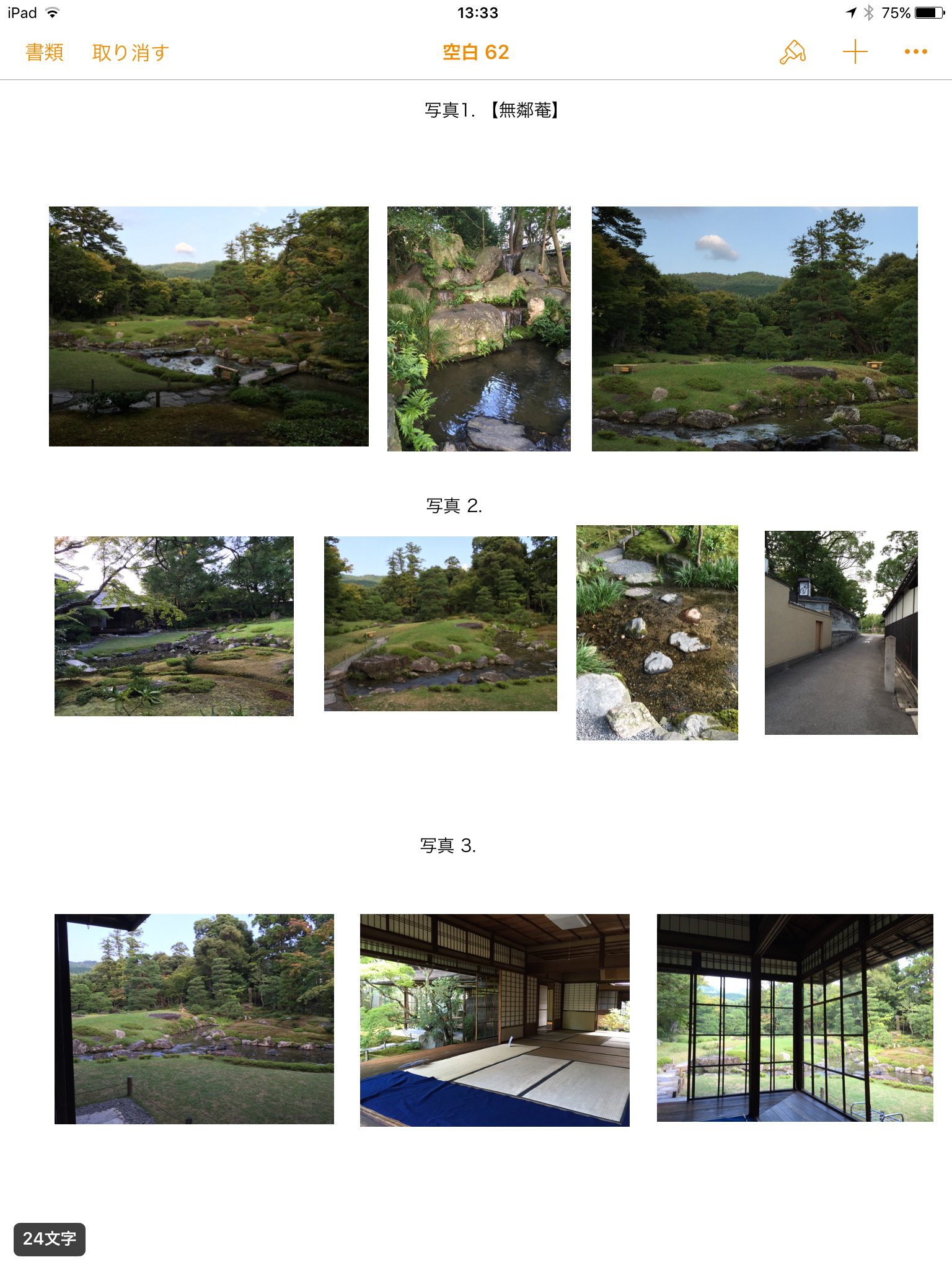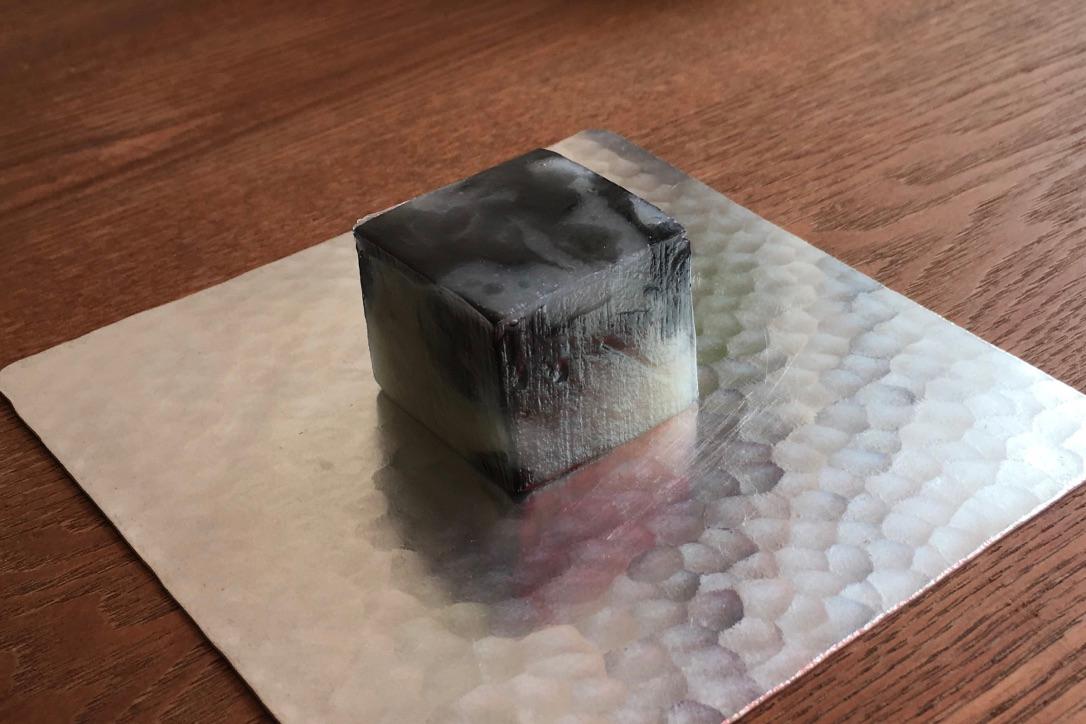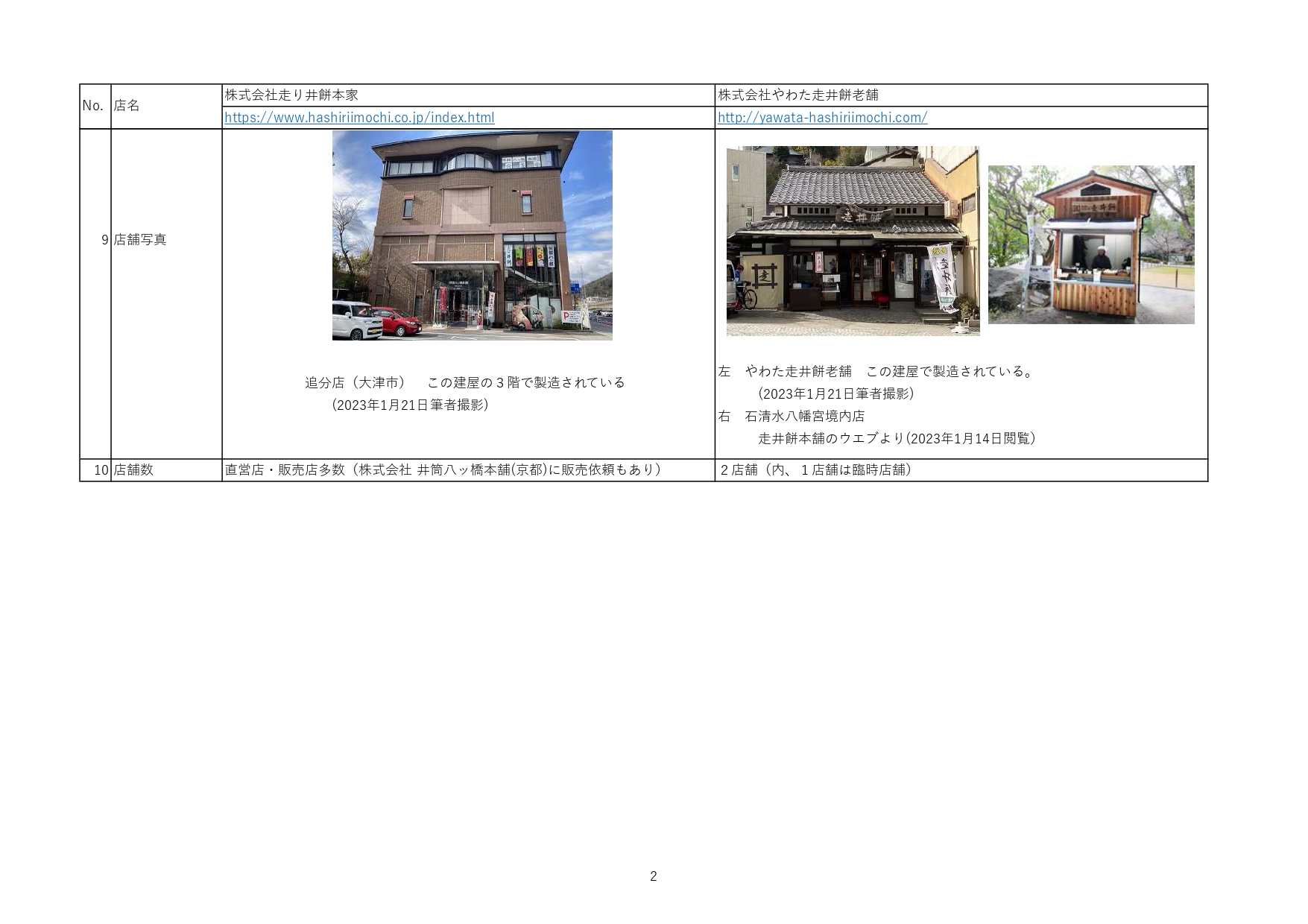京都芸術大学で学びを進める仕組みとその可能性 学びを支えるデザインの考察
筆者は京都芸術大学の学びを支えるシステムに対し、入学当初から「使いにくさ」を感じていた。この感覚は、特に「大学の初学者」にとって顕著であり、学内SNSを通じて他の新入生から「どうしたらいいかわからない。」「何から学習したらいいかわからない。」など多くの共通した声が寄せられていた。こうした経験から、自分が入学前に出会っていたらどれほど役立っただろう。と感じる本、さらに在学中にも傍に置いてレポート作成のたびに活用できる本を執筆しようと決意した。そして、その思いを形にしたのが『通信制で大卒を取る――京都芸術大学の学び方完全ガイド』(以下本書と呼称する)である。本書はAmazon Kindleにて2024年12月21日に電子書籍版を、翌日の2024年12月22日にペーパーバック版を出版した。
京都芸術大学が提供する学びのための仕組みは、シラバスや年間スケジュール、学内SNS、さらに「コンシェルジュ」と呼ばれる担当スタッフへのメール問い合わせや、学内SNSで学生の悩みを聞き、アドバイスするための「卒業生コーチ」など、網羅的で充実している。しかし、その情報量が多すぎるということと窓口が分散化しており、どこに答えを求めるべきかがわかりにくいのが現状である。特に初めて大学に通う「大学の初学者」にとってはハードルが高く感じる場面が少なくない。このような現状を補完するための書籍として本書を執筆をした。本研究では、京都芸術大学の提供する仕組みと本書を随所で比較しながら、両者の補完的役割について考察する。
書籍の基本データ
タイトル: 『通信制で大卒を取る――京都芸術大学の学び方完全ガイド』註1
著者: 石井つかさ(種岡 司)
出版日:
電子書籍版(2024年12月21日)
ペーパーバック版(2024年12月22日)
出版形式: Amazon Kindle
内容: 通信制大学での学び方を具体的かつ実践的に解説したガイドブック。
総文字数:約11,065文字(スペース含む)
ペーパーバック版:40ページ
価格:
ペーパーバック版 税込773円
電子書籍版 税込99円
対象読者:京都芸術大学の芸術教養学科で学ぼうと思う人、現在学んでいる人。
京都芸術大学の学習システム基本データ
『学習プラットフォームAirU(通称 青のAirU)』註2
シラバスや教材の確認、レポートの提出、進捗管理を一元的に行えるシステム。年間スケジュールを提供し、学習計画を立てやすい。
『コンシェルジュ』註3
学校の仕組みや単位に関することなど、様々な内容のメール問い合わせに対応。学習方法やシステム操作に関する質問に答える専用スタッフが常駐。
『学習ガイド』註4
学習の進め方などが網羅的に掲載されている。微に入り細に入りという状態で非常に充実した内容である。
『学内SNS AirU(通称 緑)』註5
学生間の交流を促進するためのSNSプラットフォーム。
レポート作成や学習進捗の共有など。また、卒業生コーチがコメントをくれる仕組みになっており、大学生活の助けとなり、通信学習で学びの孤独化」を避けることができる仕組みになっている。
本書の序章で「入学ガイダンスに参加しよう」とする旨を記載している。註6 わざわざ章を使って説明している理由としては、筆者が京都芸術大学の入学許可メールをいただいた時に、ぜひ書いていて欲しかった一文であるからだからだ。筆者は高校を卒業し、長く社会人を経験したのちになった大学生で、社会人経験のあいだに大学生で必要な用語に触れる機会がなく、まったくわからない状態で入学をした。その際、1番最初に送られてきたメールを全文転記する。
(非掲載)
このメールだけで学習をスタートさせるのは、少々ハードルが高すぎるのではないだろうか。また青のAirUにログインしても丁寧な説明は存在しない。参考3(青のスクショ) 「大学生は自ら情報を取得し学ぶもの」という前提があるにしても、青のAirUの初回ログイン時に、そういった旨の記載があってもいいのではないかと感じた。このような経緯があり、筆者は1年目に気が折れてしまい、結局1単位も取得することができずに過ごしたという経緯がある。
本書では、1章のさらに手前にあたる序章にて「入学ガイダンスに参加しよう」という内容を取り上げている。入学ガイダンスは、大学生活の基本を理解する上で重要であり、「シラバス」のような一般的な大学で使われる用語や「TR」「WS」といった京都芸術大学独自の用語を一定のレベルで把握する機会となる。しかし、ガイダンスは必須ではなく、特に社会人学生にとっては「無駄な時間」と受け取られがちである。こうした状況を踏まえ、本書ではガイダンスの重要性を序章で強調し、初学者が「最初に何をすればよいかわからない」という課題を解消する手助けを目指している。
また、ガイダンスに参加したとしても、履修プランの立て方でつまずく場合がある。京都芸術大学の履修システムは合理的で、青のAirUで提示される推奨モデルを活用すれば比較的スムーズに進められる。本書では、筆者自身が選んだ科目の基準を参考として紹介しているが、履修計画は個人の目的によって異なるため、最終的には学生自身の判断が求められる。
さらに、レポートの書き方も初学者には大きな壁となる。大学が提供する学習ガイドは充実しているものの、その網羅性が逆に初心者には「どこを参考にすべきかわからない」という状況を生む。本書では、初学者が直面する課題を解決するため、筆者独自の「型」を提案している。この型を用いることで、「何を書けばよいかわからない」という最初のハードルを乗り越える助けとなるだろう。
筆者の京都芸術大学における学びは非常に意義があるもので、今後の人生にも大きく関わってくるであろう。その意義を最大限にするためには、やはり大学を卒業するというのは大きなポイントであると考える。そのためには、「大学に入学した。」という事実だけでは足りず、卒業を目指すということが重要になる。そのためには入り口でふるいに掛けて振り落としていくのではなく、まずは全員を「卒業に導く」ための仕組みやロードマップをしっかりと用意していくということが必要なことではないだろうか。京都芸術大学の学びの仕組みのアップデートにより、本書が役割を失うことを願い、本稿を終える。
参考文献
註1 本書の発売されているAmazonのページ
註2
学習プラットフォームAirU(通称 青のAirU)
https://air-u.kyoto-art.ac.jp/
註3
コンシェルジュ
https://air-u.kyoto-art.ac.jp/airU/schooling/concierge/regist/
註4
学習ガイド
https://guide.air-u.kyoto-art.ac.jp/
註5
学内SNS AirU(通称 緑)
https://air-u.community.kyoto-art.ac.jp/
註6
通信制で大卒を取る――京都芸術大学の学び方完全ガイド電子書籍版 位置3%