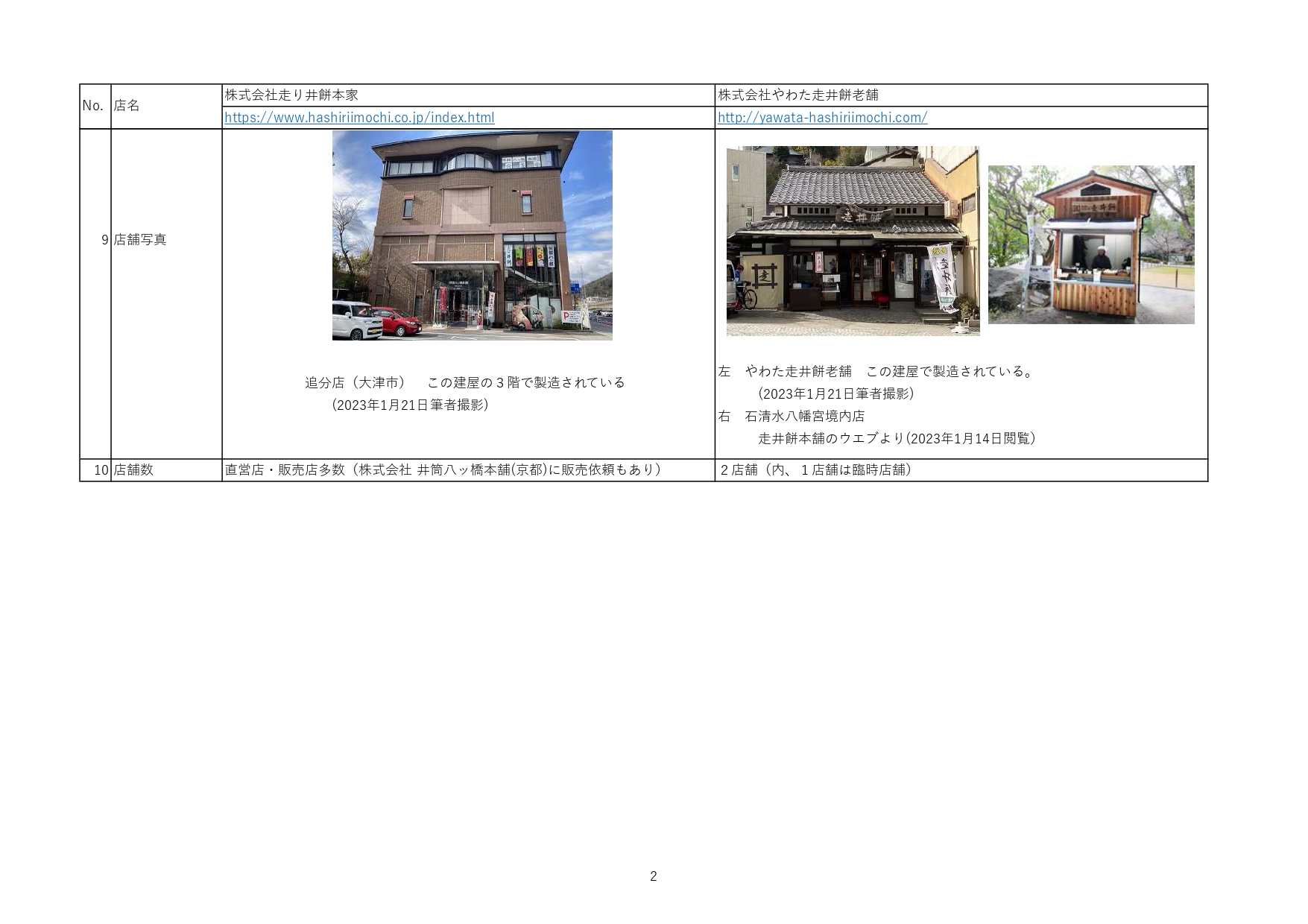古都京都の玄関口「京都駅ビル」がもつ高いデザイン性
はじめに
京都駅ビルとは、国際文化観光都市京都の玄関口として、駅・ホテル・商業施設・文化施設・駐車場・広場を備えたターミナルビルである(1)。京都の伝統的な文化と現代の要素が融合した空間であり、観光客や地元の人々が集まり交流する場として活気に満ちている。本稿では、「京の玄関口」として随所に工夫が施された京都駅ビルの魅力的な空間構成と、今後の展望について考察する。
1.基本データと歴史的背景
京都駅は、初代駅舎が生まれた1877年以来140余年、街とともに発展を続けてきた。現在の京都駅ビルは京都駅舎としては四代目となり、国際的な設計コンペを経て原広司の設計により高さ約60m、長さ約470mの規模で建設された(2)。東側に建つホテルグランヴィア京都、西側に建つJR京都伊勢丹の間の中央コンコースは、4000枚のガラスを使用した大屋根で覆われた巨大なアトリウムとなっており、直線や曲線が入り混じった現代的なアート空間となっている(写真1)。また、吹き抜けの最上部には地上45mの空中径路が通っており、吹き抜けから東西へは渓谷状の階段が設けられている。この長大な建築は、京都の街筋に従って大きく分割されており、ホテル・駅・デパート・大階段が配置されている。特に、大階段は普段は無用なデパートの非常階段を取り込んで巨大な野外劇場として有効活用する画期的な施設である(3)(写真2)。
2.事例のどんな点について積極的に評価しているのか
京都駅ビルは「京都は歴史への門である」という設計主旨から、平安京の都市の特徴である条坊制(碁盤の目)を取り入れ、玄関口としての象徴である「門」を烏丸通と室町通に配している(1)(資料1)。京都駅ビルという大きな壁の建設によって、京都の街は南北に分断されてしまうという意見が生じることも無理はない。そのため、京都駅ビルには京都の重要な通りごとに大きな開放部を設け、京都駅ビルがあっても京都の道は繋がっていることを主張した(4)。さらに、ロータリーに面する部分はガラス張りになっており、「壁」であることを感じさせないデザインとなっている(写真3)。京都駅ビルの内部は、中央コンコースを谷に見立てた段丘を東西に延ばし、京都盆地を現している(5)(資料2)。大胆な内部空間を展開するユニークな空間構成が特徴的であり、21世紀に向かう新しい空間のデザインを提案している点が評価される。京都駅ビルは、京都の和の印象を覆すような近代的で重厚感のあるデザインが特徴でもある。一見、古都とは異なるスタイリッシュな印象を与える建築であるが、そこには京都の景観を配慮した数々の工夫が施されていることがわかる。
3.国内外の他の同様の事例と比較して何が特筆されるのか
京都駅ビルの内部に着目すると、商業施設・文化的施設・土産物店はそれぞれ、西側・東側・上層階・地下というドーナツ状に配されていることがわかる。そして、それら全てにガラス張りのアトリウム空間が接続している。これによって、京都駅の施設を利用しない人々はそのドーナツの真ん中の空洞の部分を通るだけでよく、これは利便性の向上へと繋がっている(6)。普通の商業建築では、駅の通路にデパートの出入口が直結しているという場合が多い。客の取り込みもまた重要な要素であるが、京都駅は一見するとそれを満たしていない。商業施設や文化的施設を端へ追いやることにより、観光客の利便性が高まる一方で、買物客の利便性が損なわれてしまうからだ。そこで、一旦端に追いやった施設を、人工地盤に沿ってせり出させることで解決した(6)(写真4)。商業建築においては、利益を上げるために延床面積を増やす必要がある。しかし、観光地の玄関という性質上、延床面積を最大限まで高めた直方体のような建築は望まれていない。コンコースを開放的な空間とし、観光客をエスカレーターの上へ、大階段の上へと誘導することで、人が一定の場所に留まらないような工夫が施された。これは、観光客と普段の利用客、双方が共存するために考えられた京都駅ビルならではの仕組みであるといえる(資料3)。
こうして京都駅には、「ガラス張りの天井で覆われた巨大なアトリウム「それらを囲む人工地盤」「階段状に配置された施設で構成された谷の建築」が生まれた。京都駅ビルは国際文化観光都市である京都の玄関口にふさわしく、外観は周辺の景観に溶け込むようなデザインになるよう配慮がなされており、観光地であることを考慮した内部構造となっている。景観を重視しながらも限られた土地の中で施設を詰め込む工夫がなされていることが京都駅ビルにみられる特筆すべき点であると考える。
4.今後の展望について
開業間もないころの京都駅は、市中心部へ向かうための乗り換え場所にすぎなかったが、1964年に東海道新幹線が開業し京都タワーが完成すると、駅前の商業集積が進む。1997年、駅ビルに百貨店のジェイアール京都伊勢丹がオープンし、2010年代に入って訪日客が殺到すると、その傾向に拍車がかかった。京都市中心部は満杯状態で開発の余地が乏しいうえ、景観保護の高さ制限でタワーマンションなどを建設できず、マンション価格が高騰している。しかも、訪日客の急増で公共交通はパンク状態。このため、子育て層が大阪府や滋賀県に流出している(7)。
京都駅ビルのデザインには今でも賛否両論が多くあり、否定的な意見として一番多いと言われているものが、「京都の歴史的な町にデザインが合っていない」というものだ(4)。京都駅ビルが近代的すぎると思えてしまう理由として、京都駅周辺の再開発が進んでいないことが挙げられる。京都駅の周辺にある建物は比較的古いものが多く、京都駅ビルの近代建築が想像以上に目立ってしまっている。JR西日本と京都市は2023年12月、京都駅の南北自由通路の西側に、新橋上駅舎及び自由通路を一体的に整備し、観光客の急増にともなう駅構内や南北自由通路での混雑の緩和を図ることを発表した(8)(資料4)。また、駅の北側では、日本郵便とJR西日本グループの京都駅ビル開発が京都中央郵便局や隣接する立体駐車場を地下4階、地上14階建て延べ約13万平方メートルの複合施設に建て替える(7)。さらに、京都タワーも建て替えが検討されており、観光施設としての魅力向上を図る考えだ。
5.まとめ
京都駅ビルには至る所に広場や遊歩道が点在している。数々の広場や大階段など、どのテナントも入っていない自由なスペースがここまで開かれた駅は他に例が無く、訪れた人に多くのスペースを提供している(5)。他の都市の大規模な駅ビルは、かなりの面積を企業の賃貸オフィスに割いていることが多いが、京都駅ビルは賃貸オフィス部分がほとんどない、全国でもめずらしい駅ビルとなっている(9)。駅・ホテル・商業施設・文化施設・駐車場・広場を備えた京都駅ビルは、人工地盤の活用により駅ビル内にそれら商業施設やホテルを組み込む空間構造によって、一見すると全てが「京都駅」と思わせる一体感のある外観となっている。観光客と地元駅利用者の双方のことを考えた構造、また景観を重視したデザイン空間が京都駅ビルの大きな魅力であるといえる。
京都という街は、古都にして現代の大都市であり、新たな価値を生み出す攻撃的で前衛的な面をもっている。京都駅ビルは、「創造と革新」をおこなう京都という街を巨大な質量によって象徴している。現時点において、京都市立芸術大学の移転など京都駅周辺は大きく変わろうとしている。さらに、駅舎の大規模改修と中央郵便局の建て替えに伴う高層複合ビルの新設など、今後予定されている京都駅周辺の再開発により京都駅周辺は近代化が進むことが予想される。今後の京都駅周辺の再開発によって、「近代的すぎる」という批判的な意見が一部でみられる京都駅ビルの外観はより周囲に調和するものとなり、都市ブランドとしての京都の価値は高められていくことが期待される。
-
 (写真1)アトリウム空間(2025年1月18日、筆者撮影)
(写真1)アトリウム空間(2025年1月18日、筆者撮影) -
 (写真2)京都駅ビルの巨大な野外劇場(2025年1月18日、筆者撮影)
(写真2)京都駅ビルの巨大な野外劇場(2025年1月18日、筆者撮影) -
 (写真3)ガラス張りの外観(2025年1月18日、筆者撮影)
(写真3)ガラス張りの外観(2025年1月18日、筆者撮影) -
 (写真4)京都駅ビル内部にみられる人工地盤(2025年1月18日、筆者撮影)
(写真4)京都駅ビル内部にみられる人工地盤(2025年1月18日、筆者撮影) -
 (資料1)京都の通りに配された開放部(2025年1月18日、筆者撮影)
(資料1)京都の通りに配された開放部(2025年1月18日、筆者撮影) -
 (資料2)京都盆地が表された駅ビル内部(京都駅ビル開発株式会社「広場のご案内」、
(資料2)京都盆地が表された駅ビル内部(京都駅ビル開発株式会社「広場のご案内」、
https://www.kyoto-station-building.co.jp/guidemap/about.pdf、2025 年1 月20 日閲覧) -
 (資料3)人工地盤と大階段の間に配された商業施設(京都駅ビル開発株式会社「施設のご案内」、https://www.kyoto-station-building.co.jp/guidemap/facility-01.pdf、2025 年1 月23 日閲覧
(資料3)人工地盤と大階段の間に配された商業施設(京都駅ビル開発株式会社「施設のご案内」、https://www.kyoto-station-building.co.jp/guidemap/facility-01.pdf、2025 年1 月23 日閲覧 -
 (資料4)改良計画概要(西日本旅客鉄道株式会社・京都市「京都駅新橋上駅舎・自由通路の整備について」、https://w w w .w e s tjr.co.jp/pre ss/a rticle /items/2 3 1 2 2 7 _ 0 0 _ kyotoshi.pdf、2 0 2 5 年1 月2 0 日閲覧)
(資料4)改良計画概要(西日本旅客鉄道株式会社・京都市「京都駅新橋上駅舎・自由通路の整備について」、https://w w w .w e s tjr.co.jp/pre ss/a rticle /items/2 3 1 2 2 7 _ 0 0 _ kyotoshi.pdf、2 0 2 5 年1 月2 0 日閲覧)
参考文献
<註>
(1)京都駅ビル開発株式会社『京都駅ビルについて』
https://www.kyoto-station-building.co.jp/about/(2024年12月18日閲覧)
(2)カーサ・プロジェクト株式会社『建築家・原広司が国際コンペで勝ち取り実現した「京都駅」は、谷のような大階段のアトリウムが魅力的!』
https://hash-casa.com/2024/10/21/kyotostation/(2024年12月18日閲覧)
(3)小川格『なぜ「京都駅」の建築は賛否両論を巻き起こした? デザインの原点は世界各地の集落調査』
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/02220610/?all=1#goog_rewarded(2024年12月18日閲覧)
(4)Yusei『京都駅ビルの魅力 Vol.1[撮影スポットにもオススメな京都駅ビル!]』
https://crossmono.com/kyotostation-vol-1/(2024年12月18日閲覧)
(5)たてものフロンティア『「京都駅ビル」は大階段をはじめ、最も身近で壮大な京都の観光スポット』
https://tatefro.com/entry-5.html(2024年12月18日閲覧)
(6)ジオログ『京都駅大解剖〈前編〉「壁」京都駅に潜む谷の建築とは?』
https://kyohju.com/article/461962365.html(2024年12月8日閲覧)
(7)高田泰『京都駅周辺「再開発ラッシュ」 過去のいわれなき差別乗り越え、古都の“玄関口”は街の中心に生まれ変われるか』
https://merkmal-biz.jp/post/56591/3(2024年12月8日閲覧)
(8)読売新聞オンライン『京都駅に新改札と新通路…2031年度に供用開始、建設予定の高層ビル直結も検討』
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231227-OYT1T50197/(2024年12月18日閲覧)
(9)株式会社RecoD『世界中からの観光客を近代的なデザインで出迎える「京都駅ビル」』
https://www.recod.jp/building/nightview-kyoto/(2024年12月18日閲覧)
<参考文献>
・ジオログ『京都駅大解剖〈中編①〉 京都駅アトリウムのデザイン』
https://kyohju.com/article/461987467.html(2024年12月18日閲覧)
・ジオログ『京都駅大解剖〈中編②〉 原広司は「正方形」でコンペに選ばれた?』
https://kyohju.com/article/462007820.html(2024年12月18日閲覧)
・ジオログ『京都駅大解剖〈後編①〉~京都駅ビルの芸術的立ち位置~』
https://kyohju.com/article/462021904.html(2024年12月18日閲覧)
・ジオログ『京都駅大解剖〈後編②〉~日本らしい建築とは~』
https://kyohju.com/article/462029459.html(2024年12月18日閲覧)
・有限会社 金箱構造設計事務所『京都駅ビル』
https://www.kanebako-se.co.jp/works/view/240(2024年12月18日閲覧)
・日本経済新聞電子版『JR京都駅、混雑緩和へ改修 西口広場を増床し改札新設』
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF2742U0X21C23A2000000/?msockid=191b47a7d1a96b7f16a453fad0436ace(2024年12月18日閲覧)
・関西旅行ナビ『京都駅-広い構内には見どころがいっぱい!京都観光にふさわしい新名所【京都】』
https://www.kan-navi.jp/blog/kyoto-station/(2024年12月18日閲覧)
・株式会社アドベンチャー『デザイン空間が魅力の京都駅ビルで観光・文化・ショッピング・グルメを満喫』
https://skyticket.jp/guide/345089/(2024年12月18日閲覧)