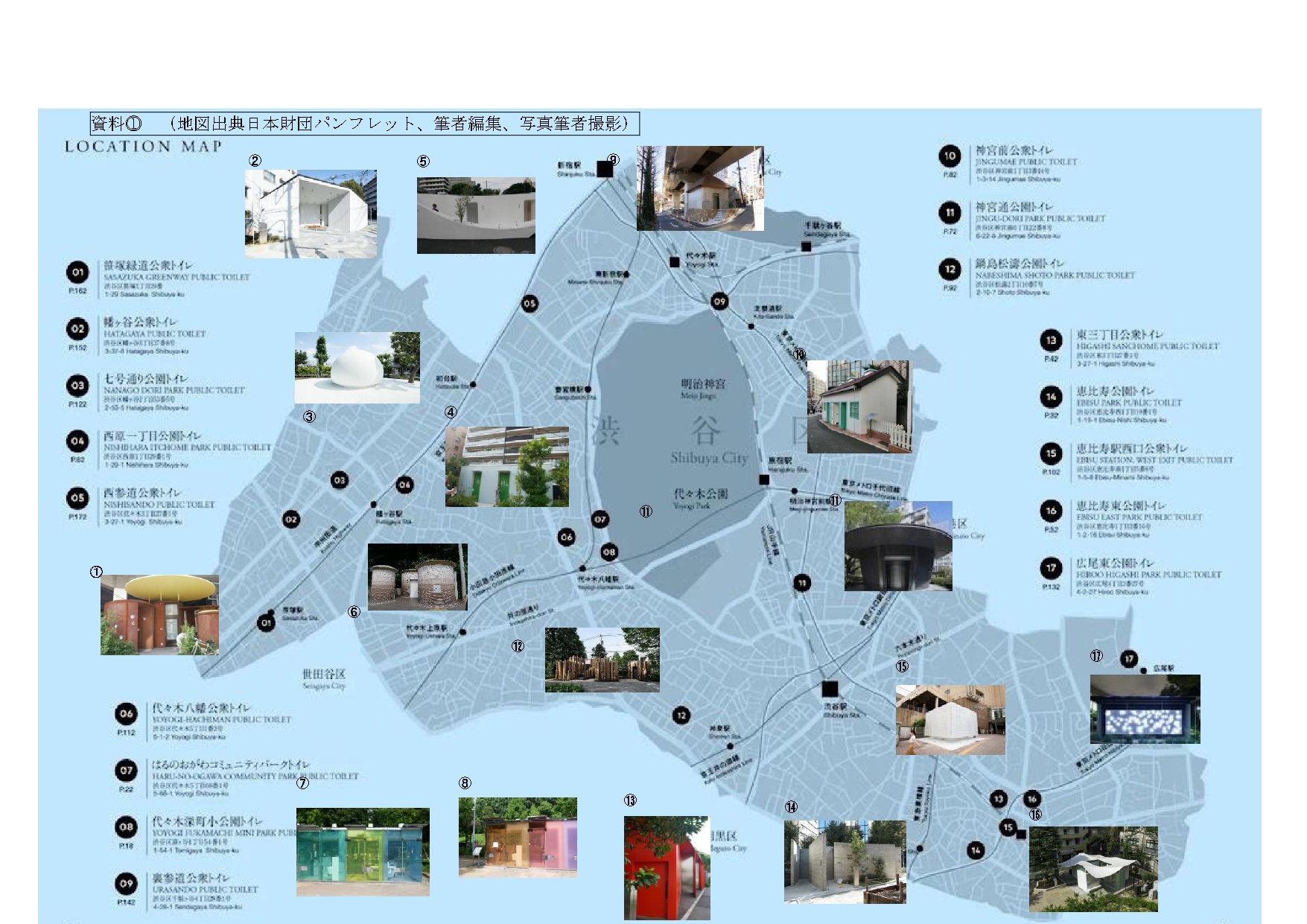川越まつり 〜次世代への継承〜
1.はじめに
埼玉県川越市で、毎年10月第3日曜日とその前日に行われる「川越まつり」。国内外から多くの観光客が訪れる山車行事の祭りである。その祭りであるが、戦時中、高度経済成長期など、時代の変遷とともに開催がいく度か途絶えたことがあるという。都度、力強く復活を遂げてきた祭りはどのように復活し、今後どのように次世代へ継承してゆくのか。その価値を考察する。
2.基本データと歴史的背景
2―1.基本データ
名称:川越まつり
開催場所:埼玉県川越市
開催日時: 毎年10月第3日曜日とその前日
川越まつり〔写真1〕は、近年「小江戸川越」と呼ばれる埼玉県川越市の中心部、黒漆喰〔註1〕の蔵造りが建ち並び江戸情緒の残る街並み〔写真2〕を中心として開催される都市型の祭礼である。
山車〔註2〕は全部で29台〔写真3〕あり、通常は全ての山車が参加することはなく、その年により増減がある。10年に一度、川越市制記念にあたる年(前回は2022年度)には、29台全ての山車が揃い参加する。2024年度は19台が参加した。2005年に国指定重要無形民俗文化財〔註3〕、2016年にはユネスコ無形文化遺産〔註4〕に指定され、関東三大祭り〔註5〕のひとつともいわれている。2024年度は約74万人の人出があった。都心から近くアクセスの良いことが、多くの集客につながっている。
「川越まつり会館」〔写真4〕では、29台の山車のうち交代制で常時2台の山車が展示されている。
2―2.歴史的背景
「川越まつり」は、慶安元年(1648)大名であった松平信綱〔註6〕が川越氷川神社〔註7〕〔写真5〕へ祭礼用具である神輿二基・獅子頭二頭・太鼓などを奉納し、氏子城の十ヵ町〔註8〕に祭りの執り行いを求めたことが起源であり、江戸の天下祭〔註9〕の影響を受けて発展し、川越氷川神社の秋の祭礼である山車行事として始まったものである。川越氷川神社の神輿が氏子の町々を渡御した記録が残されているという。
江戸時代の川越は、十七万石〔註10〕の城下町として栄えており、小江戸と呼ばれていた。江戸の隅田川と直結している新河岸川船運〔註11〕〔写真6〕により、川越の商人はさまざまな物資を江戸へ供給する一方、江戸の文化・風習を取り入れて発展してきた中で、江戸の天下祭から大きな影響を受けた。
3.評価点
川越まつりの評価点として、各町内ごとに人形〔註12〕を乗せた豪華な山車が蔵造りの町を練り歩くことにある。夜になると提灯を灯した山車が向かい合わせになり囃子を披露しあう「曳っかわせ」〔註13〕が行われる。夜が更けるとともに祭りはクライマックスを迎える。
山車は江戸川越型と呼ばれており、その構造は二重の鉾と伸縮できる迫り上げ可能なエレベーター式となっている。二重構造の理由として、山車を川越城中へ曳き入れる際、大手門を無事にくぐりぬける必要があったため、そのような伸縮構造の山車となっている。(現在では電線をくぐるためでもある。)
祭りのもう一つの見どころである、囃子であるが、川越の祭り囃子〔註14〕は、中山道沿いより入った堤崎流、甲州街道沿いより入った王蔵流、芝金杉流の三つの流派があり、同じ流派であっても伝承された時期や流れによりわずかな違いがみられる。
川越の囃子の特徴として、他の地域の囃子と比較し、現代風にアレンジされることなく昔の特徴をとどめていることにある。そのテンポはゆっくりと落ち着きのあるものといわれており、口伝伝承される曲は多く、すべての曲には舞がついている。
4.秩父夜祭との比較
埼玉県秩父市で毎年12月2日(宵宮)、3日(大祭)に開催されている秩父夜祭は、京都祇園祭、飛騨高山祭にならぶ日本三大曳山祭の一つである。江戸時代から続く歴史ある例大祭であり、冬に開催されるめずらしい祭りでもある。
「秩父祭の屋台行事と神楽」は国重要無形民俗文化財、「山・鉾・屋台行事」はユネスコ無形文化遺産に登録されており、豪華な笠鉾・屋台に曳きまわし、秩父屋台囃子、花火、屋台芝居〔註15〕、曳き踊りなどが見どころとなっている祭りである。
祭りの起源は江戸時代半ば、秩父神社周辺で行われていた絹織物の市である「絹大市」(きぬのたかまち)の経済的発展とともに大々的に行われるようになった。幕府によって華やかな屋台行事の禁止令が出された時代、戦争などによる変化を超え現代に継承されている。秩父夜祭の特徴として、澄んだ冬空にあがる花火、笠鉾・屋台の華やかな色彩が見どころとなっている。
川越まつりとの共通点として、ともに埼玉県で江戸時代から続く歴史があり、国重要無形民俗文化財、ユネスコ無形文化遺産に登録された祭りであること、時代とともにいく度か祭りは途絶えたが、ともに復活を遂げたことにある。
相違点として、見どころの違いがあげられる。ともに夜が更けるにしたがい熱気を帯びてくる祭りではあるが、川越まつりの山車と山車が向かい合った時に行われる曳っかわせによる競演は、独自の魅力があり特筆すべき点である。
5.川越まつりの復活の経緯と今後の展望
川越まつりは江戸時代をその起源とし、現在まで途絶えることなく続いてきた祭りである思われることがある。しかし、時代の変遷とともに途絶えていたことがいく度かあった。
5-1.戦後の祭り復活
昭和21年(1945)戦後初めての川越まつりの開催は、当時志義町(現・仲町)30代の若者から大人衆への説得からはじまった。しかし、他の町からの同意はなかなか得ることができず、志義町のみで行うという寸前に、高沢町(現・元町2丁目)も参加し、たった2台の山車のみで行われた。しかし、この祭りをきっかけとし、川越まつりは復活の道を辿ることができた。
5-2.高度経済成長期時代の復活
昭和の高度経済成長期時代には、伝統的である祭りは時間や手間がかかることなどから敬遠され行われていなかった。しかし、再び祭りをしたいと強く望む者たちが出てきたことが復活を可能にした。祭りの途絶えた時期、地元の30代、40代の若手の間から、「本当のまつりがしたい」という声が上がるようになった。また、昔の祭りを知る初老たちからも復活を願う者がいた。その両者が出会えたことにより、川越まつりは現在につながる復活を遂げることができた。
5-3.近年の祭りにおける問題点と今後の展望
一度、途絶えた祭りの復活は、地域の仲間意識を高め、さらに絆を深めることになった。川越まつりは地元の者たちはもちろんのこと、地域活性として、県や市など行政の後押しも強く行われている。川越まつりを宣伝することでブランド化し、川越の知名度が上がることで、さらに観光客も増えて街は発展していく。
近年では、国内ばかりだけではなく、海外からの観光客も含め2日間で集客数70万人を超す人気のある祭りとなっている。しかし、近年の祭りはイベント色が濃くなり、本来の祭りである意味を知らない人々が増えたといわれる。古来の祭りを大切に継承することを誇りとしている者たちからは、近年の祭りは意味合いが変化し、本来の目的から外れ、祭りが乱れてきていると嘆いているという。
解決する方法のひとつとして、伝統の大切さと今後の祭りの在り方に対する考え方の相違について、世代を超え、時間をかけた地域のコミュニケーションが有効である。また、行政とのさらなる連結を深め、誇りある川越まつりを次世代へ継承してゆくことが望まれる。
6.まとめ
価値観は時代とともに変化していくものである。しかし、何かのきっかけで古き良きものへの気づきがある。「気づき」には、世代を超えた人と人のつながり、コミュニケーションが不可欠である。祭りの要ともなるお囃子の継承も、口伝での伝承であり、コミュニケーションの賜物である。一度、途絶えた祭りの復活は、地域に住むものたちの仲間意識を高め絆を深めることにつながった。そのことは地域の活性化にもつながっていく。県や市からの後押しも大きな支えとなっている。
地域を愛し、仲間との多彩なコミュニケーションをとることで伝統が受け継がれていく。それは、未来へ力強く川越まつりの継承へとつながっていく。
-
 【写真1】川越まつり 山車
【写真1】川越まつり 山車
(2018年10月21日 筆者撮影) -
 【写真2】川越市中心部、黒漆喰の建物が立ち並ぶ街並み
【写真2】川越市中心部、黒漆喰の建物が立ち並ぶ街並み
平成4年には約2年の時をかけ電線を地中化し、古き良き江戸時代を彷彿させる街並みとなり、平成11年には文化庁の重要伝統建造物郡保存地区として選定された。
(2024年11月11日 筆者撮影) -
 【写真3】29台の山車
【写真3】29台の山車
・幸町 翁の山車
・喜多町 秀郷の山車
・元町二丁目 山王の山車
・大手町 鈿女の山車
・幸町 小狐丸(小鍛冶)の山車
・仲町 羅陵王の山車
・松江町二丁目 浦嶋の山車
・志多町 弁慶の山車
・六軒町 三番叟の山車
・今成 鈿女の山車
・松江町一丁目 龍神の山車
・元町一丁目 牛若丸の山車
・宮下町 日本武尊の山車
・末広町 髙砂の山車
・連雀町 道灌の山車
・中原町 河越太郎重賴の山車
・三久保町 賴光の山車
・西小仙波町 素戔嗚尊の山車
・脇田町 家康の山車
・通町 鍾馗の山車
・新富町二丁目 鏡獅子の山車
・新富町一丁目 家光の山車
・野田五町 八幡太郎の山車
・仙波町 仙波二郎安家の山車
・岸町二丁目 木花咲耶姫の山車
・菅原町 菅原道眞の山車
・南通町 納曾利の山車
・旭町三丁目 信綱の山車
・川越市 猩猩の山車
川越まつり会館(2024年11月11日 筆者撮影) -
 【写真4】川越まつり会館
【写真4】川越まつり会館
埼玉県川越市川越市元町2丁目2-10
(2024年11月11日 筆者撮影) -
 【写真5】川越氷川神社
【写真5】川越氷川神社
(2018年2月21日 筆者撮影) -
 【写真6】新河岸舟運跡地 新河岸川
【写真6】新河岸舟運跡地 新河岸川
江戸の隅田川と直結しており舟運の文化で栄え、物資の運搬や人の往来にも利用されていた。
(2024年12月11日 筆者撮影) -
 川越まつり会館展示、囃子の様子
川越まつり会館展示、囃子の様子
(2024年11月11日 筆者撮影)
参考文献
【註釈】
〔註1〕白の漆喰に墨、松煙、油煙等を入れて黒く仕上げる工法。
〔註2〕だし。祭礼に使用される豪華に飾られた出し物。
〔註3〕民族文化財のうち年中行事等に関するものであり、国は特に重要なものを「重要有形民俗文化財」「重要無形民俗文化財」に指定し、その保存と継承を図っている。
〔註4〕条約において、口承による伝統及び表現、芸能、社会的慣習、伝統工芸技術といった無形文化遺産について、衰退や消滅などの危機を回避するため保護を目的として採択された。
〔註5〕「石岡のおまつり」「佐原の大祭」「川越まつり」の3つの祭り。
〔註6〕寛永15年(1638)の大火後に川越藩の藩主となった人物。
〔註7〕武蔵野台地にあり、川越台地の北端にある。社伝によると、氷川神社の創建は、欽明天皇即位(540)に大宮氷川神社より分祀された。
〔註8〕寛延18年(1641)に城主であった松平伊豆守信綱が行った城下の区画整理のことである。上五か所が本町(現在の元町一丁目)、高沢町(元町二丁目)、南町(幸町)、北町(喜多町)、江戸町(大手町)下五か所が、鍛冶町(幸町)、多賀町(幸町、大手町)、上松江町(松江町二丁目)、下町(志多町)、鴫町(仲町)
〔註9〕江戸城の鎮守であった赤坂・日枝神社の山王祭と、江戸の総鎮守であった神田明神の神田祭のこと。時代の変遷とともに、江戸の山車は明治22年(1889)を最後に東京の町から消えてしまう。
〔註10〕一万石の価値は、「石」という精白されていない玄米の単位で表現となっている。石は、約180リットルに相当する。
〔註11〕新河岸駅から近い旭橋のたもとにかつて舟運で栄えたことのある石碑がある。
現在のように陸上交通が発達していなかった。城主であった松平伊豆守信綱が新河岸川を改修して江戸との舟運を開き物資輸送を可能にした。
〔註12〕江戸の著名な人形師が作成したものであり、古いものは、天保年間、新しいものでは明治につくられたといわれている。
〔註13〕山車どうしが向かい合わせで交わされる、川越独自の儀礼作法。人形どうしを挨拶させ、互いが囃子と踊りで相手町を称える。
〔註14〕囃子とは、元来、非日常的な音や所作で囃すことによって、神を人間社会に迎い入れそして送り出す儀式的音曲であり、祭礼様式の変化に合わせて発展してきたものである。祭り囃子は口伝による伝承であり残された資料が少ない。
〔註15〕屋台の両側に張出舞台を付け、芸座を組み立てて上演する屋台歌舞伎。
【参考文献】
・『都市の祭り』中村莩美遺稿論文集 中村莩美遺稿論文集出版委員会 2013年
・木下雅博『川越まつりと山車・元町二丁目の場合』 川越市文化財保護協会 昭和60年
・『川越祭』川越祭りを学ぶ会 2005年8月1日
・小林三郎『武州川越の祭り』たなか屋出版部 1986年9月1日
・水戸一斎『川越まつりがすごいらしい』令和2年
・『川越祭』川越祭を学ぶ会 街と暮らし社 2005年
・埼玉県文化財保護協会『埼玉の文化財・第58号』平成30年
・谷澤勇『川越まつり現場からの報告』株式会社ぷらんず社 1990年
・『創立50周年記念誌』川越市囃子連合会 2023年
・川越市教育委員会『川越氷川祭りの山車行事』調査報告書・本文編 平成15年3月27日 株式会社櫻井印刷所
・広報かわごえ2024年10月号 No.1513
【参考ホームページ】
・川越まつり公式HP https://www.kawagoematsuri.jp/ 2024.10.14 11.27.参照
・川越氷川神社HP https://www.kawagoehikawa.jp/shoukai/ 2025.1.6参照
・川越一番街商店街HP https://kawagoe-ichibangai.com/story/ 2025年1月6日参照
・国土交通省・関東地方整備局HP https://www.ktr.mlit.go.jp/araike/pdf/sonota/100neta/100neta_077.pdf 2025年1月6日参照
・秩父神社HP https://www.chichibu-jinja.or.jp/yomatsuri/ 2024.10.14参照
・秩父まつり会館HP https://www.chichibu-matsuri.jp/ 2024.10.14参照
・秩父観光なびHP https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_festival/1030/ 2024.10.14参照
・文化庁HP https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index 2024.12.2参照
・石岡のお祭りの魅力HP https://ishiokamatsuri.com/sandai-matsuri-kigen/ 2024.12.2参照
・川越市HP https://www.city.kawagoe.saitama.jp/smph/welcome/history/history03.html 2024.12.3参照
・国土交通省HP https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/mukei_bunka_isan/ 2024.12.6参照
・国土交通省HP https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/gaiyo/ 2024.12.6参照
【取材協力】
・川越まつり会館、職員の方々