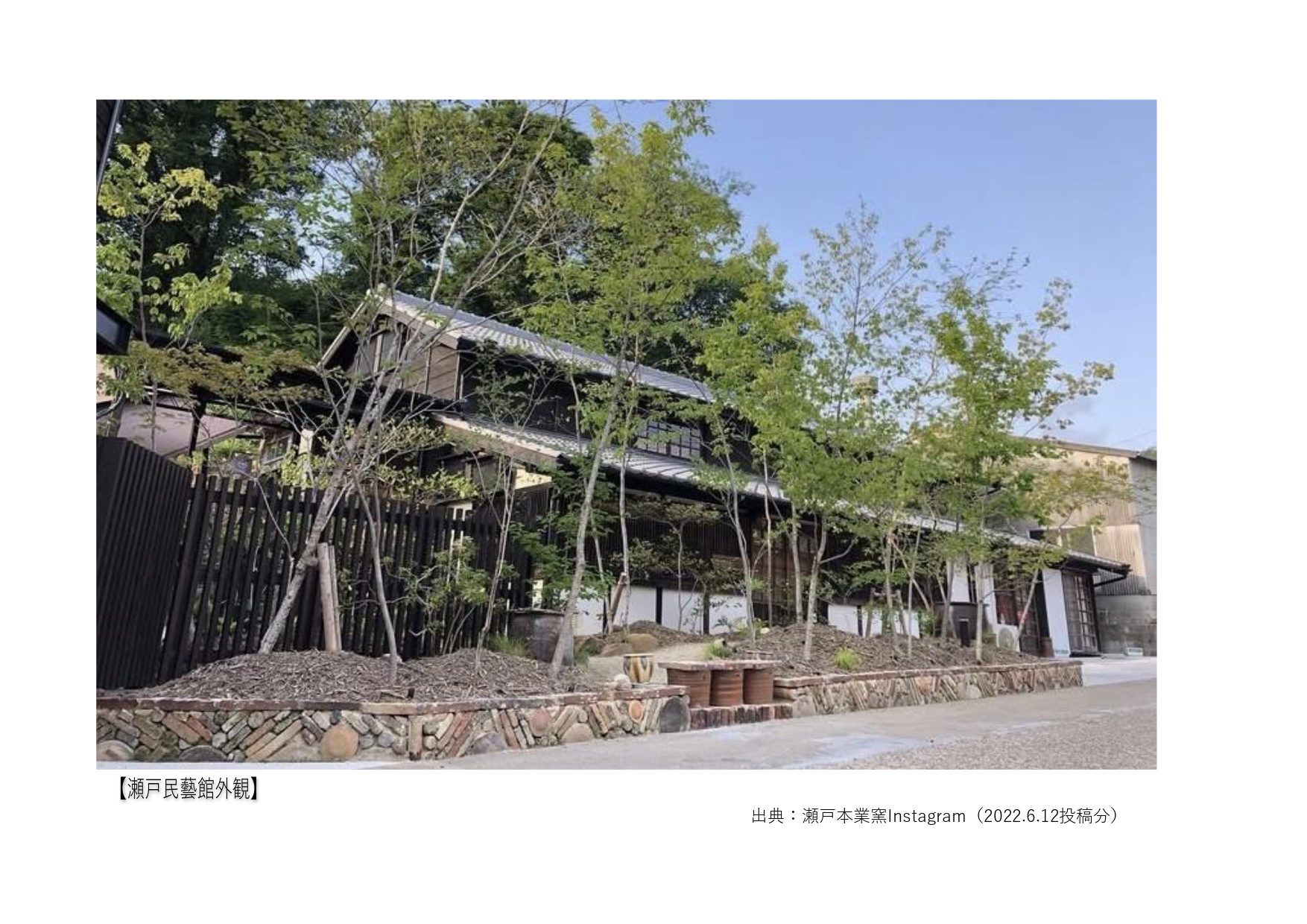横浜港から世界中に輸出された横浜スカーフ
1.基本データと歴史的背景
基本データ
横浜スカーフは横浜の伝統工芸品である。横浜開港により世界中に輸出されてきた。横浜の地場産業として栄え、最盛期の1976年には国内生産量90%のシェアを誇った。明治時代から、今日に至るまで国内、国外の社会情勢や景気、流行などに影響を受け、変遷をしてきた。小規模な産業ではあるが、職人の手による高い技術力や丁寧なしごと、豊富なデザインを強味とした伝統的な横濱スカーフが作られている。
歴史的背景
1859年の横浜開港後には生糸‧絹織物の輸出が盛んになり、羽二重を加工した手巾(ハンカチーフ)製造、「絹ハンカチ」が生まれ、それが「横浜スカーフ」に発展した。(1)
絹ハンカチ製造が地場産業として栄えた要因は、生糸が横浜に集積したこと、輸出絹物売込商,外国貿易商の存在、技術を持つ捺染用木版職人や縁かがりの内職従事者の存在、捺染染織用の水利があった事などである。(2)
絹ハンカチの製造、販売、輸出がいつ始まったかは諸説ある。(3) 1890年には羽二重に木版捺染したハンカチがフランスで人気を得て、その後1923年関東大震災で横浜が被災するまで輸出は継続した。
横浜でスカーフ製造、輸出が始まったのは昭和初期とされる(4) 捺染工場も多く建設され輸出も盛んになったが、戦時下は軍需工場となり、多くが1945年の横浜大空襲で焼失した。(5)
戦後の貿易再開後にスカーフの生産が本格化した。 国内では1950年の「糸へん景気」に加え、1953年に映画化された『君の名は』で「真知子巻き」が大流行し、ロングスカーフの売れ行き需要が伸び業界が活況となった。
国外向けでは、1960年代半ばまではアメリカやヨーロッパの下請けとして、各国の観光みやげ用スカーフなどを受注し輸出をしていた。(6) アフリカや中近東へも販路を広げ、1965年頃からは東側諸国への輸出も始まり、大量のスカーフが製造、輸出され、横浜スカーフは世界中に輸出されるに至った。(7)
1970年頃から欧米のデザイナーによるブランドスカーフやハンカチを製造するライセンスビジネスが始まり、スカーフブームを迎える。その後の不況やライセンス契約終了によりブームも沈静化し、国外ブランドの横浜スカーフは消え、ビジネスも低迷した。
廃業や業態を変更する会社も多く、現存する企業の殆どはスカーフの製造以外を主力業務としており、原則としてスカーフは受注生産の形式をとっている。(8) (資料2,3)
2.評価している点
横浜スカーフの歴史的価値を認め、その良さをいかした、現代の横浜スカーフの認知度を高める活動、研究などに多様なアプローチがみられる。主なステークホルダーはスカーフ業界団体と行政機関であり、大学や博物館が支援的な役割を担っている。(資料4)
継続されている主な取り組みとして、スカーフ業界団体が中心となり、毎年開催されるシルク関連イベントや「横浜みなと祭り」への参加など横浜スカーフの露出を高める活動がある。スカーフ大使制度やスカーフギャラリー展示など、「人」の巻き込みや「場」の創造も行われてもいる。
また、スカーフ捺染技術を応用した製品を開発販売する会社もあり、自社HPなどで由来や歴史を伝えており、消費者に伝統的な技術の価値を伝達している。加えて新しい用途に向いたデザイン、シルク素材の開発をする試みにチャレンジする会社もみられる。(9)
行政は地場産業を後援し地域活性をはかる立場から、横濱伝統スカーフの販売促進を実施する。(資料5) 地元大学は主に横浜スカーフのデザインの価値認識に基づく研究活動や、博物館と連係をして学生を主体とするミニ展示などを展開している。 また、横浜の生糸輸出にまつわる中心的存在であるシルク博物館、横浜スカーフ・アーカイブを保管する横浜歴史博物館は企画展示などで支援をしている。
一定の統括下での活動展開はされていないが、それぞれが得意分野での力を発揮しており、スカーフ愛好層及び消費者へ横浜ブランドとしての横浜スカーフの価値訴求ができている点は大いに評価できる。
3.他事例との比較
横浜の輸出工芸品である「真葛焼き」及び「横浜柴山漆器」をあわせて、価値認識および継承の視点から比較を行う。(資料6)
両者の共通点は、開港地へ人と技術が集積し創始され、職人の分業制で製作されたこと。横浜は外国貿易商を通じて欧米の好みや流行情報を入手しやすかった点。輸出で外貨獲得をめざした国策に後押しされ、ジャポニズム工芸品として海外万国博などで評価をあげた点などである。両者とも高い技術と美術品としての価値を再評価する研究者やコレクターが存在する。
横浜は関東大震災、横浜大空襲などで町が崩壊し、職人離散や技術の継承が困難となったが、継承者の存在に大きな相違点がある。
真葛焼きは創始者から三代まで継承されたが横浜大空襲により、全てが焼失し伝統は途絶えた。一方、横浜芝山漆器は僅か1名ではあるが、伝統を継承する職人が製造の技術を現在に伝え、行政支援の下で横浜芝山漆器研究会が存在する。
横浜スカーフも海外へ輸出され愛された工芸品ではあるが、特筆すべきは、美術品ではなく服飾実用品として国内でも長く流通し、現在でも捺染技術を活用した横浜ブランドとして位置づけられる点である。
「真葛焼き」「横浜柴山漆器」「横浜スカーフ」は横浜開港後に海外へはばたき愛された日本の伝統工芸品である。輸出に特化した工芸品として時代のうねりと共生し、現状は三者三様である。継承が困難でも、歴史的価値及び従事した人や場所に付随する記憶を見過ごすことはできない。技術や作品は確かに存在する。刻まれた歴史と伝統は次世代にも繋いでいくべきものである。
4..今後の展望について
輸出用スカーフに詰めこまれた技術や絵柄が、横濱伝統スカーフとして繋がれているが、認知度はいまだ一部の関係者愛好者のコミュニティに留まっている。「シルクは横浜のプライド」(10)を体現しているスカーフを、より一般市民の関心へと広げる努力が必要である。
シルク関連イベントで、シンポジウムの西川パネラーから、「地域活性化とか地域特産品の関心は地方では強いが、大都市では熱量が低いと感じる」との発言があった。(11) 確かに、大都市では地域の認識を醸成しにくいので、地域として伝統や文化を保持する意義の確認ができる機会を設ける事である。まずは市民が前向きな危機感をもって、自分ごととして捉え、伝統や文化が持つ記憶やプライドを繋ぐ必要がある。
同時に、スカーフ産業としての生き残りには、新しいニーズを生みだす必要もある。スカーフを愛用してきたのは一定の年齢層に限定され、現在の各種活動も現状を維持するレベルに留まる。それにはアーカイブされている豊富な資料から「個性的」「キッチュ」「面白い」などのデザイン活用を一考してはどうだろうか。特に若年層へリーチし、活用法や着用機会を含めて新しい提案を模索することは、将来のスカーフ愛好者拡大につながる。シルクの価格帯が問題となる可能性があるが、多様なニーズを求め、シルクスカーフが保有する付加価値を過不足なく伝える手段を探索する時機である。
5.まとめ
日本の技術を駆使して海外へ輸出され、愛されてきた横浜スカーフの存在を知る人は少ない。横浜スカーフの歴史と伝統は開港に端を発したユニークで貴重な文化でもある。地場産業として生き残るのか、過去の栄光として記録にとどめるのか、経験・知識・技術をどのような形で記憶し、未来に継承していくかは市民も含めたオール横浜で取り組むべき課題である。
参考文献
注釈 参考文献
(1)
『濱手帖 関内関外横浜の文化情報誌4』PtoP合同会社、1981, p.6
(2).
横浜市技能文化会館(『横浜スカーフ木版更紗から現代まで』横浜市技能文化会館
1989, p. 9-10 筆者要約
(3)
「椎野正兵衛がウィーン万国博覧会より帰国後明治8年に販売輸出」、「椎野正兵衛商店が明治13年メルボルン万国博出品見本を参考に明治15年に輸出」など諸説ある。
神奈川経済研究所編『横浜スカーフの歴史』神奈川経済研究所1981, p.1
(4)
「昭和9年ハンカチの寸法を大きくしたものがスカーフとして英国に輸出された」、「昭和4,5年頃に製造、輸出」、「昭和7,8年頃に輸出」など諸説ある。
山崎稔恵「横浜の輸出スカーフ意匠に関する調査研究(三)―横浜スカーフ前史再考―」、『関東学院大学人間環境研究所所報』、2019年、p.59-60
(5)
北沢克夫編『横浜捺染 120年の歩み』日本輸出スカーフ捺染工業組合、1995年p. 41–42
(6)
観光みやげ用スカーフは各国の町の名前や地図をプリントしたもので、生地もシルクよりも合繊が多かった。
『濱手帖 関内関外横浜の文化情報誌4』PtoP合同会社、1981, p.8-9より抜粋
(7)
輸出実績は1950年の975万ドルから1964年には5000万ドルを越え、1976年には1億3170万ドルとピークを迎えた。日本国内向けも、1976年が推定出荷金額221億円、出荷枚数2790万枚とピークとなった。
神奈川経済研究所編『横浜スカーフの歴史』神奈川経済研究所1981, p.5-8
(8)
『濱手帖 関内関外横浜の文化情報誌4』PtoP合同会社、1981, p.7-9より抜粋
(9)
株式会社佳雅が中心となり開発したアウトドアでも使用可能な新シルク素材でスカーフを制作。昭和30年代の輸出スカーフのアーカイブから柄を選びベースデザインとした。
エクストリームシルク『DURE』の製造工程は県をまたいだ分業制。
神奈川県横浜(デザイン)→石川県小松(生地)→京都府丹後(精錬・ハイパーガード加工)→山形県米沢(プリント)→山形県鶴岡(水洗、防燃加工、乾燥加工)→宮城県石巻(縫製)→神奈川県横浜(ハトメ加工、仕上げ、梱包)
佳雅https://yosimasa.co.jp/product/(2024年12月6日閲覧)
捺染技術活用例 濱文様手捺染てぬぐい
株式会社ケイスhttps://www.hamamonyo.jp/ (2025年1月5日閲覧)
(10)
横濱コクーン・スクウェア2024年10月4-5日「シルクは横浜のプライド~スカーフに願いを~」イベント標語から借用
横濱コクーン・スクウェアhttps://yoko-hama-web.com/(2024年10月5日閲覧)
(11)
横濱コクーン・スクウェア2024年10月4-5日「シルクは横浜のプライド~スカーフに願いを~」イベント シンポジウム「横浜発シルク新たな挑戦とスカーフ復権」パネラー横浜開港資料館館長 西川武臣氏発言
横濱コクーン・スクウェアhttps://yoko-hama-web.com/(2024年10月5日閲覧)
参考文献
横浜市勤労福祉財団編『特別展 横浜スカーフ ―木版更紗から現代までー』横浜市勤労福祉財団、1989年
北沢克夫編『横浜捺染 120年の歩み』日本輸出スカーフ捺染工業組合、1995年
神奈川経済研究所編『地域経済シリーズNo.32 横浜スカーフの歴史』神奈川経済研究所、1981年
神奈川経済研究所編『地域経済シリーズNo.31 横浜スカーフの概要』神奈川経済研究所、1981年
『濱手帖 関内関外横浜の文化情報誌 4』PtoP合同会社、2020年
シルク博物館編『横浜から世界へ 海を渡った生糸』シルク博物館、2022年
『図説・横浜の歴史』編集委員会編『図説・横浜の歴史』、横浜市市民局市民情報広報センター、1989年
小泉勝夫『開港とシルク貿易』世織書房、2013年
安藤雅之編『講演会記録 横浜開港と横浜への絹の道』シルクセンター国際貿易観光会館シルク博物館部、1993年
門田園子『デザイン至上主義の世紀 横浜スカーフにみる近代』森話社、2023年
山崎稔恵「横浜の輸出スカーフ意匠に関する調査研究(二)」
『関東学院大学人間環境研究所所報 第13号』、2014年
研究報告「横浜の輸出スカーフ意匠に関する調査研究(三) ―横浜スカーフ前史再考―」,『関東学院大学人間環境研究所所報 第17号』、2019年
ウェブサイト
横浜繊維振興会https://www.yokohamascarf.com/ 2024年11月10日閲覧)
横浜コクーン・スクウェアhttps://yoko-hama-web.com/ycs/(2024年10月5日閲覧)
横浜シティガイド協会https://www.ycga.com/(2024年10月1日閲覧)
横浜市観光協会https://www.welcome.city.yokohama.jp/ 2024年12月18日閲覧)
関東学院大学横浜スカーフ研究プロジェクト
https://univ.kanto-gakuin.ac.jp/topics/20221224-001.html(2024年12月6日閲覧)
神奈川大学オリジナル横濱スカーフ
https://www.kanagawa-u.ac.jp/news/details_22639.html(2024年12月6日閲覧)
横浜市への「ふるさと納税」返礼品
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/zaisei/shisai-takarakuji-kifu/kifukin/kyoutsuuhenreihin.html(2024年12月20日閲覧)