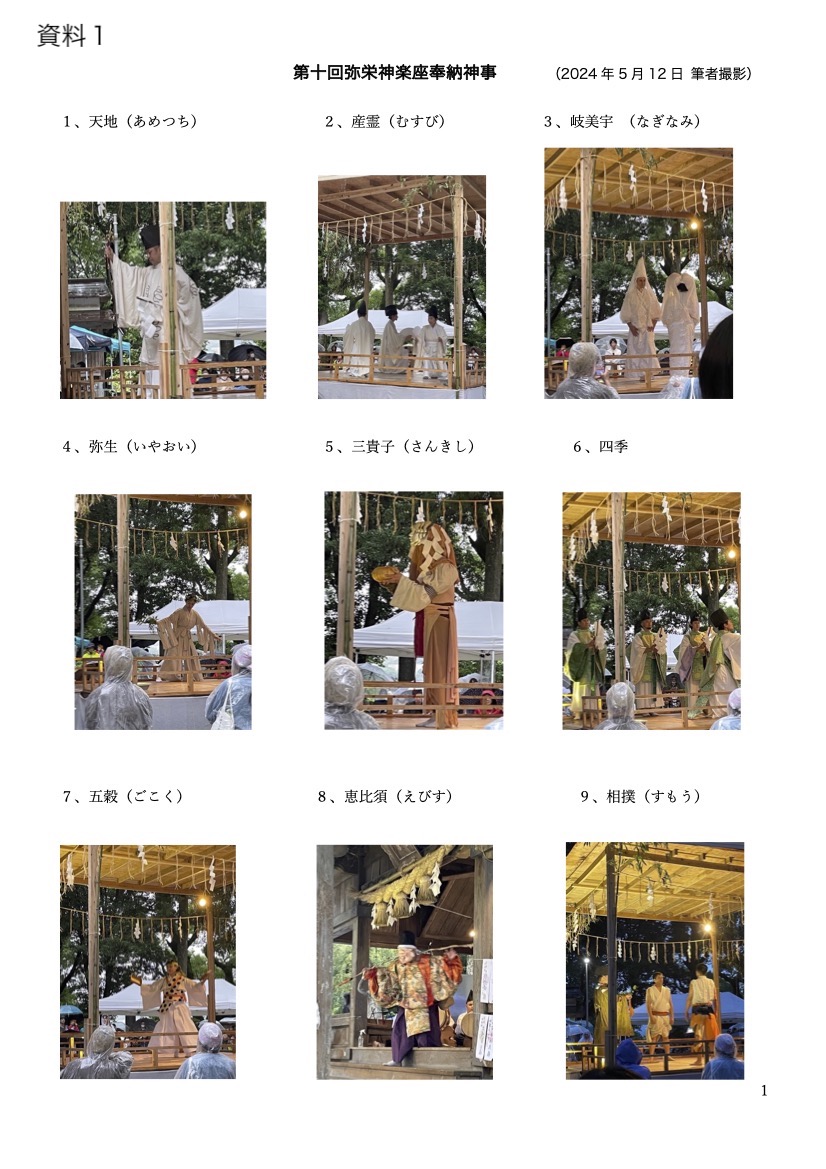明石で語り継がれる地域文化遺産と日本の食文化
はじめに
明石市は明石海峡に面し、東には大阪湾、西には播磨灘が位置し「鹿の瀬」と呼ばれる瀬戸内海有数の漁場が広がっている。ここでは明石のブランドとなっている明石鯛、明石蛸が水揚げされ、明石の魚市場「魚棚(うおんたな)」で市民に販売されている。現在は漁獲量が環境変化で減っているが玉筋魚が水揚げされ、「いかなごの釘煮」として春の風物となっている。魚棚商店街にはタコ焼き(明石焼)の有名店をはじめ、海産物や魚を販売する商店が並んでおり新鮮でつやつやとした明石鯛、魚箱から抜け出したうねうねと動く活きの良い蛸、昼網で漁獲された「生きのよい魚」が販売されている。スーパーでは冷凍技術の発達により鮮度が保たれ世界の各国から美味しい魚が私たちに提供されるようになった。しかし「お造り」を食べてみると冷凍物と活魚は一口食べるとわかる。本当に活魚の口当たりとその味は格別である。
魚が死ぬとしばらくして硬くなる(死後硬直)。硬直が過ぎると軟らかくなり、最後腐敗がはじまる。硬直前や硬直中の魚を生きが良い魚といい、硬直が解け始めたものを生きが悪いといわれる(註1)。魚の鮮度は生きが良いものと、生きが悪いもの、そして腐敗したものに区別される。つまり卸売場でセリにかけられる直前まで生きていた魚を活魚、鮮度はよいが卸売市場に卸される段階ではすでに死んでいる魚は鮮魚となる。私たちが最も美味しく食べるためには活魚、鮮魚の状態の魚が対象となる。
それでは生きた魚をどのようにして運んでいたのだろうか。海の生き物の運搬手段といえば船ではないだろうか。調査を進める中、魚を生きたまま運ぶ船「明石型活魚運搬船(資料1_写真1)」に焦点を置くこととなった。
1.基本データ
「明石型活魚運搬船」は白い船体に船底部分は青色の爽やかな色合いの木造船で姿形も美しい。船の船首(ミヨシ)は、上から真っ直ぐに立ち上がりほぼ垂直で、その船首の先には「一富士二鷹三茄子」の彫込みに金箔が美しく唐草模様が装飾されたデザインとなっている(資料1_写真2)。このほぼ垂直な船首デザインは大時化になっても大波を切り裂いて航行することができたので、他の船が休航している時でも魚市場まで活魚を運ぶことができた。その構造は、船首と船尾が西洋型、胴体が和船型となっている(註2)。胴体内部には生きた魚を運ぶために幾つかに仕切られた生簀がある(資料1_写真3)。この生簀に活魚を入れて運ぶのであるが、魚は生きているため酸素や温度を管理する必要があるので胴体や船底に海水を環流する小さな穴が多数開けられている(註3)。現在ではよく見られる養殖魚とちがい、天然魚は環境が変わることによって死んでしまうので環境にならす必要があった。しかし天然魚は人が与えたエサを食べないためやせ細り弱ってしまうので一刻も早く市場に運ぶ必要があった。ではどうやって遠くまで早く魚を運ぶことができたのだろうか。
2.歴史的背景
JR明石市駅前にある明石公園(明石城)の入口には中部幾次郎の銅像がある。中部が銅像になった功績の一つに、日本初めて1905年に活魚運搬船に石油発動機(エンジン)を取付けたことにある。それ以前は帆と櫓で漕ぐ船、押送船であった。当時西日本で魚を運搬するのは明石や淡路島が主となり、魚の取引が行われる中心は天下の台所大阪であった。そのため、瀬戸内海で獲れる魚は運搬にかかる日数によってランク付けがされ、マエ・イチアケ・シモと区別されていた(註4)(資料1_図1)。中部によって魚の運搬にエンジン付活魚運搬船が登場したことで、瀬戸内海西部地域からも蛸や鯛を活魚として運ぶことが可能になった。活魚の需要の高まりとともに、もっと大きく早く遠くから運べる船が必要になった。そして改良が繰り返され誕生したのが「明石型活魚運搬船」である。中部の生きた時代から遡るとかれこれ120年ほどの時が過ぎたことになる。日本は高度経済成長も経て時代は変化し続けている。1970年代には水産技術が発達し養殖業も盛んになり、道路交通網の整備とともに活魚トラックが活魚運搬船になり替わり、「明石型活魚運搬船」は衰退していく(註5)。しかし驚くことに「明石型活魚運搬船」は昨年まで現役で活躍していたのである。
3.事例のどんな点について積極的に評価しているのか
昨年の夏まで活躍した「明石型活魚運搬船」の名称は「第拾壱盛漁丸」という船である。木造船の寿命は約15年位といわれるが、「第拾壱盛漁丸」1981年1月に竣工、2023年夏に解体廃船なので、約43年も使われたことになる。「明石型活魚運搬船」が衰退していくとともに、木造造船所や船大工がいなくなった中で、通常の3倍も現役で航行させるには並大抵のことではなかったことは想像に難しくない。所有者の努力はもちろんのこと、「明石型活魚運搬船」の研究会が発足されていることからも、人々に愛された船は次世代に引き継がれるべき遺産だとわかる。もちろんこれによって明石が産業として栄えた証のようなもので、明石の生んだ文化・産業遺産である。そんな最後の「明石型活魚運搬船」の「第拾壱盛漁丸」の船内は、杉や桧材の木造りで日本人らしい生活空間が広がっている(資料2)。例えば神棚(船神様)があり、日本独自の装飾が施された欄間には松竹梅が彫られている。柱にも飾り彫りが施されている。船の中であるのに何とも日本家屋にお邪魔したかのような生活環境である。他の「明石型活魚運搬船」の船内がどうなっていたかはわからない。しかし外観である船首のデザインは共通で、唐草物が金色であることは「明石型活魚運搬船」の誇りであり特徴である。これには明石らしい関西人の派手好きとされる特性なのかもしれない。
4.国内外の他の同様の事例と比較して何が特筆されるのか
エンジン付の活魚運搬船によって、瀬戸内海で獲れた魚が大阪まで運ぶことが可能になった。それまでは櫓を押して船を航行する押送船があり、江戸時代に最も用いられ小型快速船とよばれていた。江戸周辺(東京湾)で漁獲された魚を江戸城下へ搬送していた。「明石型活魚運搬船」とは異なり、笹船のような姿形をしており、多くの漕ぎ手を担い海の中で早く進むために船首は細長くとがっていた。比較してみると、エンジンという動力の有無の差は大きい。また船首の形によっても長く航行、時化でも海で運搬でき、多くの漕ぎ手が要らないとなると、同じ木造船であっても「明石型活魚運搬船」へと移り変わっていくのだろう。
5.今後の展望について
明石鯛や明石蛸は産地で活魚として食べてこそ美味しい。人々が生の魚を食べる食文化があるかぎり活魚を求める習慣ははなくならない。また明石海峡の荒波や明石という地域だからこそ誕生した「明石型活魚運搬船」は、明石が産業の中心地であったと、書籍で語り継がれていくだろう。
まとめ
この卒業研究に取り組みながら、今晩の夕食にスーパーで購入した鯛のお造りを食べてみた。値札には五島列島産の解凍鯛と記載があった。最近は冷凍技術が進み冷凍ものと活魚の差がわからないほどになっている。確かに新鮮でおいしく食べたのであるが、魚棚商店街の鮮魚店で買った五島列島産の天然魚活鯛の食感は今でも忘れることはできない。これからも食文化として「お造り」技術と共に変化していくと考えられるが、活魚文化はもう一つのお造り文化として続いていくものであろう。このレポートは食文化としての「お造り」と地域の産業遺産「活魚運搬船」が表裏一体として繋がっていることを考えまとめとした。
参考文献
【参考文献・資料】
[注記]
(註1) 野口栄三郎『水産研究叢書7 漁獲物の鮮度保持』社団法人 日本水産資源保護協会、1965年、5頁
(註2) 瀬戸内海歴史民俗資料館『瀬戸内地方の船大工-重要有形民俗文化財指定の用具と技術-』瀬戸内海歴史民俗資料館、1993年、5頁
(註3) 原田輝雄、松居鴨夫、長谷川彰、窪田三朗ほか『ハマチ・カンパチ 養魚講座 第4巻』緑書房、1969年、165~166頁
(註4) 河野通博『漁場用益形態の研究』河野通博、1961年、349頁
(註5) 酒井亮介『農林統計調査 40巻11号(通号476)』農林統計協会、1990年、16~19頁
[参考資料]
・明石市立図書館『明石型生船調査資料集・生船写真帖-生船研究会・あかし市民図書館共同研究-』明石市立図書館、2019年
・あかし市民図書館『明石型生船調査報告書-生船研究会・あかし市民図書館共同研究-』あかし市民図書館、2022年
・あかし市民図書館『明石型生船調査報告書 Vol.3-生船研究会・明石市立文化博物館・あかし市民図書館共同研究-』あかし市民図書館、2024年
・金井清『最後の明石型生船第拾壱盛漁丸』生船研究会、2020年
・加瀬野久志『滅びゆく機帆船』加瀬野久志、1986年
・西日本漁業経済学会『経済発展と水産業』西日本漁業経済学会、1977年
・太田雅士『食い倒れ大阪発』文芸社、2002年
・明石市文化・スポーツ室歴史文化財係『明石の木造船』明石市立文化博物館、2022年
・胡桃沢勘司『押送船-江戸時代の小型快速船-』岩田書院、2018年