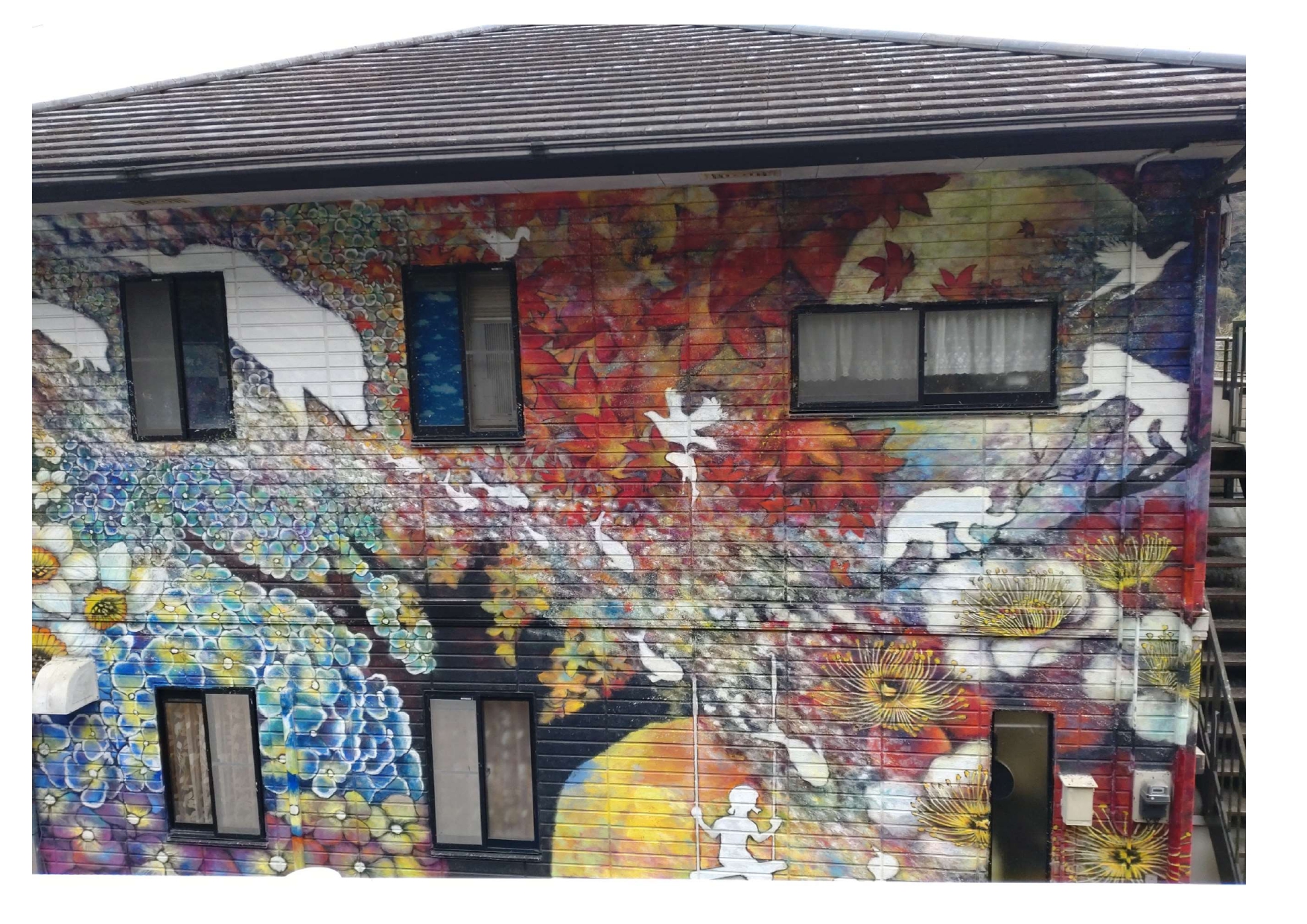金丸座・令和の大改修 ~芸術と歴史が織りなす、讃岐の古き艶やかな舞台~
金丸座は、昔から大切にされてきた建物で、重要文化財に指定されている。しかし、近年の南海トラフ地震のような大きな地震が起きたときに、人々の命を守るためには補強が必要である。そこで、2020年から補強工事が始まる。金丸座の見た目や文化財としての価値を守りながら、地震に強い建物にする取り組みが進められた。
1 基本データと歴史的背景
1-1基本データ
名称: 金丸座(旧金毘羅大芝居)
建築様式: 歌舞伎専用の芝居小屋[資料2]
建物構造:間口: 24m、奥行: 44m、正面入り母屋作り、中央部切妻造段違、背面寄棟造
葺き: 本瓦葺と桟葺瓦の併用
建築年: 天保6年(1835年)
所在地: 〒766-0001 香川県仲多度郡琴平町乙1241
座席数:約730席
設備:一階客席、二階客席、花道、回り舞台、楽屋、空井戸
1-2歴史的背景
旧金毘羅大芝居は、1835年江戸時代末期に完成した。歌舞伎芝居が花盛りであり、歌舞伎専用の劇場が各地に建てられた。そのような時代背景の中で建てられ、その後も長い年月を経て現在まで残る最古の劇場建築である。
建物はもともと金山寺町(現在、歴史民俗資料館)に位置していた。江戸時代には富場として栄え、多くの興行が開催され、上方の千両役者たちがここで名演を披露した。
1-3保存と復元: 金毘羅大芝居の歴史的復興
天保6年(1835年)に高松藩寺社方からの許可を受けて、大都市に匹敵するような規模や構造を持つ常設の芝居小屋として建設された。その名声は全国に広まり、東西の名優たちが金毘羅大芝居の舞台に立つこととなる。
しかし、近代以降の娯楽の変化に伴い、映画館としての利用や所有者の変更により、その名は次第に衰退する。町の人々はこの金丸座の保存を熱望し、保存運動が始まり、1970年に国の重要文化財に指定、1976年には、愛宕山中腹に天保時代の姿を受け継ぐ舞台が再び甦えったのである。
2.事例のどんな点について積極的に評価しているのか
2-1 金毘羅大芝居の歴史的な遺産の再生
1975年度の移築大改修後、1985年から「四国こんぴら歌舞伎大芝居」[資料1]が毎年開催され、国内外の歌舞伎ファンが訪れ、春の風物詩として親しまれる。毎年、春の風物詩として公演されていたが、コロナ渦や南海トラフ地震対策補強工事により、2020年より中止となった。今後の公演の継続は、金毘羅大芝居が文化遺産としての役割を果たし続けることを示しており、地域の文化振興に貢献することが評価される。
2-2 令和の大改修において実施された取り組みの内容や成果
現在の耐震基準に合わせるため、2020年10月から2022年3月まで、その歴史的価値と景観を損なわずに、耐震性を向上させることを主眼に置いて実施された。大きく見た目を変えない工夫が施されている。[資料4][資料5]
南海トラフ地震などの大規模地震にも耐えられるよう、基礎、壁、床などの構造を補強した。
こんぴら歌舞伎は歴史的な価値を保ちながら、現代でも安心して観劇できる施設として、地域の文化遺産を守るだけでなく、未来の世代にも引き継ぐための重要なステップであることを評価する。
2-3 地域社会や観光産業に与えた影響や貢献
金丸座が琴平町に観光客を呼び込むことで、観光客が利用する飲食店や宿泊施設、土産物店などの地域のビジネスに利益をもたらした。[資料7]
地域の観光資源としての価値を高め、歴史的な建造物は観光客を地域に引き寄せる要因となっている。国内外からの観客を受け入れる場として機能することで、異なる地域や文化間の交流が促進される。地域経済の活性化だけでなく、文化の発展にも寄与している点が評価される。
3.国内外の他の同様の事例と比較して何が特筆されるのか
愛媛県内子町の内子座の特性と比較を通して魅力を探る。
内子座の基礎データ
名称: 内子座
形式: 木造の2階建て瓦葺き入母屋造り
建築年: 1916年(大正5年)
所在地:〒791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子2102
座席数:約650席
内子座は、大正天皇の即位を祝うために内子町の有志によって建設された伝統的な木造劇場であり、地域の文化的アイコンとして長い歴史を刻んできた。1982年に内子町指定有形文化財に指定された後、1983年から1985年にかけて大規模な復元工事が行われ、2015年には国の重要文化財にも指定されている。
内子座は歌舞伎や文楽、映画、コンサートなど、多岐にわたる公演やイベントが開催され、地域住民だけでなく町外からの訪問者にも利用されている。そのため、内子座は地域内外の芸術文化活動の拠点として機能しており、文化交流や地域活性化の場としても高い価値を有している。内子座は小規模な町の劇場であるがゆえに、集客面での課題や運営費用の確保における財政的不安という現実的な問題にも直面している。こうした課題を克服するためには、観光資源としての内子座の価値をさらに高め、広域的な集客を促進する戦略の構築が求められる。2024年9月から約4年間、耐震補強工事を行い地震に強い建物にする取り組みが進められている。
一方で、芝居小屋再構築の先駆者的存在である金丸座は地域の魅力を輝かせ、文化芸術の振興と継承を促進するための重要な一翼を担っている。金丸座は日本最古の芝居小屋として、公演は歌舞伎と限定されている。この独自の伝統芸能の継承は、金丸座の特色の一つであり、特筆される。
木造の伝統的な劇場の構造を保持しており、その建築様式や舞台装置、客席の配置などは、江戸時代の劇場の特徴をよく示している。このような伝統的な建築物は、現代の技術や建築様式の進化と比較して、歴史的な建造物として貴重である。
こんぴら歌舞伎の成功が、各地で廃屋同然になっていた芝居小屋の復活に大きな影響を与え、金丸座の復活は、市民による復興運動の始まり、再び芝居小屋での興業のきっかけとなったこと、興業を継続していることは特筆される。
金丸座の優位性は、入口の鼠木戸、左右両桟敷・枡席・大向こうなどの客席だけではなく、本花道と仮花道の花道、花道に設けられた妖怪などが登場するスッポン、役者が早変わりで出入りする空井戸、廻り舞台とその下の奈落など歌舞伎小屋特有の本格的な構造と仕掛けがそのままの状態で残されていることは特筆される。
4.今後の展望について
4-1今後の維持・管理・活用方針や取り組み
施設や設備の定期的な点検・メンテナンスを行い、安全かつ快適な環境を提供することが重要であり、設備や座席の改善など、時代に適応したバリアフリー化で、観客の利便性を向上させる取り組みである。
4-2地域社会や観光産業へのさらなる貢献のための施策やアイデア
地域の若者や文化愛好者に対して、歌舞伎や伝統芸能の魅力を伝え、次世代への継承を図るプログラムの充実が求められる。地域の観光名所やイベントとの連携を強化し、金丸座を訪れる観光客の増加を図り、周辺の観光スポットとの連携パッケージや観光情報の提供、地域の伝統文化体験プログラムの充実など、観光客に魅力的なプランを提供する。
5.まとめ
金丸座は、日本の伝統文化である歌舞伎の発展を支えてきた重要な施設である。また、地域の学校や文化団体との連携を通じて、次世代に歌舞伎や伝統文化の魅力を伝える教育の場としても機能しており、その文化的意義や地域社会への貢献は高く評価されている。
2020年から行われている耐震補強工事では、歴史的な外観を損なわずに構造強化を実現する工夫が施されており、文化財保護と安全性向上の両立を目指した取り組みとして注目された。同時に、バリアフリー対応を含む現代の利用者ニーズに応じた施設整備が求められる。
これらの取り組みを通じて、金丸座は歴史的文化財としての価値を保ちながら、より多くの人々に開かれた施設へと進化していくことが期待される。
-
 [資料1]
[資料1]
四国こんぴら歌舞伎大芝居の始まり
1984年6月中旬、金丸座が観光地として名を馳せている中、テレビ番組の撮影が行われることになった。撮影のために訪れた歌舞伎俳優たち(中村吉右衛門、澤村藤十郎、中村勘九郎)は、その美しい舞台に心を打たれ、「ぜひこの舞台で演じたい」と強く感じた。
その後、1984年7月5日と6日に金丸座での撮影が実施され、俳優たちは夏の暑さの中で熱気あふれる撮影を経験した。この感動的な体験が、金丸座での「こんぴら歌舞伎」の復活への道を開いた。
金丸座は1970年に国の重要文化財に指定されており、歌舞伎公演への不安があったものの、文化庁と松竹株式会社の協力によって「こんぴら歌舞伎」として再生された。1985年6月には「第1回四国こんぴら歌舞伎大芝居」が開催され、3日間にわたる5回の公演は多くの観客を魅了した。
2024年5月10日筆者撮影 -
 [資料2]建築様式やデザインは、大阪の有名な劇場である大西座(現在の浪花座)を模範としており、当時の劇場建築において大西座が先駆的であり、その影響が広く及んだためである。
[資料2]建築様式やデザインは、大阪の有名な劇場である大西座(現在の浪花座)を模範としており、当時の劇場建築において大西座が先駆的であり、その影響が広く及んだためである。
歌舞伎芝居の舞台構造や客席配置も特筆すべき点であり、舞台の奥行きや回り舞台の大きさ、舞台下の奈落など、歌舞伎の演目を効果的に演じるための構造が施されている。当時の大都市の劇場と比肩するほどの格式を持っていた。観客席上方の大梁に「ブドウ棚」と「かけすじ」の痕跡が発見されたため、平場及び向う桟敷天井部には「ブドウ棚」を復原し、花道上部には「かけすじ」を復元整備することが決定された。
こんぴら歌舞伎オフィシャルサイトhttps://konpirakabuki.jp/index.html(2025年1月1日閲覧) -
 [資料3]令和6年度 第37回 四国こんぴら歌舞伎大芝居
[資料3]令和6年度 第37回 四国こんぴら歌舞伎大芝居
2020年のコロナ禍以来、5年ぶりの開催となる。期間は4月5日から21日まで(11日は休演)である。国内外からの集客で賑わい大成功となった春の風物詩「こんぴら歌舞伎大芝居」である。
2024年4月20日筆者撮影 -
 [資料4]金丸座では、外観を維持しつつ耐震性を向上させるための補強工事が行われた。この工事では、壁内部に強度の高い合板を埋め込むなど、建物の構造を見直しながらも景観を損なわない工夫が施された。具体的には、土壁の内側に新たな合板を追加し、楽屋の畳を薄くすることで補強材を取り付けるなどの手法が用いられた。その結果、建物は震度6強の地震にも耐えられる構造となった。工事の多くは来場者から見えない部分で行われており、金丸座本来の伝統的な美観を保ちながら安全性を高めることに成功した。2024年5月10日筆者撮影
[資料4]金丸座では、外観を維持しつつ耐震性を向上させるための補強工事が行われた。この工事では、壁内部に強度の高い合板を埋め込むなど、建物の構造を見直しながらも景観を損なわない工夫が施された。具体的には、土壁の内側に新たな合板を追加し、楽屋の畳を薄くすることで補強材を取り付けるなどの手法が用いられた。その結果、建物は震度6強の地震にも耐えられる構造となった。工事の多くは来場者から見えない部分で行われており、金丸座本来の伝統的な美観を保ちながら安全性を高めることに成功した。2024年5月10日筆者撮影 -
 [資料5]外壁を鉄骨の筋交いなどで補強している。外観上目立たない側面や背面に、鉄骨の筋交いを追加することで、建物の強度を高めた。これにより、耐震性が向上し、建物全体の安定性が確保された。2024年5月10日筆者撮影
[資料5]外壁を鉄骨の筋交いなどで補強している。外観上目立たない側面や背面に、鉄骨の筋交いを追加することで、建物の強度を高めた。これにより、耐震性が向上し、建物全体の安定性が確保された。2024年5月10日筆者撮影 -
[資料6]令和7年度 第38回 四国こんぴら歌舞伎大芝居
こんぴら歌舞伎オフィシャルサイト https://www.konpirakabuki.jp/schedule/
2024年12月10日閲覧
(非掲載) -
 [資料7]琴平町の総面積は8.47km²で(国土地理院)、町域は東西3.3km、南北5.3kmであり、象頭山の山すそに沿っており、徒歩で回れるほど小さな町である。伝統と金毘羅さんの町である琴平町は、金刀比羅宮を中心とした門前町として、古くから信仰の対象として栄えてきた。町の景観は、宗教的な場所としての歴史と伝統が息づいており、毎年多くの参詣客が訪れる。
[資料7]琴平町の総面積は8.47km²で(国土地理院)、町域は東西3.3km、南北5.3kmであり、象頭山の山すそに沿っており、徒歩で回れるほど小さな町である。伝統と金毘羅さんの町である琴平町は、金刀比羅宮を中心とした門前町として、古くから信仰の対象として栄えてきた。町の景観は、宗教的な場所としての歴史と伝統が息づいており、毎年多くの参詣客が訪れる。
琴平町は、江戸時代からの歴史的建造物や伝統的な町並みを多く残しており、特に、金丸座は国の重要文化財に指定されている。春の風物詩として四国こんぴら歌舞伎大芝居公演が開催され、多くの歌舞伎ファンや観光客を魅了している。こんぴら歌舞伎は、毎回2万人を超える客を呼び込み、経済波及効果は10億円と言われる興行である。また、これらの歴史的建造物を活用し、地域の魅力を引き出すための取り組みも行われている。2024年5月10日筆者撮影 -

-
 令和6年度 第37回 四国こんぴら歌舞伎大芝居
令和6年度 第37回 四国こんぴら歌舞伎大芝居
春の風物詩 「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が、香川・琴平町の金丸座に華麗に復活した。令和の大改修、コロナ禍以来、5年ぶりの開催となる。町中にのぼりが立てられて、歌舞伎の町となっている。2024年4月20日筆者撮影
参考文献
香川県中学校社会科研究会編『新版 香川の歴史ものがたり』、(株)成光社、2014年
栗田勇編『海の聖地 金毘羅』、(株)山陽新聞社、1983年
朝日新聞高松支局内 全日本写真連盟・香川県本部編『さぬき風物詩』、(株)朝日新聞出版、1988年
前川久夫編『大人の遠足』、JTBパブリッシング、2007年
香川県教育委員会『香川の文化財』、(株)広真、2021年
石井文男編『香川県の歴史散歩』、(株)山川出版社、1996年
溝尾良隆編『観光まちづくり現場からの報告: 新治村・佐渡市・琴平町・川越市』、(株)原書房、2007年
香川県ホームページ
https://www.pref.kagawa.lg.jp/kouryu/tokei/kankoukyakudoutaicyosa202307.html(2024年4月7日閲覧)
琴平町ホームページ
https://www.town.kotohira.kagawa.jp/(2024年5月1日閲覧)
こんぴら歌舞伎オフィシャルサイトhttps://konpirakabuki.jp/index.html(2024年5月1日閲覧)
うどん県旅ネットhttps://www.my-kagawa.jp/konpira/feature/kotohiragu/spot
(2024年5月1日閲覧)
琴平町の町並み
http://matinami.o.oo7.jp/sikoku/kotohira.htm(2024年5月1日閲覧)
内子座編集委員会編『内子座地域が支える町の劇場の100年』(株)学芸出版社、2016年
内子町ホームページhttps://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/132383.html(2024年12月10日閲覧)
内子町観光サイトhttps://www.we-love-uchiko.jp/spot/(2024年5月1日閲覧)
内子座ホームページhttps://www.town.uchiko.ehime.jp/site/uchikoza/
(2024年12月10日閲覧)
国際交流基金、賀古唯義、江戸時代の息吹をつなぐ 芝居小屋の魅力とは
https://performingarts.jpf.go.jp/article/6976/(2024年5月1日閲覧)
匠の学舎アカデミー、技心館https://takumi-manabiya.com/(2024年5月1日閲覧)