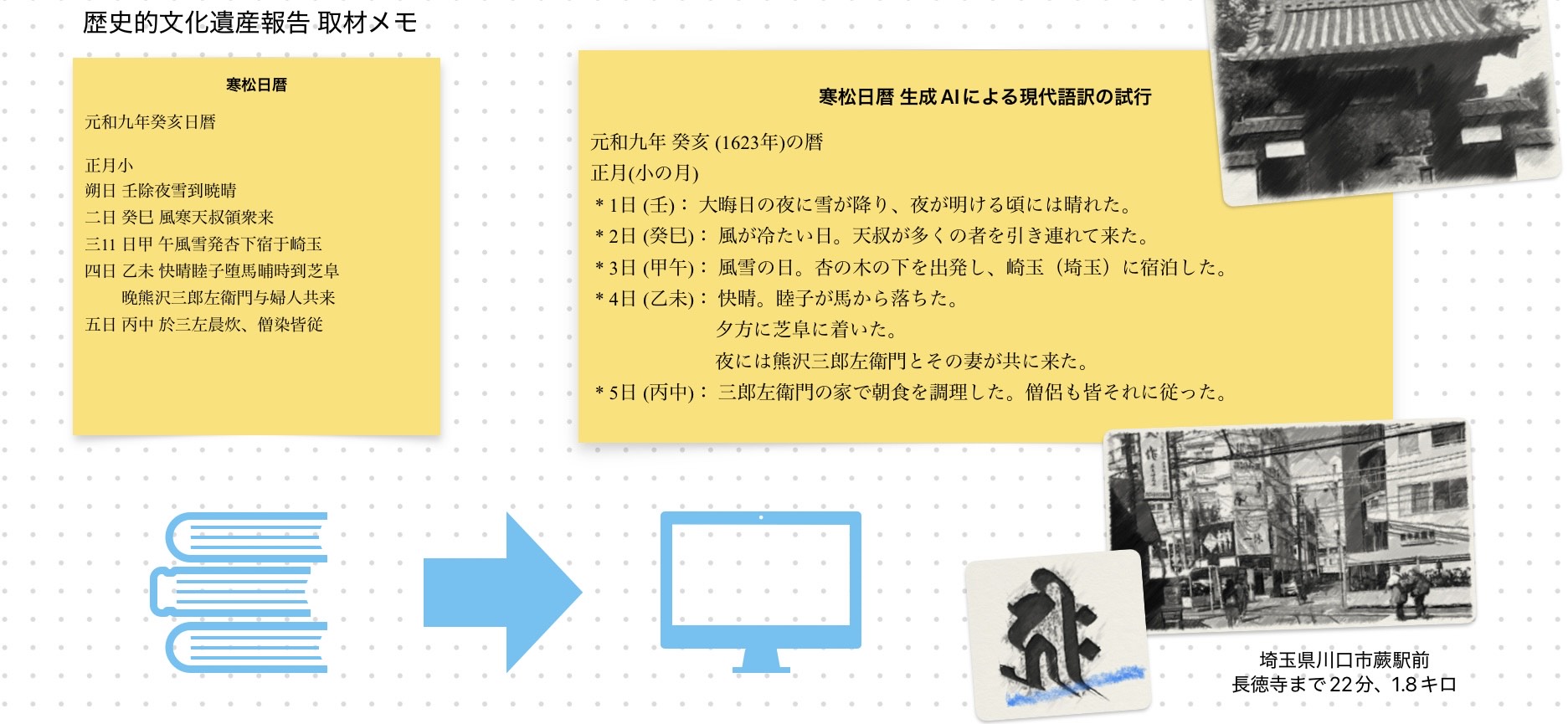成城:洗練と安らぎが織りなす街の魅力
はじめに
東京都世田谷区に位置する成城は、都内有数の高級住宅地として知られている。「せたがや百景」にも選ばれた美しいイチョウ並木や桜並木、そして生垣や豊かな緑に囲まれた邸宅が織りなす景観は、街全体に落ち着きと潤いを与えている。
この地は、かつて多くの文人たちが居を構えたことでも知られ、その歴史が文化的な薫りを深くしている。駅前の賑わいから一歩足を踏み入れると、すぐに閑静な住宅街が広がり、都市の利便性と豊かな住環境が両立している。
また、成城学園をはじめとする教育機関が多く、若い世代の活発な往来があることで、年齢層に偏りなくバランスの取れた活気が生まれている。これは、往々にして閉鎖的になりがちな高級住宅地のイメージとは一線を画し、開放的で心地よい雰囲気を醸し出している。
本稿では、このような多面的な成城の魅力について深掘りし、その持続可能性と将来に向けた展望を考察する。
歴史的背景
成城の歴史はおよそ100年前に遡る。当初、新宿区牛込に位置していた成城学園は、より広大な土地を求めて1925年(大正14年)、当時雑木林が広がっていたこの地へ移転してきた。この移転は、単なる学園都市にとどまらず、やがて独自の文化と景観を持つ街へ発展する大きな転機となった。学園は移転に伴う莫大な費用の捻出に苦慮していた。そこで、自らが土地を開発・分譲する「ディベロッパー事業」に着手した。学園に隣接するエリアには、整然とした広い道路が整備され、一区画210坪から450坪という広い敷地や景観に配慮した緑化が施された。こうして学園を核に、「理想の学園都市」づくりが目指された。そして開校から2年後の1927年(昭和2年)小田急線が開通し、「成城学園前駅」が設置されたことで、開発が更に進んだ。
この街を文化的な住宅地として一躍有名にしたのは、1930年(昭和5年)に開催された朝日新聞社が主催する「朝日住宅展」であった。これは、朝日新聞社が「新時代の中小住宅」の設計を一般から募集し、入賞した作品を実際に成城に建設・分譲した企画であった。その後の住宅建築にも繋がる「家族本位の設計思想」が取り入れられ、西洋風のモダン住宅が建てられた。また、大正デモクラシーの流れに沿った新しいライフスタイルへの憧れという時代背景もあり、成城学園の先進的な教育と相まって「緑豊かでハイカラな学園都市」のイメージを高める要因の一つとなった。
このような環境に多くの文化人が惹きつけられた。北原白秋、平塚らいてう、柳田国男、野上弥生子、らが居を構え、現在にもつながる文化的な雰囲気の街になるきっかけが作られた。
成城学園開校から6年後の1931(昭和6年)には成城のもう一つの礎となる、のちの映画会社「東宝」に発展する「P.C.L(写真科学研究所)」が丸の内より移転してきた。P.C.Lは成城にトーキーの撮影・録音の請負と技術開発を行う施設を設置したが、のちに東宝撮影所となり戦前、戦後を通じ多くの映画が製作された。戦後は「七人の侍」「ゴジラ」などもここで撮影された。黒沢明、山本嘉次郎などの映画監督。三船敏郎、石原裕次郎ら、多くの映画スターが続々と当地に居を構え、さながら「日本のハリウッド」や「日本のビバリーヒルズ」と称された時代を迎えた。[註1]こうして、成城には「映画の街」として新たな魅力が加わった。
住民自治による街つくり
成城はまず学園の開発により、碁盤目状の道路、広い敷地、生垣や樹木による緑化など、街の骨格が形成された。さらに、住宅創成期には住民相互による「生垣と庭園設置の自主的な申し合わせ」が行われ、その後の街並み形成と人的交流に大きく貢献した。長年にわたり良好な住宅環境を維持してきたのは、行政や企業主導ではなく、住民が自主的に築き上げてきたことによるものである。バブル経済崩壊後、敷地の細分化、緑や生垣の減少、街並みと調和しない建物の出現といった問題が顕在化した。これに対し自治会を中心に「成城憲章」を2002年に制定した。その前文は以下の通りである。
「私たちは21世紀の初頭に当たり、時代の変化に対応しながら、緑の保全と創出を基本とする成城らしさに溢れた街並みを継承発展させ、いつまでも住み続けることを願い、成城に住む人々の自治を共助の精神によって育まれていくまちづくりの基本理念を共有するため「成城憲章」を制定することとします。」[註2]
憲章には、建築や開発に伴って遵守すべき事項や緑の保全、街並みや美観への配慮などが盛り込まれている。これが自治会を中心に住民たちによって運用され、良好な住宅環境の保全に貢献している。
田園調布との比較
成城の特性をより際立たせるため、同じく東京の高級住宅地の田園調布と比較する。田園調布の歴史は1918年に実業家・渋沢栄一によって提唱された「理想的な住宅地である田園都市の開発」を目的とする「田園都市株式会社」の設立に始まる。1920年代に分譲が開始され、その後、地元自治会による厳格な環境保全活動によって現在の田園調布の姿が形作られた。成城の始まりとほぼ同じ時期だが、設立の目的は大きく異なっていた。成城が『学園都市』を志向したのに対し、田園調布は『理想的な住宅地』として開発された点である。当初における街の「デザイン」の違いが、その後の発展に大きな差を生むことになる。現在、成城には成城学園のほかにも東京都都市大学付属小・中・高や科学技術学園など、多くの教育機関が集積している。さらに、小田急沿線における小・中・高向けの塾も多数存在するため、学生の活発な往来が絶えない。また、多くのクリニックが進出していることで、年齢に偏りなく駅周辺の繁華街は活気に満ちている。一方、田園調布は閑静な住宅環境を優先した為、店舗が少なく駅周辺は閑散としている。また、近年は空き地や手入れされていない家が目立ち始め、かつての活気を失いつつあるという指摘もある。[註3]成城も田園調布と同様に土地の相続や分割問題、緑の減少といった課題を抱えるも、街の流動人口が保たれている為、『高級住宅地のゴーストタウン化』といった事態には至っていない。
今後の展望について
時代の流れとともに、成城の街並みは表情を変化させている。緑や生垣の減少、敷地の細分化、不調和で景観を損ねる建物の増加や駅周辺の交通渋滞といった問題により、生活環境や景観は従来の良さが失われつつある。
「成城憲章」に続き2014年には成城が目指すべき将来像として「成城ビジョン」が制定された。「緑とゆとりに包まれた公園のような環境を持つまち」「学園都市の伝統を引き継いだ文化の薫りたかいまち」「成城住民ひとりひとりの努力による自治と共生の精神で育まれるまち」の3項目である。[註4]これらは極めて有意義であるが、強制力を持たない紳士協定にとどまるため、緑化や景観に非協力的な住民への対応には限界がある。このため、行政との連携による条例の制定や、文化資産の積極的な発信を通じて街全体の価値を高め、住民の意識向上を図ってゆく必要がある。なぜなら、文化資産を住民が再認識することで地域への愛着を深め、緑化や環境保全への意識を高めるからである。
成城の文化資産としては「猪股庭園」及び「旧山田住宅」などが挙げられる。「猪股庭園」は昭和の巨匠と言われた吉田五十八による近代数寄屋建築と、田中泰阿弥が作庭に関与した趣のある名庭園である。また、「旧山田住宅」は昭和初期の和洋折衷様式を残すモダン住宅で文化的価値が高く、それぞれ保存の対象となっている。また、「理想の学園都市」の痕跡を残す道路や生垣などの景観保護や、「映画の街」として栄えたゆかりの場所の整備も重要な課題である。いずれも成城の歴史遺産であるが、これらの価値が十分に伝わっているとは言い難い。成城の多面的な魅力を掘り起こし、更に発信すべきである。
まとめ
本稿では成城の魅力を歴史的、社会的な側面から考察し、その持続可能性と未来への展望について論じた。日本にはヨーロッパの主要国のように景観を守る強力な法律が存在しない。欧州景観条約が景観への「配慮を義務付けている」のに対し、日本の景観法は「考慮を促す」に留まる。[註5]このような制約がある中でも、成城は住民の自治を基盤とし、文化資産の保存・発信だけではなく、新たな価値の発見や、現代の生活に合わせた活用法の模索を通じて、緑豊かで文化的な魅力ある街として、将来にわたって維持・発展していくことができるであろう。
-
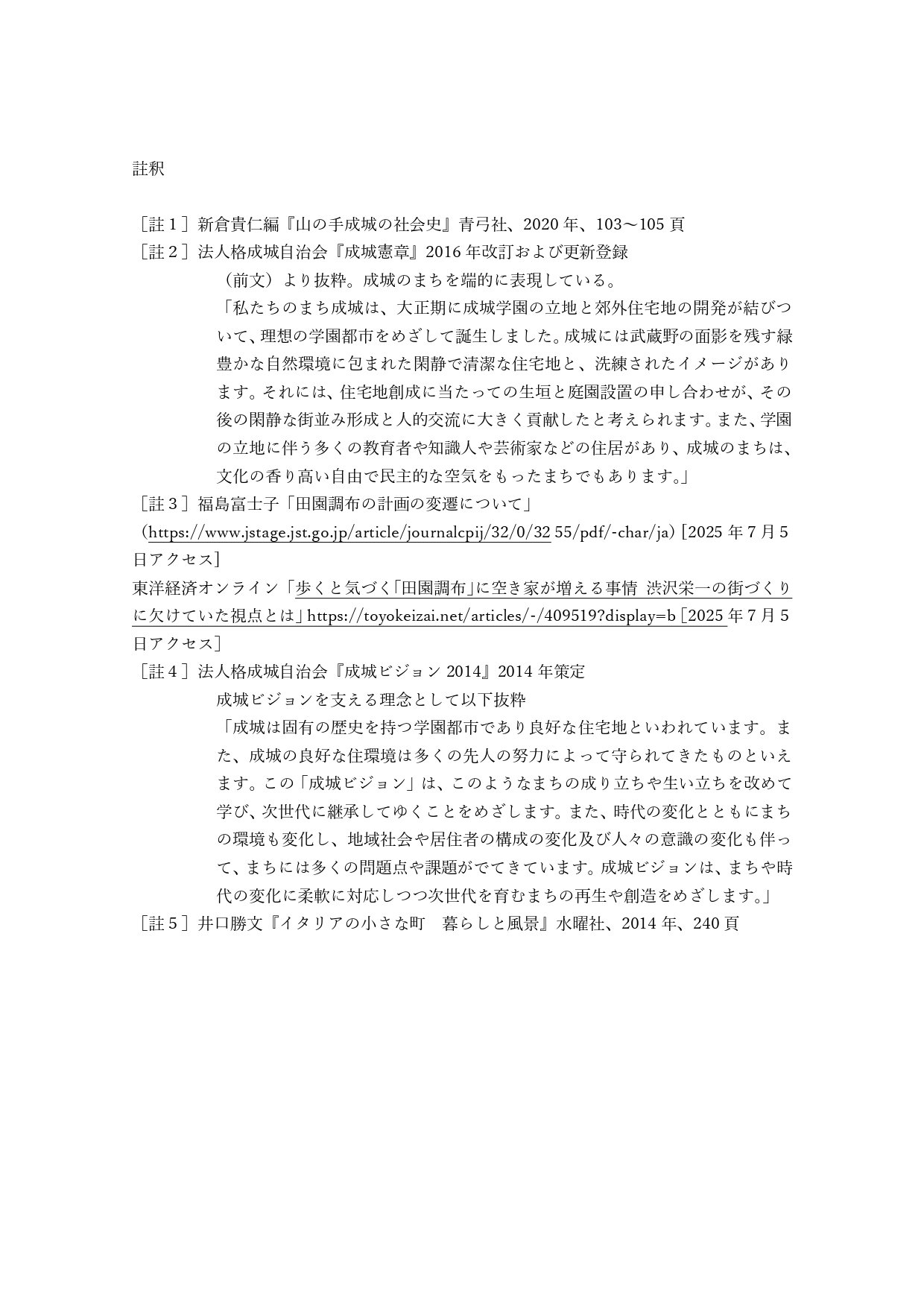
-
 成城の銀杏並木(2024年12月11日 筆者撮影)
成城の銀杏並木(2024年12月11日 筆者撮影)
成城学園の正門からの東に伸びる直線道路に沿って広がる銀杏並木。周囲の景観と調和して美しい街並みを形成している。この銀杏は、開発当初に成城学園の学生たちの手によって植えられた。「理想の学園都市」を築こうとした当時の人々の情熱が今に伝わるようである。 -
 成城さくら通り (2025年4月3日 筆者撮影)
成城さくら通り (2025年4月3日 筆者撮影)
成城北口から続く成城さくら通りは、美しい桜並木が特徴で、「せたがや百景」にも選定されている。両側には邸宅が並ぶ。整備されたまっすぐの広い道とさくら並木は、「理想の学園都市」としての成城の理念を体現している。 -
 東宝撮影所 (2025年7月14日 筆者撮影)
東宝撮影所 (2025年7月14日 筆者撮影)
1931年、のちの映画会社「東宝」に発展する「P.L.C.(写真科学研究所)」が丸の内より成城へ移転してきた。入口壁面に描かれているのは「七人の侍」のワンシーン。現在でも映画や多くのCM撮影が行われている。 -
 成城6丁目の生垣(2025年4月1日 筆者撮影)
成城6丁目の生垣(2025年4月1日 筆者撮影)
約1世紀前の開発当初の面影をとどめる生垣。当時、広い区画に大谷石で低い土台が設けられ、住民たちが互いに協力して生垣や庭園を設置する自主的な取り決めを行った。これにより、地域全体で統一感のある美しい街並みが形成された。 -
 成城の街並み(2025年7月14日 筆者撮影)
成城の街並み(2025年7月14日 筆者撮影)
この住宅に残る2本のヒマラヤスギは、開発当初の面影を今に伝えている。当時、洋館にはヒマラヤスギ、和風建築の家には松の植栽が奨励された歴史があり、その名残として成城では今もヒマラヤスギがよく見られる。しかし、美しい景観が電柱や電線によって台無しになっているのは残念である。地中化が進むよう願ってやまない。 -
 旧山田家住宅(2015年7月15日 筆者撮影)
旧山田家住宅(2015年7月15日 筆者撮影)
1937年(昭和12年)に実業家の楢崎定吉氏によって建築された。この建物は現在、世田谷区指定有形文化財として保護されている。建築様式としては外観が洋館でありながら、内部は和室が設けた和洋折衷様式が特徴であり、部屋の間取りやランドリーシュートといたユニークな設備もそのまま残されている。 -
 猪股庭園(2025年7月14日 筆者撮影)
猪股庭園(2025年7月14日 筆者撮影)
旧猪股邸は、(財)労務行政研究所の初代理事長を務めた猪股猛氏の邸宅として1967年に建てられた。その後、1996年に世田谷区へ寄贈され、現在は一般公開されている。近代数寄屋作りの巨匠といわれる吉田五十八によって設計された。詫びの精神が息づく数寄屋造りが特徴で、吉田五十八が手掛けた個人住宅で現存するものは少なく、貴重な建築物である。
参考文献
参考文献
新倉貴仁『山の手「成城」の社会史』青弓社、2020年
世田谷区立郷土資料館『成城の歩み100年』世田谷区立郷土資料館、2024年
世田谷区生活文化部文化・交流課編集『ふるさと世田谷を語るー祖師谷・成城・喜多見』世田谷区生活文化部文化・交流課、1998年
中江泰子・井上美子『私たちの成城物語』河出書房新社、1996年
成城学園教育研究所編『学校と街の物語-成城学園の100年をつくったひとびと』新潮社図書編集室、2017年
高田雅彦『成城映画散歩 あの名画も、この傑作もみな東宝映画誕生の地・成城で撮られた』白桃書房、2017年
法人格成城自治会『成城のまち』成城自治会、2015年
岩波桂二『成城学園 自然のアルバム』岩波桂二、2017年
地域総合計画研究所編『成城のまちつくりを考える』世田谷区砧総合支所街つくり課、1994年
世田谷区みどり33推進担当部みどり政策課編『世田谷・みどりのフィールドミュージアム案内マップ』世田谷区みどり33推進担当部みどり政策課編、2021年
井口勝文『イタリアの小さな町暮らしと風景』水曜社、2021年
法人格成城自治会『成城憲章』2016年改訂および更新登録
法人格成城自治会『成城ビジョン2014』2014年策定