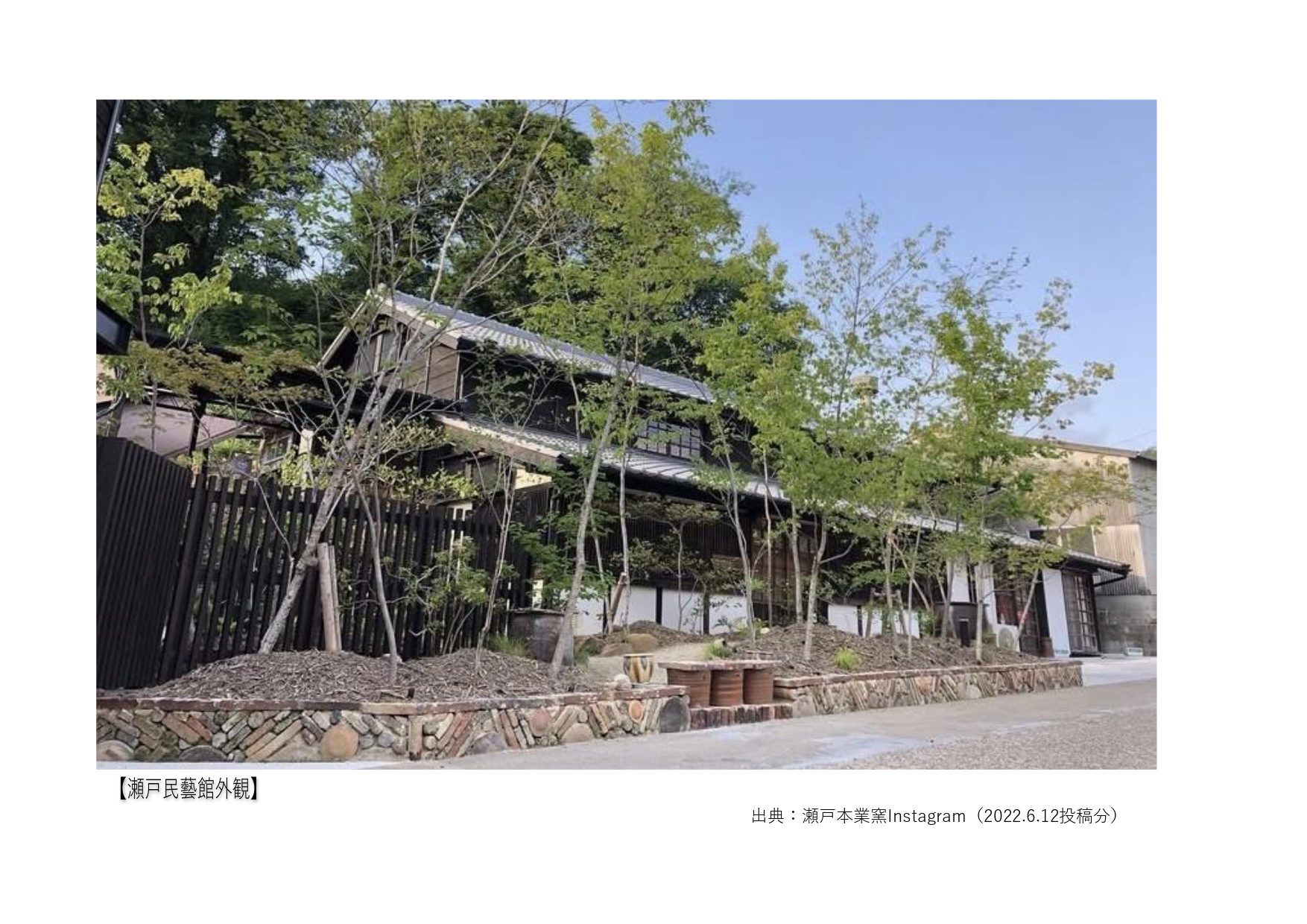中野区神明氷川神社の事例を通じて考える、日本の信仰文化と氷川神社
神道は、キリスト教や仏教のようなシンボルが存在しない一方で、地域の氏神として古くから祀られ、各地に大小ざまざまな神社が存在している。 その中で氷川神社は関東を中心に約280社ほど存在している。氷川神社が多く存在するのはなぜか、身近な氏神様である東京都中野区の神明氷川神社を通じて、日本の伝統的な神道文化と意義について考察する。
1.基本データと歴史的背景
名称:神明氷川神社
所在:東京都中野区弥生町4丁目27番30号 神明氷川神社
神明氷川神社は、文明元年(室町時代)に太田道灌が、武蔵大宮氷川神社より招き入れた神様である。神社が所在する地域は、旧雑色(ぞうしき)村を守るための神社で、明治7年4月に旧社格は村社に認定された。
当該社は神明社が、神田川の畔(あぜ)から移転して氷川神社と合祀(ごうし)され神明氷川神社となった。 主祭神として、素盞鳴命(すさのおのみこと)櫛稲田姫命(くしなだひめのみこと)大日孁命(おおひるめのみこと)事代主神(ことしろぬしのかみ)大山祗神(おおやまつみのかみ)が祀られている。
神明氷川神社のある弥生町は、もともとは純農村地域で江戸時代には約40軒100人が百姓をしており、雑色村(ぞうしきむら)と呼ばれていた。雑色という言葉は、平安時代に設けられた役所で様々な雑役に由来しており、中野区における雑色村の由来は、近くの大宮八幡宮を建てる際に様々な雑務を行っていた事から雑色村となったと言われている。
また、弥生町という名前は、昔の村から町へ移行をしていく中で弥生土器が発見された経緯から”弥生町”と名がついた。 (資料6)
2.評価している点
日本人の信仰と氷川神社の関係
氷川神社と検索すると身近に複数の氷川神社があるのが分かる。(資料1.1) なぜ氷川神社が多数存在しているのか、そのルーツ、日本人の信仰と身近な氏神様である神明氷川神社を考察する。
氷川神社の総本山は。埼玉県さいたま市にある大宮武蔵一宮氷川神社である。 大宮武蔵一宮氷川神社は第5代孝昭天皇の時代に出雲国斐井川上流の”出雲大社”の神霊を分配したのが始まりと言われており、際神は素盞鳴命(すさのおのみこと)櫛稲田姫命(くしなだひめのみこと)大日孁命(おおひるめのみこと)である。(資料4.2) 社名の氷川は「斐井川」から取ったと言われているが、際神を巡っては現在でも不明な点も多い。 奈良時代には人間同様に諸国の神々にも神階とばれる位が設けられ平安時代では武蔵野国で最高位となった。 都から遠く離れた地でありながら有力な中央貴族とのつながりを持たない氷川神がこれほどまでに高位となったのは、後に武蔵野宿禰と称した地方豪族丈氏一族の活躍があった。また氷川神社の本殿は二間社という独特な建築形式が多のも特徴である。 (一般的に神社の建築は一間や三間、五間といった奇数が一般的であり、柱と柱の間が一間と呼ぶ) 埼玉を中心とする氷川神社には二間社が多い。 氷川神社が各地に分祀された時に大宮氷川神社の本殿を真似て二間社が残ったと考えられる。
全国に氷川神社が広まったきっかけは、鶴岡八幡宮に対する年貢減滅を求める農民紛争で中心的な役割を氷河宮が演じ、この時期各地に氷川神社が分祀されたことがきっかけとなった。そして、本殿形式も独特な二間社としていると言われている。 平安時代に中央政治に認められていた神社を記録した「延喜式」神名帳では「氷川神社」は一神であったが、二間社であれば二神いたと想定される。 その後四神へと変化して行ったと考えられる。 現代二間社でないような氷川神社でもかつては二間社であった可能性がある。
また、氷川神社の分布は南北に広く東西にはあまり広がっていないのも特徴である。
こうしてみると氷川神社、地域やそれを必要とする人々自らが地域のための守神として崇めてきたという点で必要に応じて自然に広まった氏神であり、複数の神を祀っていたというのも人々の様々な願いが込められた地域密着方の氏神であると言えるのではないだろうか。
3.他の氷川神社との比較、特筆される点
・他社にはないコンパクトに洗練された社殿の配置
当該神社の境内は決して広いわけではないが多数の木々に囲まれており、鳥居をくぐるとすぐに周りと異なる静かな空間となる。
入口の鳥居は、明治12年9月に建設された花崗岩でできたもので、大正12年の関東大震災で破損し、昭和九年に再建されたものである。 参道から、左手に手水舎(ちょうずや)があり、三光鱗神(さんこうりんしん)、和合の御神徳(ごしんとく)と並ぶ。 その先には平成26年2月、中野区認定観光資源に認定された「百度石」がある。 (百度石を巡るお百度参りは、もとは百日続けて参詣することを指していたが、それがいつしか人目を忍びながら拝殿と石を一日に百往復することに変わったと言われている。) その左先には神楽殿、右側に社務所、絵馬堂(絵馬掛け所)があり、その先に拝殿がある。鳥居を潜ってからの参道は50m程の間にコンパクトに収められている。 拝殿から東向きに一直線に伸びた参道は皇居の方向を向いている。(資料1.2)拝殿の左右には、明治二十四年に奉納された狛犬が鎮座している。本殿の両脇に末社の津島神社、御嶽神社がある。(資料2)
本殿は2000年に鎮座550年の祝年を迎えて、天井・壁・床の補修・改良、照明のLED化、御簾・壁代他御調度品取替、神饌所上下水道設置、バリアフリー化、その他神前の修繕、美化などの工事により災害対策を含め外見も綺麗に生まれ変わっている。 尚本殿の構造は一間社である。
・四季の風景と氏子との密接な関わり
境内の木々が季節ごとの木々の色とりどりの変化とともに、季節毎の行事では、神明氷川神社専属の中野弥生町のお囃子(弥生ばやし連)が、行事をサポートする。(資料3,資料4.1)
また、2021年コロナ禍においては地元中野富士見町出身のDJ神山清豪氏によるシンセサイザーによる奉納演奏をYutubeで配信するなど地域に密着した新しい取り組みも取り入れている。
・社名の特徴
神明氷川神社は、神明神社と氷川神社を合祀した名前である。神明神社は天照大御神を主祭神とし、伊勢神宮内宮(三重県伊勢市)を総本社とする神社であり皇室の祖神、国家鎮護の神であり、一方、氷川神社の総本山は、大宮にある武蔵一宮 氷川神社であが、大国主命を主祭神とし生産力子孫繁栄 旺盛な農業神とする”出雲大社”の神霊を分祀したのが始まりだと言われている。この2大神を主祭神とした神社が合祀した神明氷川神社はとても貴重な社名である。(資料5)
このように神明氷川神社は都会の中心にありながら、必要な物が機能的に配置されており、周囲を緑で囲まれた都会ならではの地域密着型神社である。
4.今後の展望について
当該神社では、氷川会という催しを不定期で行なっており、お供えした食べ物を境内で焼き氏子と親睦を測るバーベキューのような催しを30年続けてきたが、一区切りして現在は次なる行事を検討中である。
お囃子には小さな子供も参加しているが、全体的には高齢化しており、昔の若者組のような仕組みが無くなった現代、今後どのように若い人を取り込んでいくかが課題となっている。 一方で、拝観社の人数は少しづつ増える傾向にあるが、特に観光プロモーションなどはしていないため今後は検討の余地はある。
現実的な問題としては敷地面積の割に大木があり、それが貴重な空間となっているが、反面それを維持するためのコストの負担が非常に大きい。
さらに、今後は中野区とも連携して災害時の対策を強化し、現在まで行なってきた耐震工事や災害に備えて備蓄しているコンロや浄水装置をいざという時に活用できるように、地域と連携を進めていく予定である。
5.まとめ
近年AI技術により、膨大なデータから様々な予測やクリエイティブな作業までもがコンピュータにより自動的に生成される時代になっている。 一方で、古来より脈々と続く”願い”はデータには蓄積されずに、それぞれの場所に時代とともに刻まれている。 日本人の多くの人が、人生の節目や願い事があると神社に出向き祈る。その願いにはAIでは計り知れない無限の思いが込められている。 今回、神明氷川神社という身近な氏神の考察を通じ、氷川神社の由来や日本人の信仰についての理解が深まった。 AIでは測りきれない日本人の心の文化・歴史を繋いでいくために、身近な氏神である神明氷川神社は貴重な文化資産の一つであると考える。
参考文献
出典:
参考URL:
大祭奉納演奏【栗花落きき】神明氷川神社 2022年10月
https://www.youtube.com/watch?v=_FC1C80aL8c
神明氷川神社公式サイト http://shinmei-hikawa-g.org/
神明氷川神社公式サイト お知らせ 瓦版第2号/社殿改修工事が始まりました。
http://shinmei-hikawa-g.org/gyoji/kawaraban201906.html
節分祭(せつぶんさい)を行いました。 http://shinmei-hikawa-g.org/gyoji/setuben.html
参考文献:
・著者:野尻靖、『大宮氷川神社と氷川女體神社 その歴史と文化』、
2020年4月 発行:株式会社 埼玉出版社会 著者:野尻靖
・著者:三橋 健、『神社の由来がわかる小事典』 2007年7月、 発行所 PHP研究所 発行者:江口克彦
・編集者 小森 正明:『神明氷川神社略誌 雑色村とともに』、 令和2年2月、発行者:宗教法人 神明氷川神社 宮司 眞壁 恵龍 編集者 発行所 神明木川神社社務所
・『中野文化財no.23 中野区の石像物 (神社)』、発行:平成9年3月31日、編集 発行:中野区教育委員会
・『常設展示図鑑 武蔵野における中野の風土と人びとのくらし』、令和3年(2021)3月16日 発行、編集・発行 中野区、山崎記念 中野区立歴史民俗資料館 企画・制作 株式会社 丹青社
取材ご協力:神明氷川神社 宮司 眞壁 恵龍 氏
現地取材による出典:中野区立歴史民俗資料館