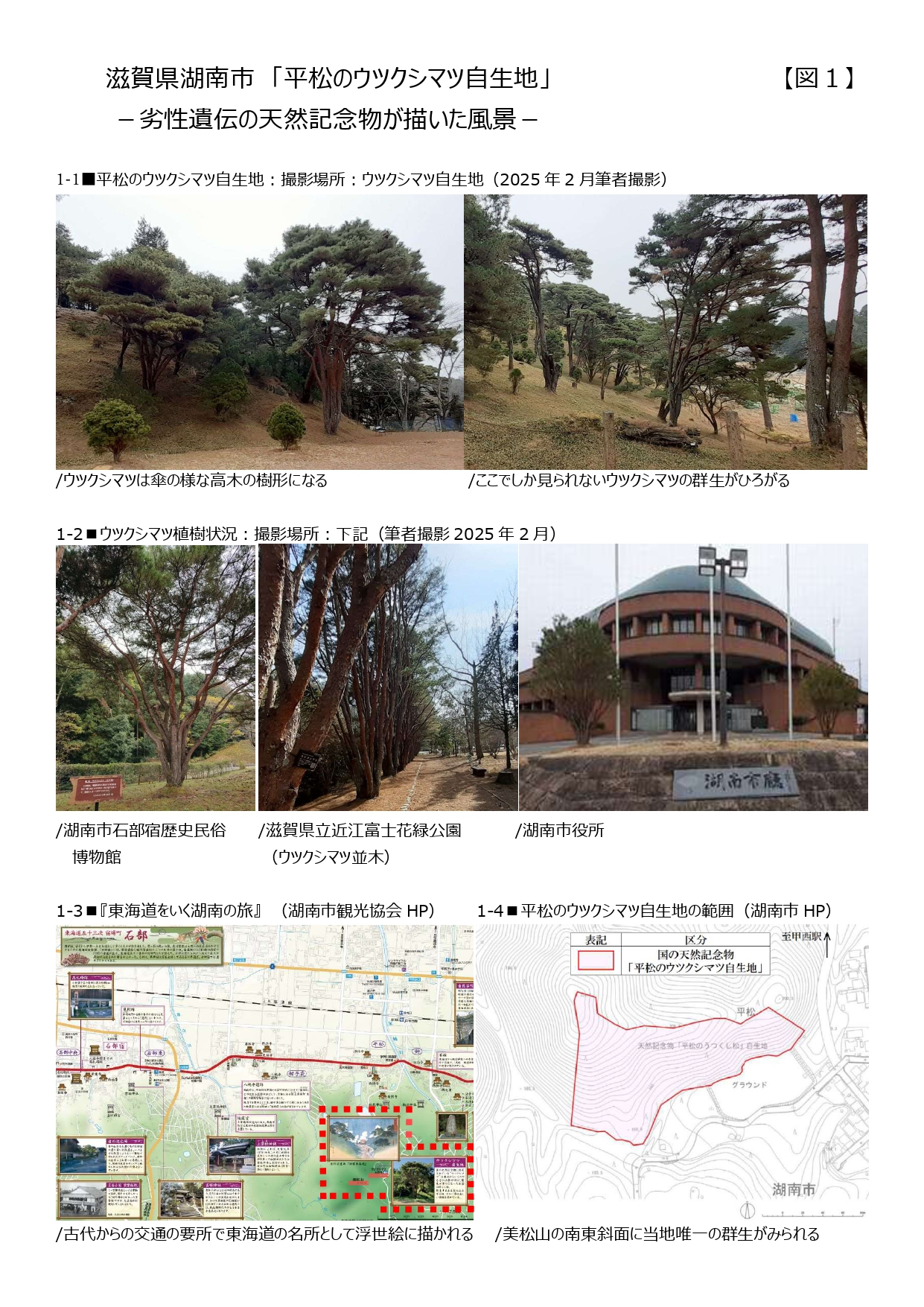再興湖東焼
「再興湖東焼」は、2006(平成18)年に滋賀県伝統的工芸品(註1)に認定された近江の焼き物である。最初の湖東焼は、江戸時代後期の1829(文政12)年に彦根城下の商人絹屋半兵衛らにより始められ、井伊直亮・直弼・直憲の3藩主の時代に彦根藩の藩窯として栄えた。この間、白く堅く焼き締まった磁器を中心に、染付・金襴手・赤絵・青磁などの細やかで美しい焼物を世に送り出していた。しかし1895(明治28)年に閉窯となったため、工芸品として美術的価値の高さと希少性から「幻の名窯」とされている。
1986(昭和61)年、信楽出身の陶芸家「中川一志郎」氏 は湖東焼の絵付に魅了され再興を目指して築窯した。現存する作品や文書をもとに研究作陶を重ね、技術の伝承を実践している活動を、以下に考察する。
1. 基本データ 再興湖東焼 彦根『一志郎窯』
ギャラリーは、滋賀県彦根市本町一丁目6-22
窯場は芹川工房、彦根市芹橋二丁目2-31
棟梁「中川一志郎」氏、息子の「中川和夢」氏と弟子で活動中
2. 事例の何について積極的に評価しようとしているのか。
「中川一志郎」氏は京都陶芸技術専門学校卒業後、遠州七窯の膳所焼で修行し茶陶を学び、兄「中川一辺陶」氏の雲井窯で信楽独特の土鍋の修行をする。中川氏は信楽の陶芸一家に生まれ、祖母、母は共に彦根出身という縁もあり彦根で築窯した。焼き物の成形、絵付、焼成に関わる工程を分業化せず一人で行っている。その姿勢は湖東焼の忠実な再現を模索する職人気質とともに、現代に合致したアレンジを施した創作活動も展開している。作品には例えば井伊の武者装束を思わせる「赤漆色」の茶器や、江戸末期では実現できなかった下色絵付け(背景色)との掛け合せなど、職人と作家の両立したバランス感覚を持合せた活動をしているのである。
3.歴史的背景は何か。
(1)民窯期-絹屋窯
「湖東焼と『藍色のベンチャー』」(註2)によると、江戸末期、染付磁器は当時の最先端産業であり、彦根の船町で呉服の古着商を営んでいた絹屋半兵衛は、仕事で京都へ出向いた際に、清水や五條坂で見かけた京焼に興味を覚えたとしている。当時の文人趣味の流行や、庶民が煎茶を飲むようになる時代背景から、伊万里、瀬戸の後発でも普及品には市場参入の余地があるとの判断から窯を起こすことを決意したと考えられている。
『湖東焼の研究』(註3)の総説では、彦根藩三十五万石の地理的条件として、琵琶湖の湖上交通は塩津と大津間の物流が盛んで、道は東は中山道に西は京大坂に通じており、湖東一帯は近江の沃野に選りて四通八達の地であるにも関わらず、殖産の道がなかった消費地どまりであった。天下に名乗って出られる「浜縮緬」や「蚊帳麻布」のごときものも作られず、且つ近江商人の特色とする天秤棒を担いで六十余州を行脚する様な胆力がある商業家も輩出しなかったとしている。
そのなかで絹屋半兵衛は、近江商人の経営手法である共同出資者を募って新規事業を起こす「乗合商い」を原資としてリスクマネジメントを図りつつ、古着商いの買い付けに「産物廻し」と呼ばれる、産地彦根と販売先での往復商法を思いついたのである。当初は有田の職人を雇い、窯場を芹川右岸の晒山、その後佐和山山麓の餅木谷に築いた(写真1)。素地には天草陶石を用い、日常品、高級品の双方を見据えて焼成したが、知名度が低いために「湖東」銘が無い作品の方が評価される憂き目であった。その後藩から二度に渡る金貸与ののち、1842(天保13)年窯場は藩への召し上げとなる。
(2)藩窯の時代(写真2,3,4)
1923(大正12)年、当時を生きた証人がいる時代「湖東焼の研究(註3)」のはしがきを書いた大河内正敏は、湖東焼を「技工の最も洗練された徳川末期の藝術を代表するものとして当時の藩窯中に双ぶものはない」と評価している。絹屋から召上げた井伊直亮は雅楽器収集などの道具好きであり、大老職、京都守護職の立場上、多くの朝廷や大名との交際に用いる「献上品」に湖東焼を用いる意図があった。この時期から高級品志向が盛んになり、絵付師の幸斎などの名工を迎える。そして井伊直弼時代になると「埋木舎」で楽焼を通じて焼き物に精通した「直弼好み」を実現するために、各地から優れた職人を招聘し、棟梁においては美濃から「寺尾市四郎」を五人扶持の待遇で迎え体制強化を図り、子供見習いを含めて職人は50名を数えるほどとなった。材料にもこだわり上質の唐呉須を用いて「湖東銘」の統一ブランドを徹底させた。流通では京都・大坂に売捌所を設け、手船を建造して江戸の大市場へ進出を目指したのである。
(3)民窯への払下げ
1860(安政7)年、桜田門外の変が起こり世情不安となり職人は四散した。直弼の窯業育成の熱心さから親しく現場に望み、自らも作図をして見せ、職人を励まして奮起させた自慢の人が突然いなくなった(註4)。1862(文久2)年、攘夷派の岡本半介による開国派を粛清するクーデターによって行き場を失った職人たちは失望の末、湖東の窯場を去ったのである。後には、彦根出身の山口喜平ら4人で細々と続けられ、長浜湖東、円山湖東など復興を企画したが成功を見ず1895(明治28)年に閉窯となった。
職人の中には、湖東焼の知見を継承したとされる人がいる。市四郎が瀬戸から呼び寄せた「幹山伝七」は、京焼に移った後ドイツから招いたワグネルと出会い西洋絵具を用いた陶業を繁栄させた。
(4)再興の時代
1986(昭和61)年に彦根の有志が「湖東焼復興推進協議会(現、NPO法人.湖東焼を育てる会)を発足させた。当時の地場産業は、武具、武器の製作にたずさわっていた塗師、指物師、錺金具師などが平和産業としての仏壇製造に転向したとされる伝統的工芸品指定の「彦根仏壇」、バルブ工業、縫製加工であった。しかし高度成長期以降の販売の低迷や生活様式の変化を機に、地場産業の多角化を模索する中で陶芸ブームを背景に再興を果たした。
4: 国内外の他の同様の事例に比べて何が特筆されるのか。
信楽焼振興協議会(註5)によると「信楽とは形になるものは何でもつくるたくましい産地である」としている。同じく信楽出身で、遠縁の近江科学陶器(現.大塚オーミ陶業)に入社し、岡本太郎のアシスタントとして、太陽の塔の「黒い太陽」の制作に携わった人に「小嶋太郎(1940-)」がいる。1970(昭和45)年、大阪万博の後に独立し、渡来人より伝えられたとされる緑彩陶器の産地として栄えた山麓に布引窯を開いた。最初は掘建て小屋からスタートするもヒッピーたちが集まる楽しい場所であったと懐古している。数多くの陶板レリーフを手がけつつも、独創的な作品を生出し「七彩天目」と名付けた変釉の世界観を織りなしている(写真7,8)。小嶋太郎の作陶一家4人が表現する「梟」は単なる縁起物に留まらない。本物の梟に触れた経験を元に、人の知恵を集めたとする梟の境地「ミネルバの梟」を表現しているのである。方や湖東焼の中川一志郎は、書道にも精通し甲斐玲子との交流を深めるとともに彦根城の朱印帳の題字も務めているなど、書画一体となった人間味ある染付けや赤絵に精通している(写真5,6)。
5: 今後の展望について。
布引焼で修行した唐橋焼の若山義和は、焼き物には「時代に沿った需要があり、材料が調達でき、後継者のいることが要件である」と述べている(註6)。清水焼の近藤高弘氏(写真8)のようにオーナーを持ち作陶に集中できる環境は望まれるが、直弼が江戸の市場拡大を目指したように、2017年オープンの東京日本橋「ここ滋賀」を拠点とした活動は顧客獲得の機会となる。最後に、炊飯土鍋のような一点特化した非凡さがあれば、焼き物で生計を立てにくい時代であっても、未来の作陶に期待できると思われる。
-
 図1.絹屋半兵衛が築いた窯
図1.絹屋半兵衛が築いた窯
右上:現存する絹屋の家屋、彦根市元町2-16(2017/12/22著者撮影)
右中:佐和山山麓の餅木谷に窯を築いた跡、彦根市古沢町(2017/12/22著者撮影)(非公開)
右下:窯跡には山の斜面に沿って、登り窯跡がある(2017/12/22著者撮影)(非公開)
左:「江州彦根城」山水図大皿(1831年)たねや美濠美術館(2017/11/26著者撮影)(非公開) -
 図2.彦根城下
図2.彦根城下
右上:玄宮園からみた彦根城天守閣(2016/5/1著者撮影)
右下:彦根城博物館、湖東焼が収蔵展示されている
左上:井伊直弼が青春時代を過ごした「埋木の舎」彦根市尾末町1-11
左下:井伊家の菩提寺である「清涼寺」井伊直弼は生前、戒名を定め肖像画に歌を添えて納めている 彦根市古沢町1100(上記3点はいずれも2017/12/22著者撮影)
-
図3.彦根城博物館に展示の湖東焼 (非公開)
右上:赤絵虎渓三笑図六角徳利、床山玉洸作。当時の先進国中国の故事、仙人を描いている。また湖東焼の人物はおしなべて全身である。武家のためか上半身だけを描いた姿(腹切り)は見当たらない。(2016/5/1著者撮影)
右下:赤絵金彩鳳凰文酒盃、賢友作(以下全て、2017/12/22著者撮影)
下中:染付鳳凰図大鉢
左下:青磁牡丹文耳付花生
左上:色絵牡丹図鉢
上中:染付波文舟形盃洗 -
 図4.豊会館[又十屋敷]滋賀県犬上郡豊郷町下枝56(2017/12/24著者撮影)
図4.豊会館[又十屋敷]滋賀県犬上郡豊郷町下枝56(2017/12/24著者撮影)
江戸後期に生まれた藤野喜兵衛は北海道に渡り漁場を開き廻船業者として活躍する。天保飢饉時には庶民救済の一作[飢餓普請]により「松前の庭」を作庭した。彦根藩は湖東焼の藩窯の経営を1852(嘉永5)年から2年間、販路拡大を目論んで藤野四郎兵衛に委託した関係にある。 -
 図5.再興湖東焼窯元 http://www.kotouyaki.jp
図5.再興湖東焼窯元 http://www.kotouyaki.jp
左:ギャラリー、暖簾は「甲斐玲子」書
右:芹川工房(いずれも2017/12/9著者撮影) -
 図6.再興湖東焼作品
図6.再興湖東焼作品
上段:蕎麦猪口 図柄には近江八景のニーズは高い、本品は「比良の暮雪」を描いている
青みがかった白地は湖東焼の特徴であり、例えば鉄瓶に白垢が出来るほどの、鉄分を含む地下水で作る釉薬のためとされている
右上:湖東の銘が入っている。釉薬を削り取ったところを「蛇の目」と呼び、長く風合いを楽める仕掛けとなっている。
下段:ギャラリーのショーケースより(いずれも2018/1/13著者撮影) -
 図7.琵琶湖東岸の陶器の産地
図7.琵琶湖東岸の陶器の産地
右上:蒲生野は西方から、鏡山、雪野山、布引山、百済寺へ直線に連なっている(著者作成)
右下:緑釉陶器の窯跡(東近江市土器町)名神高速道路建設時に黒丸PA周辺から多く出土した(2017/12/24著者撮影)
下中:百済寺から西方の蒲生野を望むと、山並みが連なる(2017/12/2著者撮影)
左下:太陽の塔の黒い太陽 お祭り広場について、岡本太郎は「新しく独立し、歩み始めたばかりのアジア・アフリカの諸国の存在感をふくれあがらせ、祭にとけ込ませる、人間的な誇りの場でなければならない」とした。小嶋太郎は「芸術はきれいであってはいけない」ことを学んだのである(2017/7/22撮影)
左上:布引山にある石塔寺の三重の塔。白州正子は朝鮮にある塔とは違いがあり日本の美術品であるとしている(2016/7/31著者撮影)
上中: 鏡神社宝篋印塔 塔身の四隅にはふくろうが彫られている。鏡神社は新羅から渡来文化を伝えた天日槍(あめのひぼこ)を祀り、陶人を招聘したとある。また近隣の竜王町には「須恵」という在所が現存している(2017/12/2著者撮影) -
 図8.清水焼と布引焼
図8.清水焼と布引焼
上段:近藤悠三記念館 http://ryusui.co.jp
上右:全景 京都市東山区清水一丁目287(以下、2018/1/26著者撮影)
上中:近藤悠三作 柳染付壷、1965年
上左:近藤高弘作 「波」銀滴碗、2016年
下段:布引焼窯元 東近江市外町 http://www.nunobikiyaki.jp
右下:「ここ滋賀」が入る建物(東京都中央区日本橋)(2018/1/19著者撮影)
https://cocoshiga.jp
下中:東京都豊島区役所3階の総合フロア(東京都豊島区南池袋)
小嶋一浩作「梟のレリーフ」(2017/11/30著者撮影)
http://www.city.toshima.lg.jp/artculture/brand/fukuro/machi.html
左中下:彦根城と竹生島を眺める桜の絵皿(2017/11/11著者撮影)
左上:桜の図柄の湯呑みと、金魚の図柄の箸置(2017/11/11著者撮影)
参考文献
註1.滋賀県商工観光労働部中小企業支援課編『滋賀の伝統的工芸品』2015年
註2.天谷真彰著『湖東焼と『藍色のベンチャー』CiNii論文、2004年
註3.北村壽四郎著『湖東焼の研究』国立国会図書館デジタルコレクション、1925年
註4.小倉栄一郎著『湖東焼廃窯事情』CiNii論文、1986年
註5.信楽焼振興協議会編『岡本太郎、信楽へ』サンライズ出版、2015年
註6.京都新聞社編『京都滋賀 窯元めぐり ー和食器を求めてー』京都新聞社、1998年
【参考文献】
湖東焼
幸田真音著『あきんど 絹屋半兵衛』文春文庫、2009年
湖東焼復興推進協議会編『幻の名窯 湖東焼 改訂版』サンライズ出版、2008年
彦根城博物館編『一期一会の世界 大名茶人 井伊直弼のすべて』彦根城博物館、2015年
布引焼
平野暁臣編『岡本太郎と太陽の塔』小学館クリエイティブ、2008年
平野敏三著『信楽・伊賀 日本のやきもの7』淡交社、1986年
近江と焼き物
白州正子著『近江山河抄』講談社、1994年
滋賀県立琵琶湖文化館編『近江文化叢書9 近江のやきもの』サンブライト、1981年
滋賀県立陶芸の森編『近江やきものがたり』京都新聞出版センター、2007年
末永國紀著『近江商人学入門』サンライズ出版、2017年
愛知県陶磁資料館、五島美術館編『日本の三彩と緑釉』五島美術館、1998年