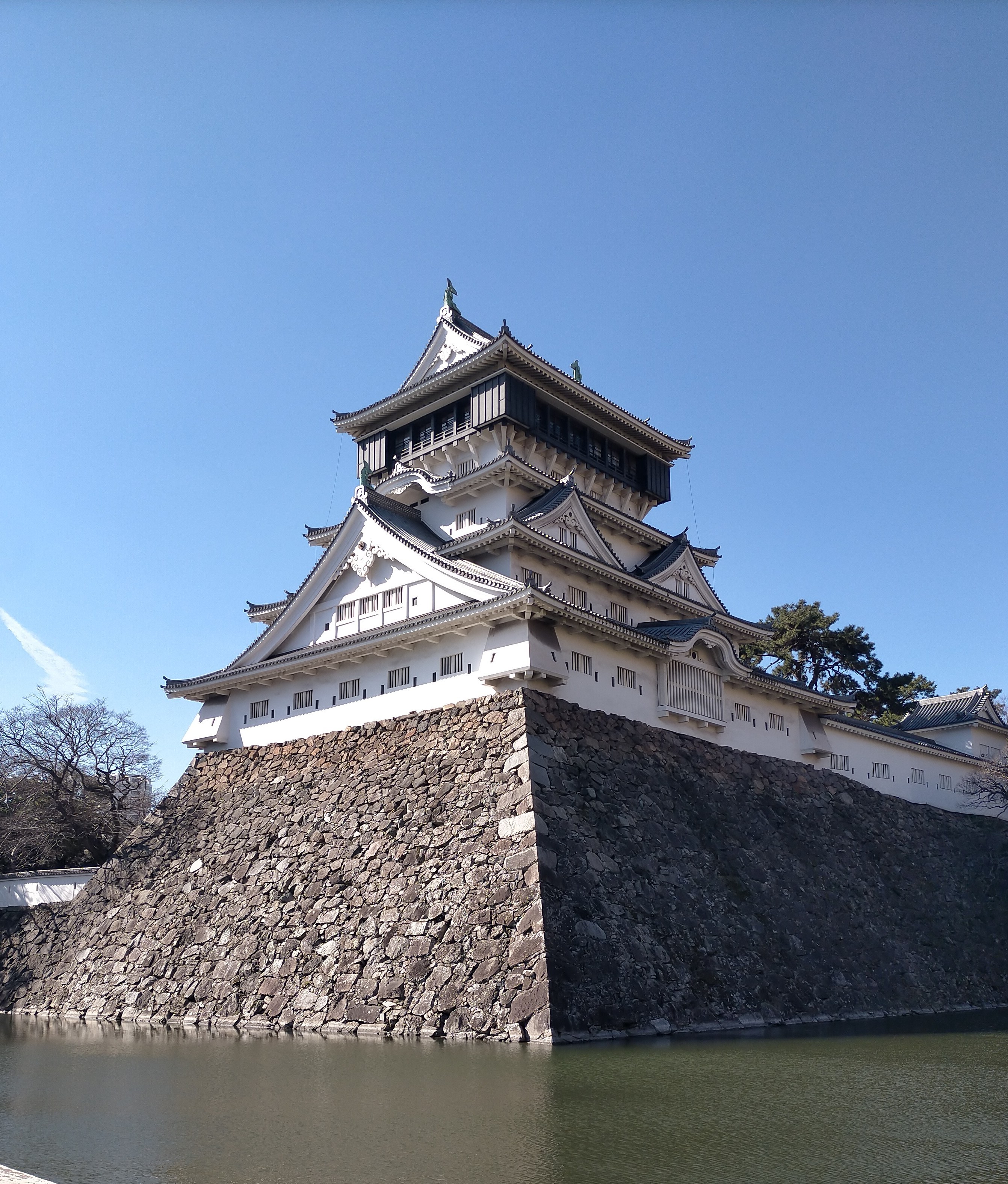宗像大社秋季大祭「みあれ祭」とそれを支え守る漁師たち
はじめに
毎年見るたびに圧倒され感銘を受ける祭りがある。福岡県宗像市にある宗像大社の海上神幸「みあれ祭」である。この祭の伝統を守り斎行する漁師と三女神の関わりを評価・考察する。
1. 基本データと歴史的背景
宗像大社には天照大神の御子神である三女神(1)が航海・交通安全の守護神として祀られている。毎年10月1日に三女神が集結することで新たな若々しい強い力が授かるという宗像大社秋季大祭が行われ、その幕開けが「みあれ祭」である。
宗像は日本における最初の国際港で朝鮮半島やアジア諸国に最も近い位置にあった。玄界灘の波は荒く命を失うことの多い航海は高度な航海技術を持った宗像海人族の協力が不可欠であった。玄界灘の交通の要衝で航海の道標である沖ノ島は島全体が御神体として沖津宮に田心姫神が祀られており4世紀から9世紀末まで「国家的祭祀」として航海の安全と交易の成就を祈願し祭祀が行われていた。今も残されている多くの国宝が沖ノ島の重要性を裏付ける。
その三女神の祭り「みあれ祭」の起源は鎌倉時代からとされる。宗像大社の古文書「正平年中行事」(1350)に春夏秋冬の年4回、御長手神事(みながてしんじ)(2)として沖ノ島から神霊を運ぶ船が神湊(こうのみなと)に着いていたことが記されている(3)。
沖津宮と中津宮の二女神(4)各々の神輿を乗せた御座船を守りながら大島から神湊まで数百隻の漁船が疾走する勇壮な漁師たちによる神迎えの神事である。
2.「みあれ祭」を積極的に評価できる点
宗像大社は古事記や日本書紀、日本神話にも登場する連綿と続いてきた歴史を持つ日本最古の神社の一つである。
宗像大社は実は1ヶ所ではない。九州本土の辺津宮から海を隔てて8㎞沖の大島・中津宮とさらに玄界灘沖の60㎞にある沖ノ島・沖津宮との三つの異なる信仰の場と三女神を合わせて1つの宗像大社なのである(5)。この三宮は一直線上に並んでおり延長線上には朝鮮半島がある。[資料1]
「みあれ祭」は戦中から戦後にかけて宗像神社復興運動の活動として権現司小野迪夫の尽力により中世に行われた御長手神事を再興し、古儀(6)に則って1962年から斎行された大島及び宗像七浦(7)の漁民が参加する挙郡一致の祭りとなった。
各漁協からは「われわれの海の御神様のお祭りなら何を措いても御奉仕させて貰わにゃ」(8)
との声が上がり、門司・福岡海上保安部も快諾したという(9)。
9月中旬に神職が沖ノ島に渡り沖津宮から田心姫神の神璽(10)を大島に渡す「沖津宮御神璽迎え」が行われ、「みあれ祭」の前日まで大島・中津宮にて毎日日供祭の神事が行われる。10月1日に神輿に乗り大島の小学生の鼓笛隊を先頭に港まで陸上神幸される。神輿を担ぐのは大島の漁師や中学生たちだが、若者の減少のため私が度々話を聞く宗像漁協の中川氏もかりだされるという。担ぎ手の黄色の装束は婦人会の方が準備し着せてくれるなど地域や大島の島民も支えている。
神職が祝詞を奏上しながら進む先導船を先頭に、二女神の神輿を乗せ「国家鎮護宗像大社」の大幟を立てた各々の御座船を数百隻の漁船が大船団で守りながら疾走する。この景色を宗像本土の至る海岸でワクワクしながら多くの観客が見守っている。[資料2]
花火を合図に大島から船のエンジン音が轟き紅白の御長手の大幡や大漁旗を翻し現れる船団の姿は体が震えるほどの感動を与える。神湊の直前で供奉船は御座船を中心に右旋回し豊漁と安全を祈願し御座船にお賽銭を投げ入れ手を合わせて各港へ帰っていく。その様子は海を生業にする人たちの祈りに包まれている。[資料3]
「みあれ祭」は漁民が中心となって行う祭りである。なぜなら古代から小さな船で何の機器もなく経験と勘だけを頼りにこの荒波の玄界灘を命を懸けて航海をしてきた宗像海人族の末裔たちが行っているのだ。海に一度出ると命がけの仕事である。命がけだから心より神に祈るようになり、それが信仰となったのだ。
玄界灘の沖には奇跡のように沖ノ島が浮かんでいる。ここは航海や漁の目印にもなっており海が荒れると避難港になり停泊できる貴重な場所である(11)。
「みあれ祭」は歴史ある大きなお祭りだが商工会や市が行う町おこしイベントではなく、毎日命の危機にさらされている漁民により無事を感謝しこれからの安全を願って斎行する心からの神事であることを評価する。
3.「塩竈みなと祭」と比較し「みあれ祭」に特筆されるもの
全国でも神興海上渡御を行う祭りがあり、その一つが宮城県の「塩竈みなと祭」である。
戦後の疲弊した市民の元気回復を願って1948年に始まった。志波彦神社・鹽竈神社の2基の神輿をのせた御座船「龍鳳丸」「鳳凰丸」が約100隻の供奉船と共に松島湾を巡幸する(12)。[資料4]
当初は7月10日に行われた祭は1963年に8月5日に、2005年に「海の日」に変更されている。1964年から志波彦神社の神輿と御座船「龍鳳丸」が海上渡御に加わり、陸上パレードや花火大会、婦人会による「ハットセ節」、3000人の市民が踊る「よしこの鹽竈」など新しく唄と踊りが加わって盛大に行われるようになった。観客を呼び込み祭りを盛り上げることがメインとなり市民誰もが参加できる祭りである。
一方「みあれ祭」は1963年から現在まで一貫して10月1日に斎行されている。観客の有無には関せず雨が降ってもコロナ禍でも漁船と観客は制限されたが神興渡御は行われていた(13)。
この祭りは集客のための露店や派手なイベントなどの催しはなく、観客はただひたすら海岸で女神様の渡御の神事を見守ることに徹している。
柳田国男は、「祭礼」と「祭」は違い、「祭礼は祭りの一種特に美しく華やかで楽しみの多いもの、見物客が集まって来るもの」また「祭は神と一定の条件を具えた奉仕者との間だけで行われるもの」と定義している。(14)。このことから集客を目的とする「塩竈みなと祭」は「祭礼」であり、三女神と漁師の間で行われる「みあれ祭」は「祭」という相違点がある(15)。
また島全体を御神体とし60㎞の広範囲におよぶ海を隔てた島からなる信仰の場は特筆すべき事例であり、そこで漁を生業とする漁師たちが自らの意志で無償で船を出して行う祭りは他に例を見ない。「神事だからお金をもらって参加は良くない気がする」と中川氏はいう。
4.今後の展望
この祭りは漁師が支えている。宗像海人族の末裔である漁師が居なくなれば「みあれ祭」は途絶えてしまうのだ。
漁師の後継者不足は深刻な問題である(16)。[資料7] 宗像にある「道の駅むなかた」は九州・沖縄の道の駅ランキングで3年連続1位を獲得(17)するほど鮮魚の人気は高い。[資料5-1.2] 漁業の良さをうまくアピールし、子どもの頃から祭りを体験した若者達がその価値を認識し後継者となれば継続に貢献できるのだ。
大島には沖ノ島・沖津宮のための遙拝所が設置されおり、七浦の漁師たちが今までとこれからの安全を祈り続けることで継承していくのである。[資料5-4]
5.まとめ
宗像大社は2017年に世界遺産に登録された。
古代から沖ノ島で国家的祭祀が行われ貴重な宝物(18)が千数百年の間そのまま残されていたのは、沖ノ島の「不言様」(おいわずさま)(19)や「一木一草一石たりとも持ち出さない」という禁忌を住民が今でも神を信じ厳守しているからである。[資料6]
沖ノ島近海は絶好の漁場であり、三女神に守られていると感じるのは、「漁業者としては、大漁だったりすることや毎日無事に帰って来られること」だと中川氏はいう。
海で命の危機に直面し神に祈り助かった経験を持つ漁師は少なくないという(20)。
常に危険と隣り合わせの宗像七浦の漁師たちの信仰は今も篤く、「みあれ祭」は海に生きる人々が本気で行う神事だから観る人の心を打ち、この漁船が創る光景は特異な文化遺産として三か所の信仰の場でこれからも変わることなく漁師たちによって継承されていくのである。
-
 辺津宮・中津宮・沖津宮の配置図
辺津宮・中津宮・沖津宮の配置図
「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 編集・発行 『ハルカムナカタ』 2023年12月 第2版発行 P5参照
大島に設置されている沖ノ島遠望ライブカメラでリアルタイムの様子がうかがえる。 -
 大島の中津宮から神湊へ神輿が渡される。
大島の中津宮から神湊へ神輿が渡される。
2019年・2024年10月1日 筆者撮影 -
 海上神幸を行う漁船の勇壮な海上パレード
海上神幸を行う漁船の勇壮な海上パレード
2024年10月1日 筆者撮影 -
 広報紙は塩竈市役所が作成されている。
広報紙は塩竈市役所が作成されている。
2025年1月9日 塩竈市ホームページより筆者撮影掲載 -
 5-1,5-2,5-3 2025年1月20日 筆者撮影
5-1,5-2,5-3 2025年1月20日 筆者撮影
5-4 2024年8月24日 大島にて筆者撮影 -
 大島の人々は沖ノ島の禁忌を子どもの頃から聞かされているため、守ることは日常の当たり前だと捉えている。 2024年8月24日 大島交流館にて筆者撮影
大島の人々は沖ノ島の禁忌を子どもの頃から聞かされているため、守ることは日常の当たり前だと捉えている。 2024年8月24日 大島交流館にて筆者撮影 -
 地域活性化にむけて大島での取り組みがなされているが人口は減少傾向である。
地域活性化にむけて大島での取り組みがなされているが人口は減少傾向である。
https://www.city.munakata.lg.jp/w050/020/010/010/030/30-2-1.pdf 宗像市公式ホームページ 対象地域の現状 より抜粋掲載 2025年1月28日 筆者作成 -

-
 「みあれ祭」に参加する宗像漁業協同組合の中川氏に度々質問し、メールにていつも即答して頂き感謝している。
「みあれ祭」に参加する宗像漁業協同組合の中川氏に度々質問し、メールにていつも即答して頂き感謝している。
2024年5月17日~2025年1月28日 2025年1月29日 筆者作成
参考文献
註・参考文献
(1)沖ノ島・沖津宮の田心姫神(たごりひめのかみ)、大島・中津宮の湍津姫神(たぎつひめ のかみ)、九州本土田島・辺津宮の市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)の三女神。
(2)御長手とは『宗像大菩薩御縁起』の神功皇后の戦いの時、織幡宮の祭神武内大臣が織り勝利に導いたとされた紅白二流の長旗で、沖ノ島から毎年増減なく成長する不思議の竹をとり紅白の長幡を旗竿に付し宗像大神の象徴として辺津宮に迎えていた。「みあれ祭」では船に立てて行進するシンボル的な幡である。https://www.okinoshima-heritage.jp/files 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産公開講座 第9回 「宗像の信仰と人々の関わり」Ⅵみあれ祭 2025年1月25日最終閲覧
(3)朝日新聞西部本社著『九州のまつり』発行人 久本三多 発行所 葦書房有限会社 昭和58年7月25日初版発行
(4)辺津宮・市杵島姫神の待つ九州本土へ沖ノ島・沖津宮の田心姫神と大島・中津宮の湍津姫神の二女神がお里帰りをされるため、御座船で渡られる。
(5)「ある物体が意志をもって配置されるとき、それらは物体そのものの性質とは異なる次元での効果をもつようになる。軸線という空間手法がそこに存在しているから」川添善行著・早川克美編『空間にこめられた意志をたどる』京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎 2020年9月14日 第二刷発行 P18,19
(6)『正平二十三年宗像宮年中行事』息御嶋(沖ノ島)の項に見る御長手神事のこと。
(7)宗像七浦とは(大島・神湊・地島・鐘崎・勝浦・津屋崎・福間)の漁港の漁師。
(8)宗像大社社務本局発行 『宗像』 月刊誌第21号 みあれ祭計画について。
(9)海洋神事奉賛会の七浦の漁業協同組合また水難救済会、大島の沖・中両宮奉賛会なども中心的な役割を担い支えている。七浦にはそれぞれの氏神があり、その宗像の総社が宗像大社である
新修宗像市史編集委員会『新修宗像市史 祈りとまつり』宗像市発行 令和5年12月1日 発行 P555
(10)神霊をうつし納めた忌竹で作った櫃。沖津宮神璽は沖ノ島の、中津宮神璽は大島の、辺津宮神璽は辺津宮周辺に育成した竹を使う。
https://www.okinoshima-heritage.jp/files/download/topic_blocks/ac5096af-4c59-4eb7-8324-19aaf4687e08/value01/value02 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群公開講座 第9回「宗像の信仰と人々の関わり」 P23 「神璽」 2025年1月25日最終閲覧
(11)宗像漁業協同組合 中川智裕 32歳 2024年12月16日 聞き取り
(12)この神興海上渡御は古来、海の道案内の役割を果たされた鹽竈神社の御祭神、鹽土老翁神(しおつちおぢのかみ)を年に一度海にお連れする氏子たちによる感謝祭である。
https://kankoubussan.shiogama.miyagi.jp 塩竈市観光物産協会「塩竈みなと祭」 2025年1月22日最終閲覧
(13)世界遺産ガイダンス施設 海の道むなかた館 宗像市地域学芸員 M氏より聞き取り調査
https://munakata-taisha.or.jp/archives/238 宗像大社公式ホームページ 秋季大祭(みあれ祭)についてのお知らせ 2025年1月22日最終閲覧
(14)柳田国男著『日本の祭』角川ソフィア文庫 平成25年2月15日 発行 「祭りから祭礼へ」P3/24 P11/24 電子書籍
(15)芸術教養演習1 「みあれ祭とそれを支える漁師たち」 2024年8月 筆者作成
(16)大島の人口は減少を続けている。昭和50年の1,421人から平成27年には609人となり40年間にほぼ6割減となった。 宗像市 https://www.city.munakata.lg.jp/w048/kasokeikaku.pdf 宗像市過疎地域持続的発展計画(大島地域) 2025年1月22日最終閲覧
(17)「道の駅むなかた」の広い売り場半分が朝獲れた新鮮な魚介類の売り場で、平日でも午前中には売り切れてしまう。
「JAF会員の選ぶ!イチオシ道の駅グランプリ2023」で148駅全道の駅で3年連続1位となった。 株式会社共同通信社 https://www.kyodo.co.jp/news/ 「道の駅むなかた」3年連続1位で「殿堂入り」JAF九州本部「イチオシ道の駅グランプリ2023」 2025年1月22日最終閲覧
(18)鉄艇や71枚の三角縁神獣鏡などの銅鏡、古代中国の唐三彩瓶、金銅製龍頭、勾玉、古代ペルシャのカットグラス碗など。 宗像善樹著『史料にみる宗像三女神と沖ノ島傳説』三武義彦 発行 2017年7月3日 第一刷発行
(19)沖ノ島に古代から伝わる「不言様」といい、島で見たもの聞いたことは島の外で話してはならないという禁忌が守られている。島に上がった者は家に帰っても何も言わないので妻や子どもも島のことは何も知らないのである。
(20)「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議『沖ノ島―守り、伝える。―』平成26年4月初版 P11
<参考文献>
・新修宗像市史編集委員会『新修宗像市史 祈りとまつり』宗像市発行 令和5年12月1日 発行
・宗像大社社務本局発行 『宗像』 月刊誌第21号 註2)みあれ祭計画について
・『宗像ふるさと紀行』福岡県宗像警察署内「宗像を知る会」代表 加藤昌隆 発行 平成5年3月1日
・「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議『沖ノ島―守り、伝える。―』平成26年4月初版
・川添善行著・早川克美編『空間にこめられた意志をたどる』京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎 2020年9月14日 第二刷発行 P18,19
・朝日新聞西部本社著『九州のまつり』発行 久本三多 昭和58年7月25日初版発行
・宗像善樹著『史料にみる宗像三女神と沖ノ島傳説』三武義彦 発行 2017年7月3日 第一刷発行
・正木晃著『宗像大社・古代祭祀の原風景』発行者 遠藤絢一 2008年8月30日 第一刷発行
・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 編集・発行『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 世界遺産登録記念誌』福岡県人づくり・県民生活部文化振興課世界遺産室 2019年3月
・「みんなで学ぼう!ふるさと宗像Book」編集委員会『みんなで学ぼう!ふるさと宗像Book』宗像市教育委員会 2018年4月 初版
・『世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 公式ガイドブック』 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 編集・発行 2020年1月初版発行
・外山晴彦監修『日本の神々がわかる 神社事典』 成美堂出版 2013年1月1日発行
・米澤貴紀著『神社の解剖図鑑』 株式会社エクスナレッジ 2016年1月1日 初版第一刷発行
・田中治郎著・山折哲雄監修『学校で教えない教科書 面白いほどよくわかる 日本の神様』 発行者 西沢宗治 株式会社キャップス 平成19年11月30日 第一刷発行
・「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群保存活用協議会 編集・発行 『ハルカムナカタ』 2023年12月 第2版発行
・芸術新潮編集部『神々が見える 神社100選』 発行者 佐藤隆信 株式会社新潮社 2016年12月15日発行
・柳田国男著『日本の祭』角川ソフィア文庫 平成25年2月15日 発行 電子書籍
・https://www/okinoshima-heritage.jp/files/download/topic_blocks/ac5096af-4c59-4eb7-8324-19aaf4687e08/value01/value02 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群公開講座 第9回「宗像の信仰と人々の関わり」 P23 「神璽」 2025年1月25日最終閲覧
・https://kankoubussan.shiogama.miyagi.jp 塩竈市観光物産協会「塩竈みなと祭」 2025年1月22日最終閲覧
・https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/17/32803.html 第77回塩竈みなと祭 - 塩竈市ホームページ 塩竈みなと祭詳細情報[PDFファイル/1.28MB] 23646.pdf 2025年1月22日最終閲覧
・https://www.kyodo.co.jp/news/ 株式会社共同通信社 「道の駅むなかた」3年連続1位で「殿堂入り」JAF九州本部「イチオシ道の駅グランプリ2023」 2025年1月22日閲覧
[聞き取り調査]
・宗像漁業協同組合 中川 智裕 32歳 2024年5月17・23日、2024年12月23日、2025年1月28日
・世界遺産ガイダンス施設 海の道むなかた館 宗像市地域学芸員 M氏 70代 2024年8月7日
・宗像市大島交流館 宗像市地域学芸員 徳広氏 60代 2024年8月24日、2025年1月21日
[資料6] 世界遺産ガイダンス施設 海の道むなかた館 市職員I氏掲載許可を頂いた。
[資料4] 塩竈市役所 秘書広報課広報係 K氏に掲載許可を頂いた。