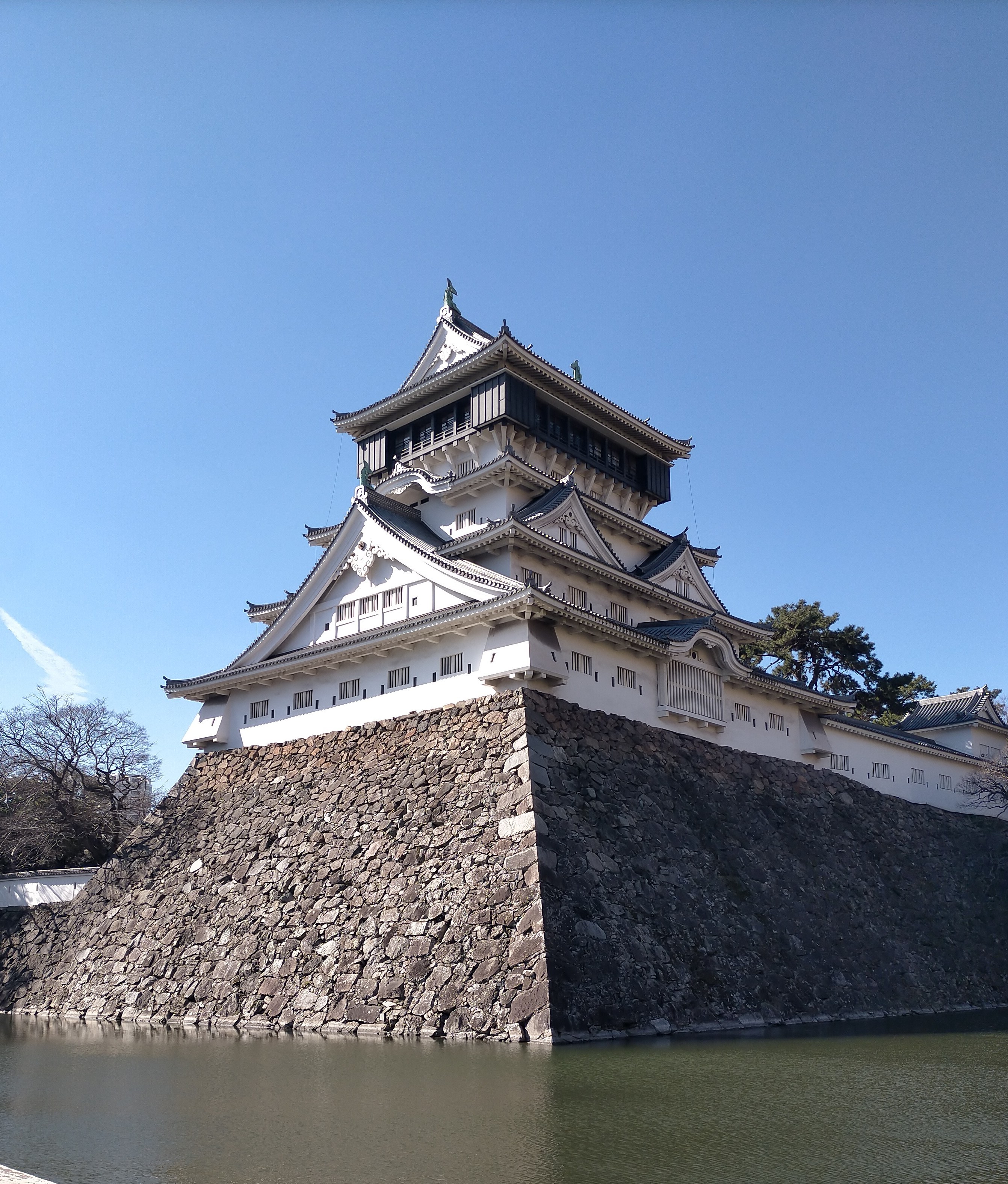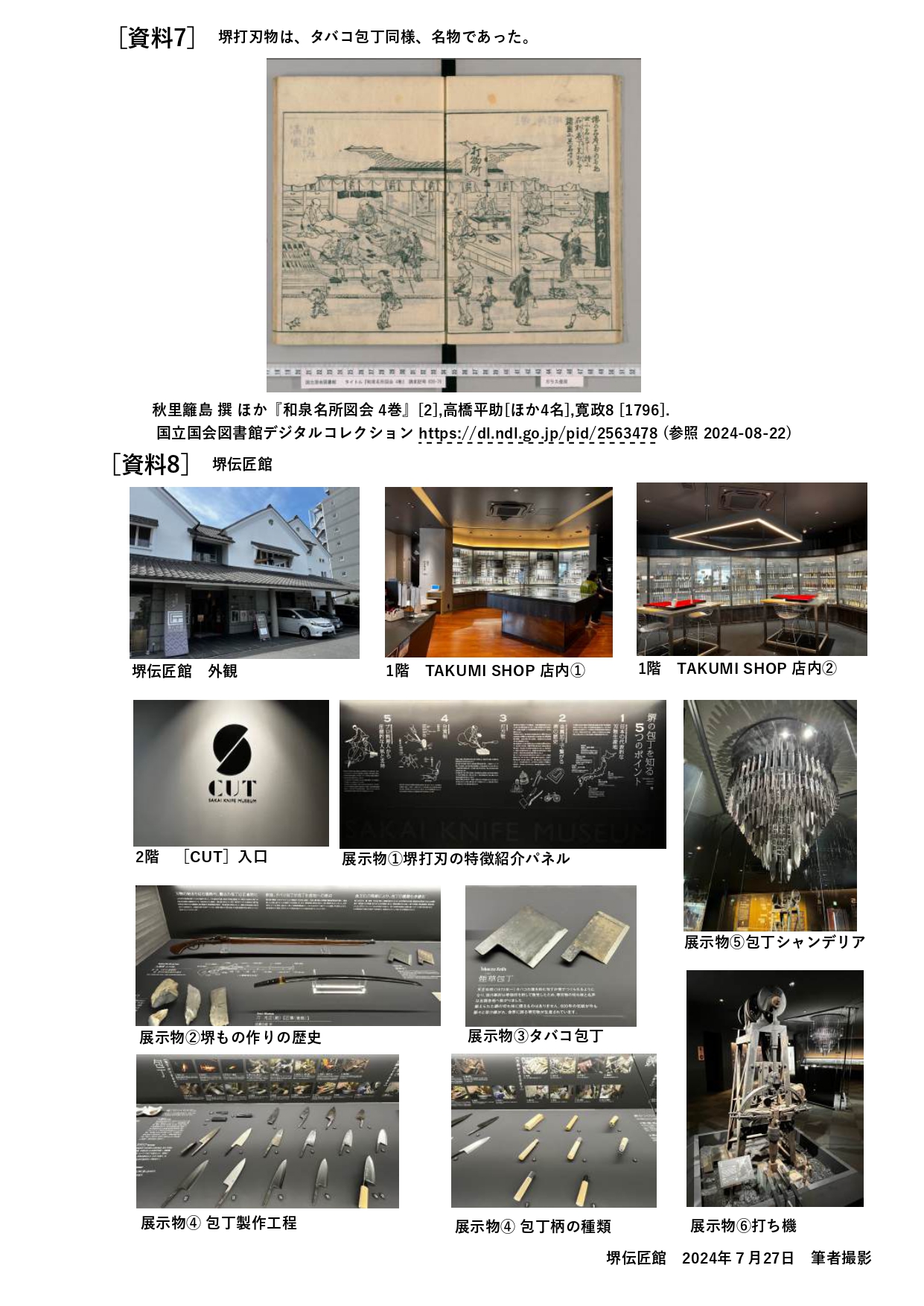大阪切子 〜手磨きできらめくガラスの宝石〜
はじめに
切子と言えば、伝統的工芸品の江戸切子(1)と薩摩切子(2)が広く知られている。大阪にも工房を持ち、切子の制作をする職人がいることはあまり知られていない。本稿では、大阪の切子職人である安田公子(以下安田)(3)を通して大阪切子を文化資産として報告する。
1.基本データ
大阪市天王寺区に大阪切子安田ガラス工房がある。工房を構える安田は、髙橋太久美(以下髙橋)(4)[資料1-1]に師事し、現在、切子職人・作家・講師として活動している。
2.歴史的背景
2-1 大阪におけるガラス製造の基盤と隆盛
ガラス製造は、江戸時代にはすでに日本の各地で行われており、大阪では、1713年には製造が行われていた[資料2]。大阪市北区の地名である天満には、大阪天満宮や造幣局があり、界隈は明治時代にガラス産業の中心地として発展した[資料3]。発展した理由は、1875年に伊藤契信が日本硝子会社[資料1-2]を興し、洋式硝子工場として日本近代ガラス工芸の基盤を作り上げたことである(5)。造幣局が、1885年以後、民間に材料や機械を払い下げたことや(6)、地域を囲むように流れる大川の利便性、都市部の人口増加により生活が変化し、瓶やガラスの需要が増えたことも影響と考えられる(7)。1902年には、日本硝子会社を独立した島田孫市[資料1-3]が、板硝子の製造に初めて成功し、ガラス業界の悲願を達成した(8)。終戦後の1919年には、800以上のガラス関連工場が立ち並び全国の7割近くを占めたが(9)、昭和後期から平成に入ると衰退をした。
以上のように現在は衰退の方向にあるものの、明治維新の大きな流れで創業された官営工場を基としたガラス製造の基盤は、日本の発展とともに人口増加や立地の利便性も相まって、新たな民間の会社の立ち上げや官営工場の払い下げにより発達し、その後社会情勢により幾度も途絶えそうになりながらも継続されてきた。
2-2 大阪の切子制作の始まり
江戸時代後期、輸入されたヨーロッパ製のカットガラスのことを、ダイヤモンドを語源とした「ギヤマン」と呼び、西欧文化の象徴として受け入れられた(10)。
岡泰正によれば、「文化年間(1804〜1818)頃には、まず大坂で和製切子が本格的に試みられたと推定され、大坂、京都、江戸、薩摩、佐賀、福岡、山口などで製作された。これらを和製ギヤマンと呼んでいる」(11)と述べている。
この和製切子が、大阪の切子制作の始まりである。
3.事例のどんな点について積極的に評価しているのか
「大阪切子」は、大阪で制作される切子の総称では無く、大阪に伝わる技法を用いて最後まで手作業で作り上げる切子作品、製品のことである。木盤やコルク等を使った「手磨き」で仕上げることを定義にしている(12)[資料4]。ガラスの色味やデザインに決まりがないため自由度が高く、作家の個性が出しやすいのも特徴の一つである[資料5]。主にロックグラス、タンブラー、盃が多く、鉢、皿、花器、水差しなどが制作される。作家によっては、アクセサリー、照明の傘、ガラスペンの制作もする。
安田の作品は、緻密で繊細なカットが多く、切り込みから生まれた光が輝き、外側からも内側からも視覚を楽しませ驚かせる。ガラスでありながら温かみを感じさせるのも魅力である。大阪切子の技法を受け継ぎながら、作家の持つ現代の感性を個々の作品で巧みに融合してゆく点を積極的に評価する。[資料6-1、 6-2、6-3]
4.薩摩切子との比較による特筆点は何か
国内外で広く知られた薩摩切子は、鹿児島県指定の伝統的工芸品である。薩摩藩当主の島津斉興(1791〜1859)と斉彬(1809〜1858)の尽力により誕生した。独自の研究により発色を成功させた紅色と、「ぼかし」と呼ばれる技術は、薩摩切子を象徴するものだ[資料7]。一度衰退し途絶えたが、1980年代に鹿児島県と株式会社島津興業と、多数の人々の協力のもと伝統文化の見直しが始まり、行政と民間企業が主体となり復活を遂げた(13)。現在は民間企業で生産され、2025年に復元40周年を迎える。誕生と復活のどちらの際にも組織が中心になり、地域の工芸品にすることを念頭にして、一貫して管理運営された事業は、ガラスの製造や切子職人への技術の継承を成功させ、組織として強いブランド力を持っている。
大阪の切子制作は、明治時代に入ると大きな時代の変化の中で繁栄した。切子を大量生産していた時代には、切子屋の中でも、花切子専門、矢来というカット専門、底などの平らな面の加工専門と分かれていたほどであった[資料5]。技術の専門性の高さが窺え、切子職人としての役割が大きかったと考える。
一方で、1903年創業のカメイガラス[資料1-4]は、大阪のテーブルグラスの分野で代表され、工芸美に溢れる製品を発表してきた(14)。髙橋は、かつてカメイガラスで企画された「復刻版薩摩切子」の制作に取り組んだメンバーの一人で、切子歴60年の職人である(15)[資料1-1]。平成に入り、カメイガラスが廃業すると協力工場などが一気に衰退する。その後、髙橋は、技術を繋ぐために工房で門下生を育て始めるが、安田も門下生の一人である。
薩摩切子の運営が組織のトップダウンとするならば、大阪の切子は独立した個々の集まりである。職人として、時に作家として活躍の場を広く持ち、時代の波に対応してきた歴史がある。大阪の切子制作は、歴史上途切れておらず、個人から個人へ技術が継承されており、個々の活躍が見られることが特筆される点である。
5.今後の展望について
5−1 大阪切子保存会の設立と今後の課題
2017年に「大阪切子」を継承する会として大阪切子保存会(16)が設立された。髙橋が会長を務め、関西で工房を持ち10年以上作家・職人活動をしている安田、西川昌美、井住哲司、滝下浩子、たきのさゆり、辻原夕見、松下洋介、近藤隆一、西眞り子の9名が会員として所属している。現在、会員それぞれの高い技術力によって技術は継承され維持されていると言える。各々が工房を持ち、制作活動以外にも、講師、ワークショップ、展示会を開催しているが、大阪切子の知名度は高いと言えず、まずは知ってもらうことが今後の課題である。個々の活躍が大阪切子保存会の活動につながっているが、大阪切子保存会としての活動を増やし、手磨きの技術の良さや、優れた点を伝える場となれば、大阪切子の技術を一斉に見る機会も増え、知名度につながると考える。
5-2 SNSの活用と新たな展望
周知活動が実を結んだ例もある。安田のSNSを見たニューヨークの店舗(17)から声がかかり、海外に販路を広げた。安田は「手作りの良さ、切子の技術、磨きの手法が古典的な⼿磨きであることが歴史があると評価されたと感じていて、新たな視点としては、切子がテーブルの装飾やインテリア全体のコーディネートの一部として捉えられている面もある」と話す[資料5]。特にテーブルの上では、グラスを花器にするなど、陶器や銀食器の中で、切子は宝石のような食卓のアクセサリーとしての役割も期待されているようだ。
西山松之助によれば、「4、伝統は、伝達され保存されるためには、新鮮な現代人の意識によって再体験・再評価されるものである」(18)と述べている。
大阪切子が、海外に伝達され保存されるには、新鮮な視点によって再評価されることが重要と考えられる。日本人にもガラスや氷を涼しさの演出に使う感性があるが、酒器の印象の強い切子に対しても新たな視点を持てば大阪切子の活路が広がると考える。
6.まとめ
安田は、切子の魅力について、「ガラスの表面を削って磨いて模様を施す切子は、ガラスの透明感をより引き立たせることができ、仕上がりが宝石のようにキラキラと輝くところ」と話す[資料5]。大阪切子の持つ高級感、特別感、懐かしさは、人々を魅了し日常に彩りを添える。手磨きできらめく大阪切子を、文化資産として伝えていくべきであると考える。
参考文献
参考文献
【註釈】
(1)江戸切子は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)に基づき経済産業大臣が指定した伝統的工芸品である。
経済産業省 伝統的工芸品指定品目一覧(都道府県別)https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221116001/20221116001-2.pdf
2024年12月25日閲覧
(2)薩摩切子は、鹿児島県指定の伝統的工芸品である。
鹿児島県ホームページ https://www.pref.kagoshima.jp/kids/sangyou/dentoukougei.html 2024年12月25日閲覧
(3)安田公子
2003年 切子職人髙橋太久美氏に弟子入り
2008年 第14回新美工芸会展「新美工芸会奨励賞」
2011年 第17回新美工芸会展「大阪市長賞」
第40回日本伝統工芸近畿展「新人奨励賞」
第58回日本伝統工芸展 初入選
2012年 第41回日本伝統工芸近畿展 入選
2014年 第43回日本伝統工芸近畿展「大阪府教育委員会賞」
2015年 第44回日本伝統工芸近畿展 入選
2017年 独立 大阪市天王寺区に工房開設
LEXUS NEW TAKUMI PROJECT 2017 大阪府代表
2018年 第47回日本伝統工芸近畿展 入選
第14回日本のガラス展 入選
平成30年度全国伝統的工芸品公募展「中小企業庁長官賞」
2020年 第49回日本伝統工芸近畿展 入選
2020年 第67回日本伝統工芸展「日本工芸会新人賞」
(4)髙橋太久美
切子ガラス工芸研究所たくみ工房代表
新美工芸会会長
日本ガラス工芸学会会員
切子ガラス工芸研究所 たくみ工房代表
大阪切子保存会会長
切子ガラス工芸研究所たくみ工房 kiriko-takumi.com 2025年1月2日閲覧
(5)山口勝旦編『江戸切子 その流れを支えた人と技』、里文出版、1993年
(6)文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/267472
2024年12月25日閲覧
明治4年(1871)造幣寮創業
明治10年(1877)造幣局と改称
明治18年(1885)以後 民間に材料や機械を払下げた。造幣に必要な硫酸、ソーダ、石炭ガス、コークス、機械器具の生産にいたるまで、みずから行なう近代的造幣工場。
(7)山本孝造、『びんの話』、日本能率協会、1990年11月
(8)山本孝造、『びんの話』、日本能率協会、1990年11月
(9)日本経済新聞、2013年2月16日 https://www.nikkei.com/article/DGXNASIH06006_X00C13A2AA2P00/ 2024年12月25日閲覧
(10)佐々木順子、北海道立近代美術館編『びいどろ・ぎやまん・ガラス ―日本の硝子小史』北海道新聞社、1986年4月
(11)岡泰正、「和製ギヤマンは輸入ギヤマンを超えたか」、棚橋淳二他監修、『特別展「ギヤマン展ーあこがれの輸入ガラスと日本」図録』、神戸市立博物館、2014年7月、P11、30〜31行
(12)大阪切子保存会 Instagram https://osakakiriko.com 2025年1月2日閲覧
(13)小平田史穂、「さつま切子復元に関する記録」、『尚古集成館紀要』、(15)、尚古集成館、2016年
(14)山口勝旦編『江戸切子 その流れを支えた人と技』、里文出版、1993年
(15)山口勝旦編『江戸切子 その流れを支えた人と技』、里文出版、1993年、
P260、17行目〜18行目
現在、大阪の切子業者の相当数は、カメイガラスの協力工場となっている。宇良硝子加工所をはじめ、林、福岡、吉村、坂本、高橋、森、柴田、柏倉などの工房が数えられ、ここで加工されたカットグラスは、最後の艶出しまで手仕上げで完成される。
[原文のまま]
(16)大阪切子保存会 Instagram https://osakakiriko.com
2017年設立
会長 髙橋太久美
会員 安田公子、西川昌美、井住哲司、滝下浩子、たきのさゆり、辻原夕見、
松下洋介、近藤隆一、西眞り子(2025年1月現在)9名
設立の目的
「大阪切子保存会」は、手磨きにこだわる大阪切子の伝統的な技を後世に伝え、大阪切子のより一層の発展に努めることを目的として、2017年に設立しました。
職人の育成や作家の輩出を行うことで後世に大阪切子の技を伝承し、また展示会の開催やイベントへの出展によって大阪切子の発展や普及に努めています。
(17)RWGUILD rwguild.com/collections/artisan-kimiko-yasuda 2025年1月2日閲覧
(18)西山松之助、「伝統論」、『藝道と伝統』、吉川弘文館、1984年、P.454
【参考文献】
・土屋良雄編『薩摩切子』、紫紅社、1983年7月
・西山松之助、「伝統論」、『藝道と伝統』、吉川弘文館、1984年
・佐々木順子、北海道立近代美術館編『びいどろ・ぎやまん・ガラス ―日本の硝子小史』北海道新聞社、1986年4月
・山本孝造、『びんの話』、日本能率協会、1990年11月
・山口勝旦編『江戸切子 その流れを支えた人と技』、里文出版、1993年4月
・岡泰正、「和製ギヤマンは輸入ギヤマンを超えたか」、棚橋淳二・アンナ・ラメーリス、キティ・ラメーリス監修、『特別展「ギヤマン展ーあこがれの輸入ガラスと日本」図録』、神戸市立博物館、2014年7月、
・小平田史穂、「さつま切子復元に関する記録」、『尚古集成館紀要』、(15)、尚古集成館、2016年
【聞き取り取材】
大阪切子安田ガラス工房 安田公子氏
2024年5月23日、8月22日、10月30日
【参考ウェブサイト】
・切子ガラス工芸研究所たくみ工房 kiriko-takumi.com 2025年1月2日閲覧
・大阪切子安田ガラス工房 Instagram kirikoka 2025年1月2日閲覧
・大阪切子保存会 Instagram https://osakakiriko.com 2025年1月2日閲覧
・鹿児島県ホームページ https://www.pref.kagoshima.jp/kids/rekishi/satsumahan.html 2024年12月25日閲覧
・経済産業省 伝統工芸品指定品目一覧(都道府県別)https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221116001/20221116001-2.pdf 2024年12月25日閲覧
・島津薩摩切子 https://satsumakiriko.co.jp 2024年12月25日閲覧
・尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/about/ 2024年12月25日閲覧
・日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXNASIH06006_X00C13A2AA2P00/ 2024年8月15日閲覧
・大阪市立中央図書館 レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000112886
2025年1月7日閲覧
・造幣局 https://www.mint.go.jp/about/profile/guide_mint-history.html 2025年1月10日閲覧
・文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/267472
2025年1月10日閲覧