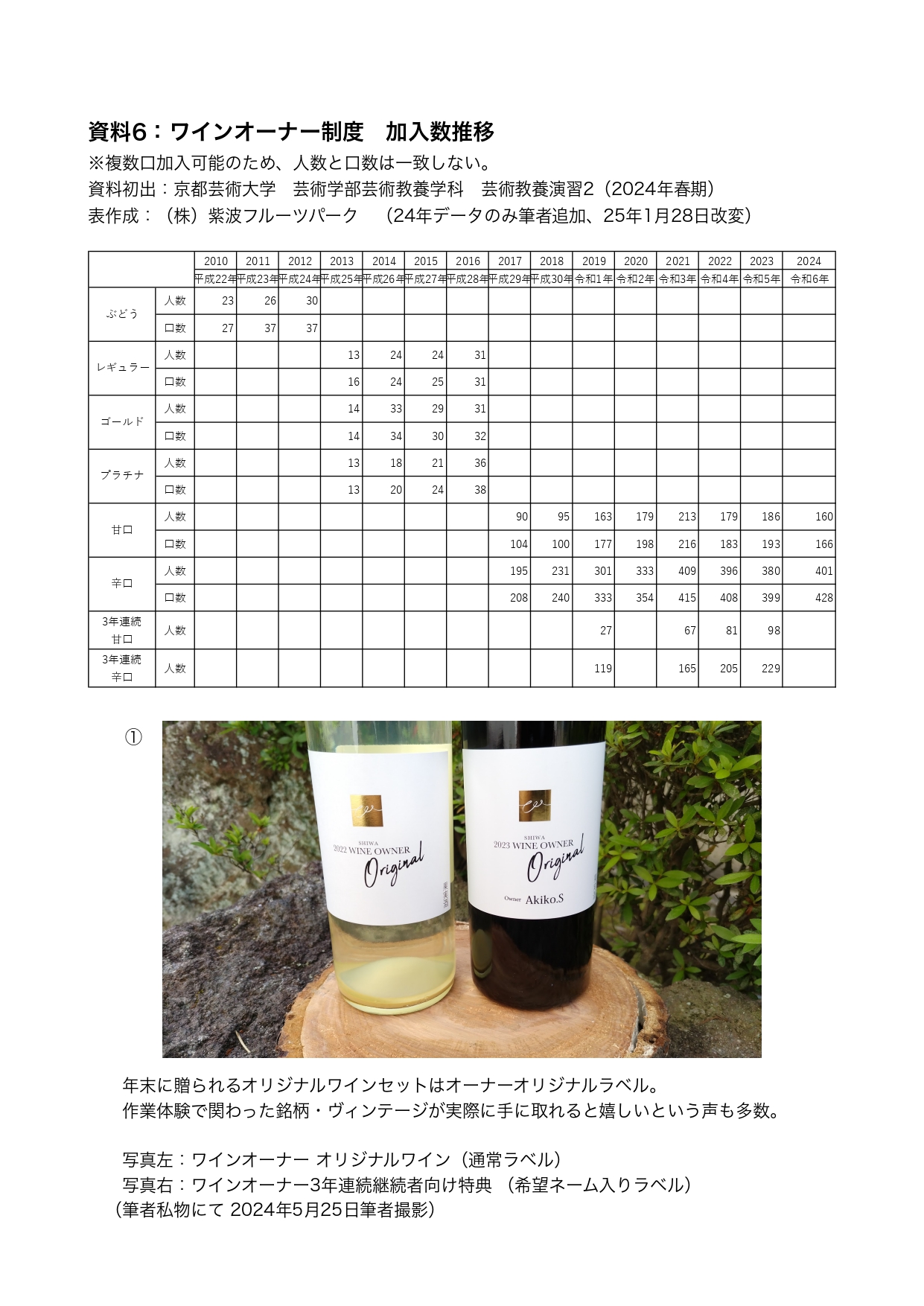円頓寺商店街にみるまちづくりと地域特色の継承
1. はじめに
名古屋駅から北東に徒歩約15分、那古野地区と呼ばれる地区に昭和の情緒が残るこじんまりとしたアーケード商店街が東西に2つ連なっている。円頓寺商店街と円頓寺本町商店街だ。近年、経営者の高齢化や生活スタイルの変化、少子高齢化などにより多くの商店街が衰退の途上におかれている。円頓寺商店街もかつてはその危機に瀕していたが、2007年に円頓寺界隈の活性化をコンセプトとしたボランティアグループ「那古野下町衆(1)」の結成を機に復興へと舵を切り、商店街だけでなく地域全体で活気を取り戻しつつある。本稿では円頓寺商店街の復興の取り組みに注目し、その取り組みから、地方都市商店街の活性化や街づくりへのヒントを考察する。
2. 基本データと歴史的背景
円頓寺商店街は、名古屋市西区の那古野地区にある、約30店舗が軒を連ねる全長約220メートルの全蓋式アーケードをもつ近隣型商店街である。(2)(3)名古屋駅と名古屋城の中間に位置しながらも、昭和の下町を想起させる雰囲気と、骨組みを利用しモダンな印象を与えるアーケードによってレトロさと近代感を調和させた商店街である。商店街にはコンビニやチェーン店がほぼなく、「ここに来ないと出会えない(4)」特色のある個人商店が多く並ぶ。
円頓寺商店街周辺には、名古屋がものづくり王国へと発展した変遷を物語る歴史的資源が多くみられる。円頓寺商店街のある那古野地区は、名古屋城築城の際に清須城下の武士や職人、商人、寺社や町名までも丸ごと移動させた「清州越」で形成された商人街である。(5)商店街東端にある五条橋の下を流れる堀川は、名古屋城築城普請の物資輸送のためにつくられ、名古屋城築城後も物流の大動脈として活用され、名古屋の発展に大きく寄与した。堀川西岸には水運を利用する商人を中心とした町人地が配置され、五条橋から堀川の間、現在も蔵や商人屋敷の残る四間道の辺りは「川筋商人」と呼ばれた大問屋が集まる中心地域であった。(6)円頓寺商店街周辺は、江戸時代には川筋商人や荷を運ぶ水主たちの利用する盛り場として、長久山圓頓寺が現在の位置に移転してからは門前町として発展。堀川沿いには中山道と東海道をつなぐ美濃路があり、周辺に多くの職人が住んだことから、名古屋扇子や名古屋友禅などの伝統工芸が生まれた。(7)明治に路面電車が延伸され、瀬戸方面からの交通の便が良くなったことに加え、大正には周辺に陶磁器や紡織などの工場ができ、円頓寺商店街一帯は多くの労働者や職人が利用する名古屋西北部最大の繁華街となった。(8)第二次世界大戦で空襲の被害にはあったものの、戦後も繁栄は続き、大正から昭和の中頃まで商店街は労働者や商店に勤める人々が日常の買い物や晩酌などに集まる大衆的な盛り場として地域を支えてきた。(9)しかし、市電の廃止や自動車の発達、周辺工場の移転などにより、昭和50年代には商店街の賑わいに陰りが見え始める。スーパーマーケットの台頭による消費者の買い物スタイルの変化や、後継者不足などで徐々に店舗数も減少。かつては50店舗以上あった店も平成の初めには23店舗までに数を減らした。(10)転換点は2007年の「那古野下町衆」結成であった。商店街の現状に危機感を持った有志の人達が集まり、イベントの実施や空き店舗対策に乗り出す。2009年に那古野下町衆から派生した「那古野地区店舗開発協議会ナゴノダナバンク(以下ナゴノダナバンク)(11)」が設立され、空き家・空き店舗再生プロジェクトを実施。2013年には秋の風物詩となるイベント、「第1回円頓寺秋のパリ祭」が開催され、毎年恒例の人気イベントとなる。2015年には老朽化していたアーケードがリニューアルされ、それを機にパリの商店街パッサージュ・デ・パノラマとアーケードを共通項とした姉妹提携を行うなど、商店街は活性化に向けて意欲的に活動を行っている。
3. 評価点
円頓寺商店街の特色として、まず一つは江戸から続く繁華街としての歴史と、それを目で見ることのできる歴史的資源が周辺地域に残っている点が挙げられる。東海道と中山道をつなぎ、物流の大動脈でもあった美濃路とその立地によって育まれた伝統工芸、江戸時代から続く菓子問屋街、川筋商人町の町並みを残す四間道、周囲には花街の名残りを残す古い建物も多く残り、現在では珍しくなった屋根神様(12)も見ることができる。商店街自体も昭和の姿そのままの古い店舗の存在によって昭和の風情を残しており、タイムスリップをしたような感覚を味わえる。活性化にむけた取り組みでは、商店街やこの地域の持つこうした特色を生かし、古い建物をリノベーションして再利用することで、情緒ある雰囲気を損なうことなく新たな店舗を誘致できるよう考慮された。また、商店街に個性ある魅力的な個人店が残っていたことから、同様の「ここに来ないと出会えない物、味、空間、人を備えた店(13)」をポリシーに、店の誘致プランが考え出された。円頓寺商店街では、建物の持ち主への許可や、事業者の選定を行う前に、その建物や商店街にあう事業や店の具体的な青写真を先に立て、その計画を持って大家への交渉、マッチングする事業者への声掛けを商店街側から行い、「一本釣り」することで、空き店舗の解消につなげていった。(14)この活動が、円頓寺商店街のもう一つの特色であり、この方法を採用することによって、商店街は現行の店を邪魔することなく、商店街の風情を残したまま、空き店舗を解消することが可能となった。
4. 他の商店街との比較
通常、空き店舗がある場合は、不動産会社などを通じて情報を外部に公開し、広く事業者を探す手法が一般的である。円頓寺と共に名古屋の三大商店街と言われ、名古屋で最も勢いがあり、土日で約7万人、平日でも約3万人と多くの客を呼ぶ大須商店街(15)でもその方法で事業者を探している。年間7~8%の店舗が入れ替わっている(16)という大須商店街ではこの方法を採用することで、流行を取り入れた店舗が流動的に新規参入し、時代の流れに沿った商店街の姿が維持できるし、流行と共に店が循環することで商店街の停滞化を防ぐこともできる。現に大須は門前町、歓楽街、電気街、オタクカルチャーの街へと時代と共に少しずつ姿を変え、新旧多種混淆のごった煮の街としての個性を築いている。(17)一方でこの方法は、商店街に活気があるからこそ採用できる方法でもある。一時の円頓寺商店街のように、道に人気がなく、閑散とした商店街に出店をしようとする事業者を一般から募集するのは難しいと考えられる。
5. 今後の展望
那古野下町衆やナゴノダナバンクの取り組みにより、復興の道を進み始めた円頓寺商店街。新しい店や出店希望者も増え、那古野エリアは名古屋の観光地の一つとして紹介されるようになり、商店街を訪れる人も増えた。しかし、休日や夕方以降の人出は増えたものの、平日の昼間はまだ閑散としており、イベント頼りではない日常使いできる商店街としては課題も多い。特徴的な店は多いものの、青果店やスーパーのような日常の買い物ができる店や、食べ歩きができる店は少なく、ベンチなどの休憩場所もない。近年、商店街は地域のコミュニティの一つとしても注目されている。周囲の人たちが日常的に利用し、交流を深めることができる「場」として商店街がどのような役割を果たせるのか、商店街にはまだまだ多くの可能性が秘められていると言える。また、ナゴノダナバンクの取り組みは行政からも注目され、名古屋市の商店街活性化プロジェクト「ナゴヤ商店街オープン(18)」の取り組みへと繋がった。この取り組みを通して名古屋市内の商店街は商店街同士で学びあう横の広がりを持ち始めており、商店街を起点としたまちづくりは名古屋市内全体へと広がっている。
6. まとめ
土地にはその土地の持つ風土や歴史があり、街にはその年月がその地域の表情として現れ、その表情の違いが街の特色となり、魅力となる。円頓寺商店街が行ってきた取り組みは、その地域の持つ歴史や特色を生かしたものであり、その取り組みは商店街のみならず、地域の復興にもつながっている。近年、日本各地の商店街や駅前は再開発などによって、その街の持つ歴史や特徴を失いつつある。きれいではあるが特徴のない街へ変わってしまった街に人はどれほどの愛着を持ち、魅力を感じるだろうか。ナゴノダナバンクの代表である市原は、建物の所有者が建物の利用を決める際の理由として「自分や先祖が大切にしてきた建物への愛着や価値をわかって使ってもらえる」ことと「それが街の活性化に役に立つ」のふたつがあると述べている。(19)同じことは建物だけではなく街にも言える。土地にはそこに住む人々や訪れた人々の愛着や思い出、歴史がある。円頓寺商店街の取り組みは、そうした人々の歴史や記憶を大切にしたからこそ成功したと言える。歴史は遠く過ぎ去ったものではなく、様々な人によって日々紡がれ、連綿と引き継がれてきたものである。それに着目し、要とした円頓寺商店街の取り組みは商店街のみならず、まちづくりを行うためのひとつの模範となるのではないだろうか。
-
 (画像1)円頓寺商店街周辺図
(画像1)円頓寺商店街周辺図 -
 (写真1)円頓寺商店街西側入口(撮影日2024.5.9)
(写真1)円頓寺商店街西側入口(撮影日2024.5.9) -
 (写真2)円頓寺商店街東側入口(撮影日2025.1.16)
(写真2)円頓寺商店街東側入口(撮影日2025.1.16) -
 (写真3)商店街中心地(撮影日2025.1.16) 透明度の高い屋根から明るく差し込む日差しによって、アーケードの骨組みや吊り下げランプが強調されるモダンな景観。
(写真3)商店街中心地(撮影日2025.1.16) 透明度の高い屋根から明るく差し込む日差しによって、アーケードの骨組みや吊り下げランプが強調されるモダンな景観。 -
 (写真4)円頓寺商店街東側入口横にある天然酵母のパン屋「芒種」(撮影日2025.1.16) 前の店の外観をそのまま利用して営業している。
(写真4)円頓寺商店街東側入口横にある天然酵母のパン屋「芒種」(撮影日2025.1.16) 前の店の外観をそのまま利用して営業している。 -
 (写真5)円頓寺商店街中ほどにある「松川屋道具店」(撮影日2025.1.16) 夏には店頭に風鈴が並び、商店街に涼の音を届ける。
(写真5)円頓寺商店街中ほどにある「松川屋道具店」(撮影日2025.1.16) 夏には店頭に風鈴が並び、商店街に涼の音を届ける。 -
 (写真6)円頓寺商店街に隣接する四間道(撮影日2024.5.9) 元禄13年の大火の後、防火などの理由から道路幅を4間に広げたため、四間道と呼ばれるようになった。江戸時代の蔵や町家などが残り、名古屋の「町並み保存地区」に登録されている。
(写真6)円頓寺商店街に隣接する四間道(撮影日2024.5.9) 元禄13年の大火の後、防火などの理由から道路幅を4間に広げたため、四間道と呼ばれるようになった。江戸時代の蔵や町家などが残り、名古屋の「町並み保存地区」に登録されている。 -
 (写真7)五条橋上から臨む堀川(撮影日2024.5.9) 円頓寺商店街東側にある五条橋とその下を流れる堀川。堀川はかつては名古屋の物流の大動脈として利用された。
(写真7)五条橋上から臨む堀川(撮影日2024.5.9) 円頓寺商店街東側にある五条橋とその下を流れる堀川。堀川はかつては名古屋の物流の大動脈として利用された。
参考文献
【註】
(1)「那古野下町衆」は、2007年に円頓寺商店街、円頓寺本町商店街、四間道界隈の若手商店主を中心に、コンサルタント、大学研究室、企業、クリエイターなど、那古野地域に愛着をもつ人々によって結成された団体。那古野地区周辺のまちづくりについて話し合い、イベントの企画誘致やマップの作成、空き店舗対策など多岐にわたる活動を行っている。
那古野下町衆HP http://nagosyu.net/、(閲覧2025.1.8)
(2)円頓寺商店街online https://endojishotengai.com/home.html、(閲覧2025.1.8)
(3)中小企業庁の「商店街実態調査報告書」で用いられている商店街のタイプ別分類。「近隣型商店街」「地域型商店街」「広域型商店街」「超広域型商店街」の4つがある。円頓寺商店街は中小企業庁「はばたく商店街30選」2016において「最寄品中心の商店街で地元住民が日用品を徒歩又は自転車等により買い物を行う商店街」である近隣型商店街に分類されている。
中小企業庁HP「令和3年度商店街実態調査報告書 概要版」、https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2022/download/220408shoutengai01.pdf、(閲覧2025.1.8)
中小企業庁HP「はばたく商店街30選」、円頓寺商店街(円頓寺商店街振興組合)、https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/monozukuri300sha/2016/S15.pdf、(閲覧2025.1.8)
(4)(12)山口あゆみ『名古屋円頓寺商店街の奇跡』講談社+α新書、2018年、p.63
(5)『愛知県史 通史編4 近世1』愛知県史編さん委員会、2019年、p.54。
(6)『愛知県史 通史編6 近代1』愛知県史編さん委員会、2017年、p.144
名古屋市HP「堀川の歴史」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-4-4-6-0-0-0-0-0-0.html、(閲覧2025.1.8)
(7)物流の大動脈であった美濃路には人や物が多く行き交うため、周辺には盛り場や門前町など町人町が形成された。そこに住む職人によって名古屋扇子や友禅、提灯、和凧などの伝統工芸も生まれた。
エキ/シロ/ナビHP「・見る〈美濃路〉」https://ekishiro.jp/bukken/132/、(閲覧2025.1.8)
ものづくり文化の道HP「ものづくり文化の道とは?」http://www.nagoya-monodukuri.net/monobun.html、(閲覧2025.1.8)
(8)代表的な工場は「豊田織機」と「日本陶器(現:ノリタケ)」。工場移転のため、現在は「トヨタ産業技術記念館」と「ノリタケの森」になっている。
ノリタケHP「ノリタケのあゆみ」https://www.noritake.co.jp/company/about/history/、(閲覧2025.1.8)
ノリタケの森HP「散策する―歴史を感じる―」https://www.noritake.co.jp/mori/look/walk_relax/、(閲覧2025.1.8)
トヨタ産業技術記念館HP「当館について」https://www.tcmit.org/about/history、(閲覧2025.1.8)
(9)『大正昭和名古屋市史 第9巻 地理編』名古屋市役所、1955年、p.78、p.85
『大正昭和名古屋市史 第3巻 商業編(上)』名古屋市役所、1954年、pp.573-574
(10)山口あゆみ『名古屋円頓寺商店街の奇跡』講談社+α新書、2018年、p.34
(11)那古野下町衆の「空き店舗対策チーム」として2008年活動開始。活動の迅速さを向上するため2009年に「那古野地区店舗開発協議会ナゴノダナバンク」として那古野下町衆より独立、2018年、法人化し「株式会社ナゴノダナバンク」として、空き家対策や古民家リノベーションなどの不動産活用、イベント企画運営などの活動を行っている。
ナゴノダナバンクHP https://nagoban.com/about/、(閲覧2025.1.8)
(13)名古屋市域で多くみられた民家の屋根に設けられた小さな祠。明治初期からはじまり、昭和初期に広まったと考えられ、昭和30年代頃まで建てられた。長屋が密集して、地上に建てる土地がなかったからや、みんなで拝むのに都合がよかったからなど、屋根の上に社を設けた理由はいくつか説がある。住宅が密集した下町で祀られるため、火難除けや疫病を防ぐ津島神社、秋葉神社に熱田神宮を加えた三社がまつられることが多かった。生活や地域社会の変化に伴い祀られなくなり、建て替えや都市開発などによって数を減らしている。
『中日新聞縮刷版 平成18年7月号(第35巻7号)』中日新聞社、2006年、p.752
名古屋市博物館HP コレクション資料紹介「屋根神」https://www.museum.city.nagoya.jp/collection/data/data_09/index.html、(閲覧2025.1.8)
(14)山口あゆみ『名古屋円頓寺商店街の奇跡』講談社+α新書、2018年、p.65
愛知県HP 商店街活性化モデル事例集(2023年度実施)「円頓寺商店街(名古屋市西区)PDFファイル」https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/530099.pdf、(閲覧2025.1.8)
(15)(17)大須商店街は名古屋市中区大須2丁目から3丁目付近にわたる商業地区。江戸時代に大須観音の門前町として発展し、現在は約1200の店舗・施設がある。エリア内の8つの商店街通りの総称で、万松寺通商店街振興組合・大須新天地通商店街振興組合・名古屋大須東仁王門通商店街振興組合・大須仁王門通商店街振興組合・大須観音通商店街振興組合・大須門前町商店街振興組合・大須本通商店街振興組合・大須赤門通商店街振興組合の8つの振興組合からなる大須商店街連盟によって運営されている。中小企業庁「がんばる商店街77選」では広域型商店街(「百貨店、量販店を含む大型店があり、最寄品より買回り品が多い商店街」)に分類されている。
大須商店街HP「@大須」https://osu.nagoya/ja/、(閲覧2025.1.8)
中小企業庁HP「がんばる商店街77選」、にぎわいあふれる商店街「大須商店街連盟」、https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/shoutengai77sen/nigiwai/4chuubu/1_chuubu_19.html、(閲覧2025.1.8)
(16)LIFULL HOMES PRESS「斜陽からの再生!なぜ大須商店街はシャッター通りにはならず賑わいを取り戻せたのか(公開日2015.1.16)」、https://www.homes.co.jp/cont/press/buy/buy_00283/、(閲覧2025.1.8)
PRESIDENT Online「週末に鬼ごっこができるほどガラガラだった…名古屋・大須商店街が「日本一元気な商店街」に再生できたワケ(公開日2023.6.25)」、https://president.jp/articles/-/70824、(閲覧2025.1.8)
(18)NAGOYA SHOTENGAI OPEN HP https://shotengaiopen.nagoya/、(閲覧2025.1.8)
名古屋市HP「ナゴヤ商店街オープン2024(令和6年度商店街商業機能再生モデル事業)」 https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000174161.html、(閲覧2025.1.8)
(19)山口あゆみ『名古屋円頓寺商店街の奇跡』講談社+α新書、2018年、p.69
【画像・写真】
画像1:地理院地図(電子国土Web)の画像をもとに執筆者が作成
地理院地図(電子国土Web)https://maps.gsi.go.jp/、(閲覧2025.1.13)
写真1~7:筆者撮影、撮影場所:(写真1~5)円頓寺商店街、(写真6)四間道、(写真7)五条橋橋上から南方向を撮影。
【参考文献】
『愛知県史 通史編8 近代3』愛知県史編さん委員会、2019年
『大正昭和名古屋市史 第1巻 緒論及原始産業編』名古屋市役所、1953年
『西区70年のあゆみ』西区制70周年記念誌編纂委員会、1978年
山田寂雀・西岡寿一『名古屋区史シリーズ3 西区の歴史』愛知県郷土資料刊行会、1983年
名古屋タイムズアーカイブス委員会編『昭和イラストマップ 名古屋なつかしの商店街』風媒社、2014年
『円頓寺商店街のあゆみ―アーケード設立50年を迎えて―』円頓寺商店街振興組合、2015年
新雅史『商店街はなぜ滅びるのか 社会・政治・経済史から探る再生の道』光文社新書、2012年
広井良典編『商店街の復権―歩いて楽しめるコミュニティ空間』ちくま新書、2024年
広井良典『コミュニティを問いなおす―つながり・都市・日本社会の未来』ちくま新書、2009年
満薗勇『商店街はいま必要なのか 「日本型流通」の近現代史』講談社現代新書、2015年
中沢孝夫『変わる商店街』岩波新書、2001年
田上敦士「コミュニティ再生の視点からの商店街の再生について」『広島商船高等専門学校紀要42巻』、pp.21-28、2020年、https://www.jstage.jst.go.jp/article/hiroshimashosenkiyo/42/0/42_5/_pdf/-char/ja、(閲覧2025.1.8)
岩田悠佑「平成23年度 都市センター研究報告 那古野地区まちづくりの方向性:那古野スタイルの構築」『アーバン・アドバンス=Urban advance/名古屋まちづくり公社名古屋都市センター編』、pp.67-73、2013年、http://www.nup.or.jp/nui/user/media/document/investigation/h23/nagono.pdf、(閲覧2025.1.8)
名古屋市HP 那古野一丁目地区景観協定「那古野一丁目地区景観協定の概要(地区図)」https://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/contents/0000141/141180/kyoutei_gaiyou.pdf、(閲覧2025.1.8)
名古屋市HP 美濃路(みのじ)まち歩きマップ&ウォーキングガイド動画「美濃路(みのじ)まち歩きマップ」 https://www.city.nagoya.jp/nishi/cmsfiles/contents/0000127/127856/minojimap-map.pdf、(閲覧2025.1.8)
名古屋市HP「『町並み保存地区』のあらまし―四間道町並み保存地区―」 https://www.city.nagoya.jp/kankobunkakoryu/cmsfiles/contents/0000080/80120/aramashi_shikemichi.pdf、(閲覧2025.1.8)
名古屋歴史ワンダーランドHP 名古屋西北部最大の商店街 円頓寺商店街(最終更新日2022.3.4)https://www.nagoya-town.info/bunnka/nisi~endouji~syoutengai/nisi~enndouji~syoutenngai.html、(閲覧2025.1.8)
名古屋の商店街検索サイト「金シャチ商店街」 円頓寺商店街振興組合、https://www.kinsyachi.com/street/04027/、(閲覧2025.1.8)
名古屋の商店街検索サイト「金シャチ商店街」 円頓寺本町商店街振興組合、https://www.kinsyachi.com/street/04028/、(閲覧2025.1.8)
クラフトマルシェ in 円頓寺本町HP https://endojihonmachi.com/、(閲覧2025.1.8)
reallocal名古屋 インタビュー「名古屋最古の『円頓寺商店街』起死回生の立役者たちの心意気!」(公開日2021.4.16) https://www.reallocal.jp/87598、(閲覧2025.1.8)